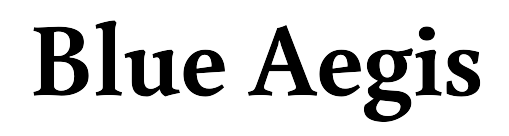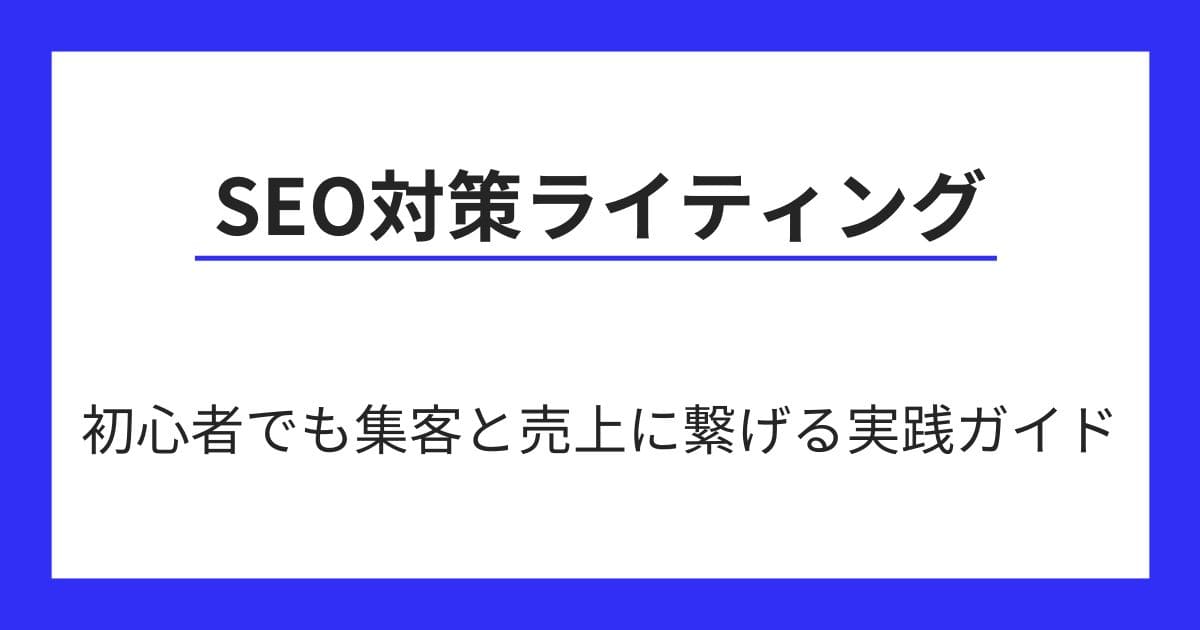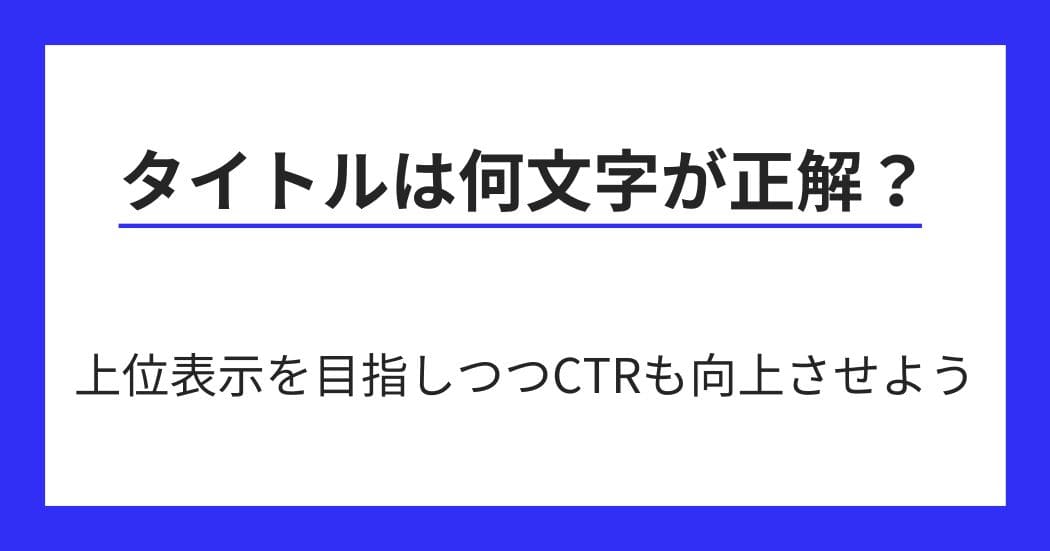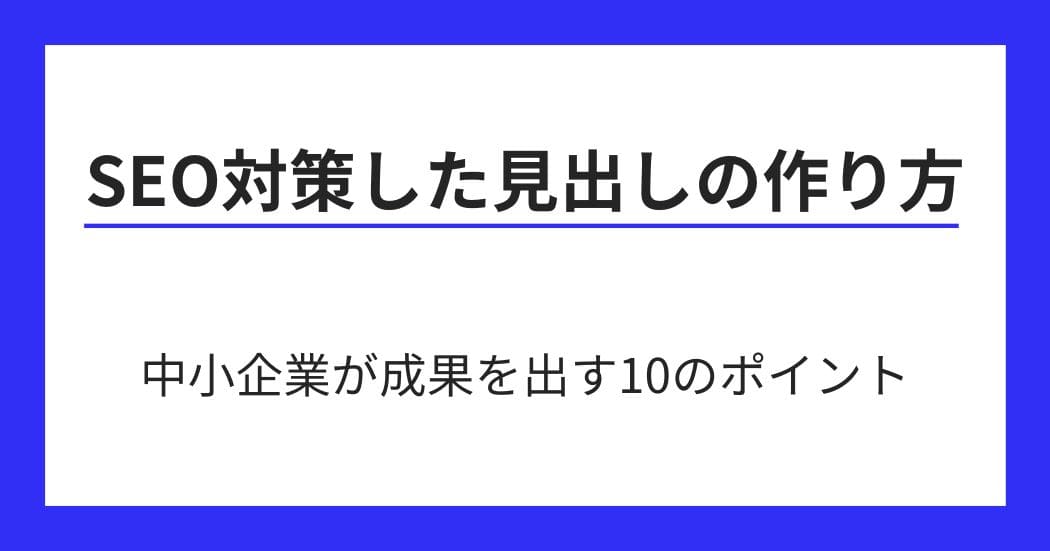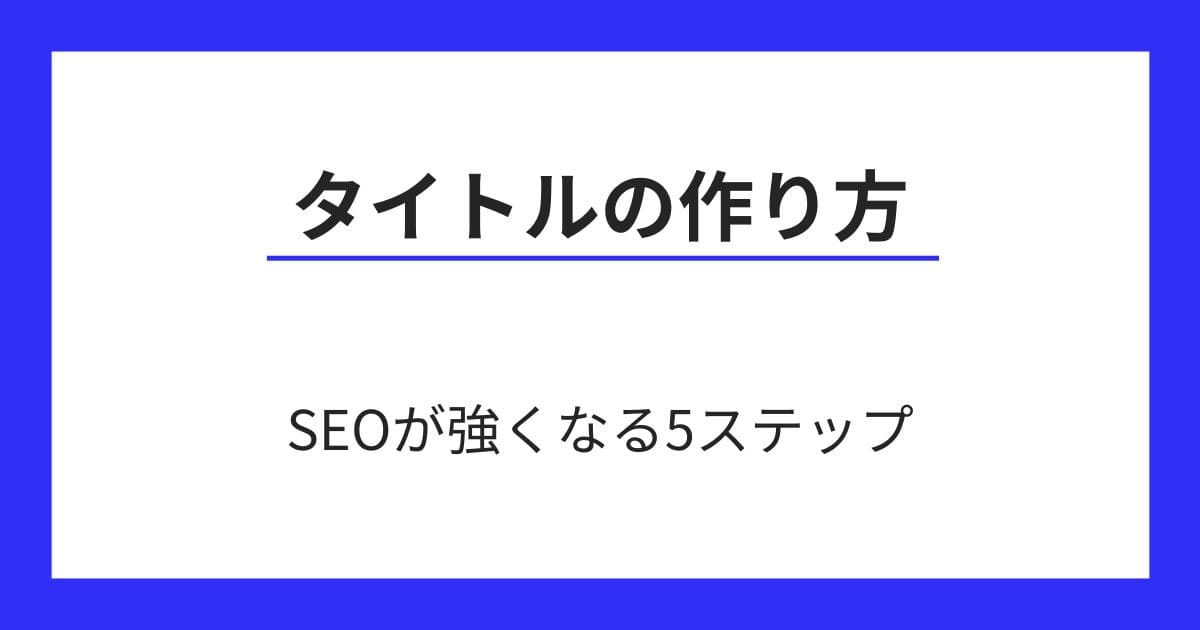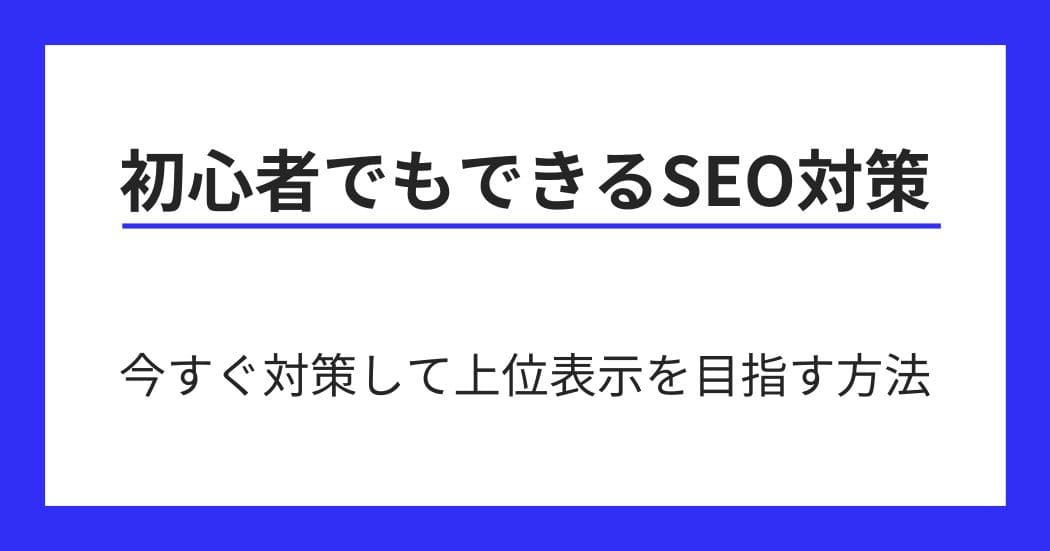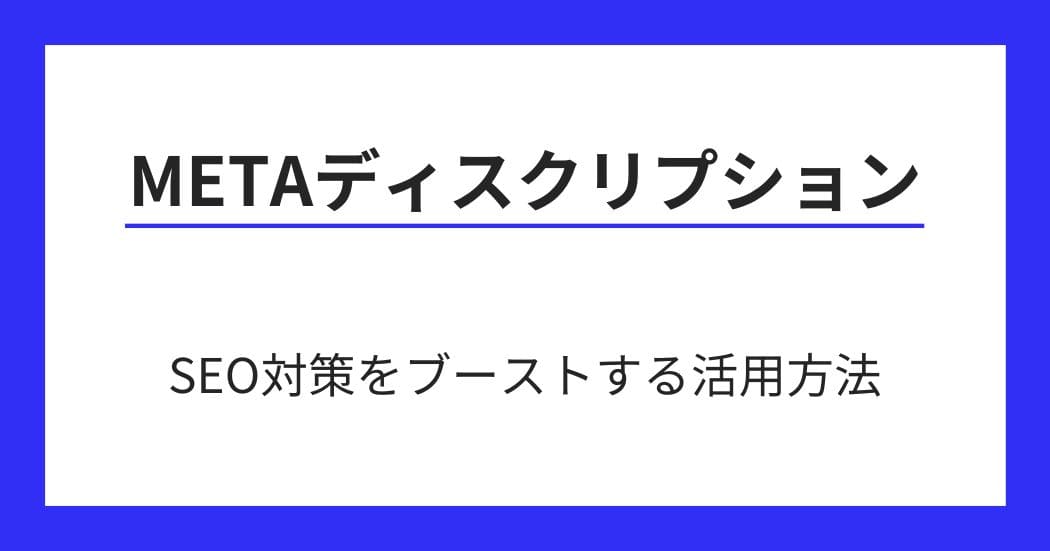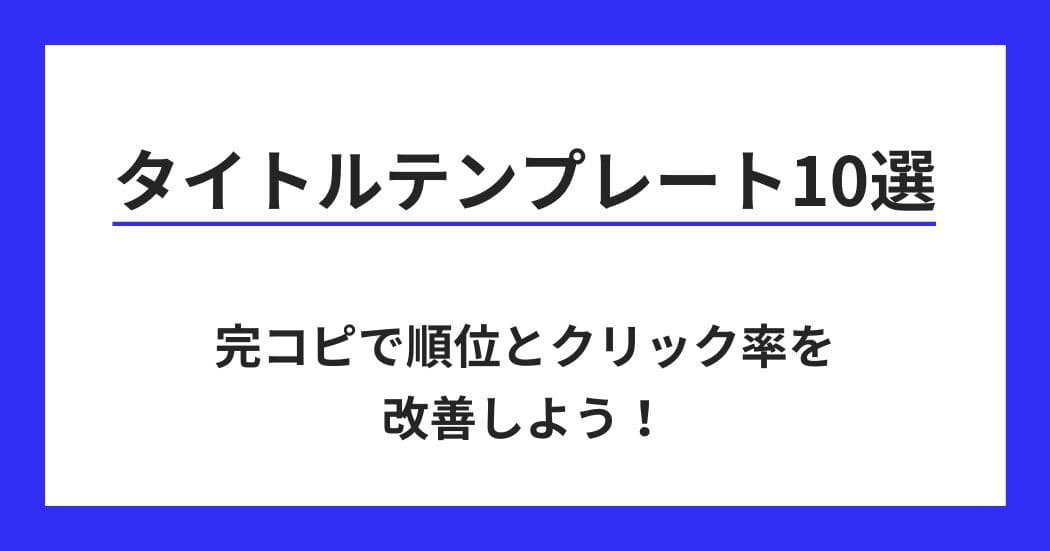SEO対策したライティングで、記事を検索結果の上位に押し上げたいけど、やり方が分からない。
そんな中小企業の経営者に、本記事では今日から実践できるSEOライティングの具体的な手法を、ステップバイステップで詳しく解説します。
デジタルマーケティングの専門知識やSEOに関する知識がない方でも、具体的な対応方法が分かり、実践することができます。
中小企業経営者や個人事業主の方が、限られた時間とリソースの中で最大の成果を出せるよう、実践的で再現性の高い内容に絞ってお伝えしていきます。
この記事を読むと分かること
- 検索エンジンに評価される記事の書き方(10の実践手法)
- SEO対策ライティング実践のポイントやコツ
- SEO対策ライティングについてのFAQ
SEO対策したライティングの効果的なやり方10選
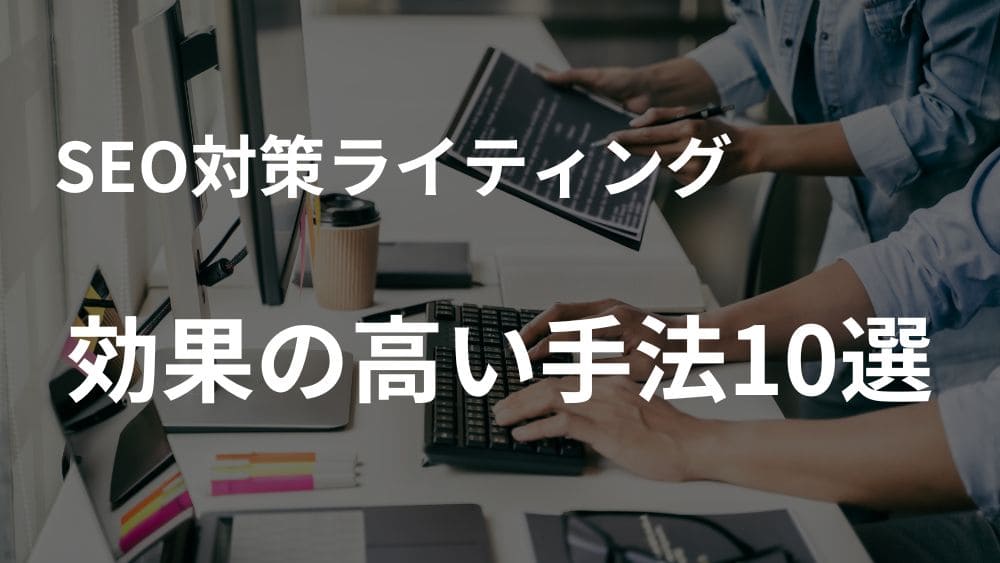
SEOに強い記事をライティングするやり方は、体系的に学べば決して難しくありません。
このセクションでは、SEO未経験の方でも今日から実践できる10の重要な手法を、具体例とともに解説します。
これらの手法をマスターするだけで、検索エンジンとユーザーの両方に評価される記事が書けるようになり、アクセス数と問い合わせ数の改善が期待できます。
1.キーワードを自然に配置したライティングをする
SEO対策したライティングの最も基本的なルールは、狙ったキーワードを記事内に自然に配置することです。
ただし、とにかく「キーワードを詰め込めばいい」ではありません。
SEO対策したライティングにおいて重要なのは、文脈にそった「自然さ」と「適切な場所」にキーワードを配置するということです。
- 記事冒頭(導入文・リード文)へのキーワード配置
記事の最初(いわゆる導入文、リード文とも言われます)の100文字以内にメインキーワードを含めることで、記事のテーマを明確に示します。 - 本文中への自然な配置
記事本文中にキーワードを積極的に使用しキーワードの密度を上げます。
積極的に使用しつつも文脈に合わせて、あくまでも自然に使用することを心がけてください。
詰め込もうとして不自然に使用すると、人間からもGoogleからも評価は下がります。
例:「外壁塗装 費用」の場合- 「外壁塗装の費用を抑えるためには、適切な時期選びが重要です」
- 「一般的な外壁塗装では、費用の60%が人件費として計算されます」
- 共起語の活用
SEO対策の効果を上げるなら、キーワードだけでなく「共起語」も自然に使用したライティングを行ないましょう。
例えば「外壁塗装 費用」なら「外壁」「相場」「外壁塗装」などが共起語になります。
ラッコキーワードなどのSEOツールを活用すれば、共起語などを確認できます。
キーワード密度の目安
全文字数の1〜3%程度が適切です。1,000文字の記事なら、メインキーワードが10〜30回程度自然に含まれていれば十分です。
実践のコツ
私たちは気づかないうちに主語を省略しがちです。
主語はキーワードとして設定されていること多いので、省略された主語に気付く事ができれば、自然とキーワードの密度を上げることが出来ます。
キーワードをタイトル(H1)と主要な見出し(H2、H3)に含める事も大切なポイントです。
★タイトルと見出しの記事へリンクさせる
2.見出し直下は端的に要点をライティングする
見出し(H2、H3)の直下に書く最初の文章は、「セクションリード」と呼ばれ、SEO対策されたライティングでも重要な部分です。
セクションリード部分で「この見出しではどのような疑問に答えているのか?」「この見出しを読むと何が分かるのか?」を端的に説明することで、読者に続きを読む価値があることを伝えることができます。
端的に答えられる事の出来る内容であれば、セクションリードでシンプルに主張や答えを出してしまうのも一つの手です。
- 読者の継続読書を促す
見出しを見て「自分の知りたい情報がありそう」と感じた読者に、「確実にここに答えがある」ことを伝えます。 - 検索エンジンへの内容説明
クローラーにとって、各セクションで何について説明しているかを明確に示す重要な手がかりになります。
SEOに強いセクションリードの書き方
❌悪い例: 「外壁塗装について詳しく説明していきます。まず基本的なことから始めて、順番に解説していきましょう。」
⭕良い例: 「外壁塗装の費用は、30坪の住宅で80万円〜120万円が相場です。ただし、使用する塗料や工法によって価格は大きく変わるため、以下の3つのポイントを理解しておくことが重要です。」
良い例では、読者が最も知りたい「具体的な費用相場」を冒頭で明示し、続きを読む理由(3つのポイント)も示しています。
実践のコツ
- 何を伝えているセクションなのかを端的に書く。場合によっては結論を最初に書く
- 具体的な数字や事実を含める
- 「以下で詳しく解説します」など、続きへの期待を持たせる
3.見出しごとに一つのテーマに絞ったライティングをする
読みやすく、SEO対策効果の高い記事をライティングするためには、1つの見出し(H2、H3)では1つのテーマだけを扱う「ワンヘッディング・ワンテーマ」の原則を守ることが重要です。
これにより、見出し単位で伝えるべき事がシンプルになり、読者にも検索エンジンにも正しく記事の内容が伝わり、評価が向上します。
★見出し記事へのリンク
- 見出しで約束した内容だけをライティングする
見出しで示したテーマから脱線せず、その内容だけに絞って説明します。
関連する必要な内容を伝える場合は、別見出しにするか、別記事にしてリンクを張るようにして下さい。
❌悪い例
「H3:外壁塗装の費用相場」配下での文章
「外壁塗装の費用は30坪で80万円が相場です。ところで、業者選びも重要で、相見積もりを取ることをおすすめします。また、工期は天候に左右されるので梅雨時期は避けた方が良いでしょう。」 →費用の話から業者選び、工期の話まで混在
⭕良い例
「H3:外壁塗装の費用相場」配下での文章
「外壁塗装の費用は、30坪の住宅で80万円〜120万円が相場です。この価格差は使用する塗料によって決まり、シリコン塗料なら80万円、フッ素塗料なら100万円、無機塗料なら120万円程度となります。」 →費用相場というテーマに完全に特化 - 他のテーマに触れる場合は別の見出しへの誘導を使う
関連する内容を伝えたい場合は、文章内で脱線するのではなく、適切な見出しへの誘導を行います。 - 段落分けで内容を整理する
1つの見出し配下でも、内容を論理的な段落に分けて整理します。
本ページ内「結論→理由→具体例の型で本文を展開する」を参照
実践のコツ
記事を書く前に、まず見出し構成だけを作成してみてください。
各見出しが独立したテーマになっているか、全体の流れが論理的かを確認してから本文執筆に入ると、一貫性のある分かりやすい記事になります。
4.画像やデータで理解を補強する
文字だけの記事は、読者にとって負担が大きく、画面上に文字ばかりが並んだ状態は離脱の原因になります。
PC画面上で制作した記事は、スマホで見た時に画面一杯に文字が並んでいる状態になりやすいです、注意しましょう。
SEO対策したライティングに画像やデータ表などを適宜配置することで、文字ばかりの圧迫感を減らし理解度の向上と滞在時間の延長を図ることができます。
- 理解を助ける図解・グラフ
複雑な情報は、表やグラフを使用して視覚化することで、格段に分かりやすくなります。
文章よりは表の方が分かりやすいし、表よりもグラフにして掲載するほうが分かりやすいです。 - 実例を示す写真
Before・Afterの写真や施工過程の写真は、読者の理解と信頼を大幅に向上させます。 - 権威性を示すデータ
業界統計や調査結果を引用することで、記事の信頼性が高まります。
出典は必ず明記しましょう。
画像データのSEO効果を得る為の対応
- 画像ファイル名は内容が分かるように命名(例:gaiheki-tosou-kosuto-hikaku.jpg)
- alt属性(代替テキスト)に適切な説明を記載
- 画像サイズを最適化してページ表示速度を向上
実践のコツ
- 見出しの直後に関連する画像を配置
- 長い文章が続く場合は、途中に区切りとして画像を挿入
- スマートフォンでも見やすいサイズに調整
5.導入文で検索意図に直結した答えの存在を提示する
記事の導入文(リード文)は、読者が「この記事を読み続けるかどうか」を判断する重要な部分です。
ここで読者の疑問に共感を示しつつ、「この記事にその答えが詳しく書いてある」ことを明示することで、読者の離脱を防ぎ、滞在時間を大幅に向上させることができます。
- 読者の課題・悩みへの共感
検索キーワードから推測される読者の悩みを明確に言語化し、共感を示します。
例:「外壁塗装 費用」の場合 「外壁塗装を検討しているけれど、『いくらかかるのかわからない』『業者によって見積もりが全然違う』そんな不安を感じていませんか?」 - 検索意図への回答予告
読者が最も知りたい情報について、この記事で詳しく解説することを予告します。
検索意図に対して答えている事が分かれば、読者は記事を読み進んでくれます。
例:「外壁塗装の費用で最も気になる『30坪の住宅でいくらかかるのか』という疑問。この記事では、塗料別の詳細な相場から費用を左右する要因まで解説します。」 - 記事で得られる価値の明示
この記事を読むことで、読者がどのような状態になれるのかを明確に伝えます。
記事が提供する価値を手に入れたいと感じる読者は、よりしっかりと記事を読んでくれます。
例:「読み終わる頃には、適正価格を見極め、信頼できる業者を選び、外壁塗装で失敗しないための全知識が身につきます。」 - 読者の背景・状況への配慮
記事のターゲット読者像を明確にし、「自分のための記事だ」と感じてもらいます。
明確にしたターゲット読者増が感じてい疑問などを先周りして解決するライティングを行なうことで、価値がより高くなります。
例:「初めて外壁塗装を検討される方でも、業者に騙されることなく適正価格で満足いく工事ができるよう、分かりやすく説明していきます。」
導入文のテンプレート
- 【共感】 ○○でお困りではありませんか?
- 【回答予告】 この記事では、○○について詳しく解説します。
- 【価値提示】 読み終わる頃には、△△できるようになります。
- 【読者配慮】 ○○の方でも、△△できるよう、分かりやすく説明していきます。
6.結論→理由→具体例の型で本文を展開する
各見出し配下の本文は、「PREP法」の応用である「結論→理由→具体例」の型で展開することで、論理的で説得力のある文章を書くことができます。
この型を使うことで、読者の理解度が向上し、検索エンジンからも高く評価されます。
P(Point:結論)
見出しで約束した内容の答えを、最初に明確に提示します。
例:「H3:外壁塗装の費用相場」の場合 「外壁塗装の費用は、一般的な30坪の住宅で80万円〜120万円が相場です。」
R(Reason:理由)
なぜその結論になるのか、根拠や理由を説明します。
例:「この価格差は、主に使用する塗料のグレードによって決まります。塗料は大きく3つのグレードに分かれており、それぞれ耐用年数と価格が異なるためです。」
E(Example:具体例)
データ、事例、体験談などの具体例で理解を深めます。
例:塗料グレード別の費用比較(30坪住宅の場合)
・シリコン塗料:80万円(耐用年数10-12年)
・フッ素塗料:100万円(耐用年数15-18年)
・無機塗料:120万円(耐用年数20-25年)
P(Point:結論の再提示)
要点をまとめ、読者の行動を促します。(H2やH3単位の場合は省略することが多いです)
例:「つまり、外壁塗装の費用を正確に把握するには、どの塗料を使うかを最初に決めることが重要です。長期的なコストパフォーマンスを考えて選択しましょう。」
実践のコツ
この型に慣れるまでは、見出しを作った段階で「P(結論)」「R(理由)」「E(具体例)」「P(まとめ)」の4つの要素を箇条書きでメモしてから本文執筆に入ると、論理的な文章が書きやすくなります。
7.オリジナリティ性の高い一次情報を盛り込む 重要
SEO対策のライティング手法として最も重要と言えるのは、他サイトにはない独自の情報を記事に盛り込むことです。
Googleの品質評価基準の中に、E-E-A-T(Experience-経験、Expertise-専門性、Authoritativeness-権威性、Trustworthiness-信頼性)と呼ばれる概念があり、オリジナリティ性の高い一次情報を盛り込んだライティングは最初のE(Experience-経験)に該当します。
Googleは「オリジナリティの高いコンテンツ」を最も高く評価するため、一次情報や実体験を積極的に活用することで、競合記事に大きな差をつけることができます。
一次情報が重要な理由
Googleの品質評価ガイドラインでは、「他のサイトの情報をまとめただけの記事」よりも「独自の調査・経験・知見を含む記事」を優先的に上位表示するとしています。特に中小企業にとって、これは大手企業に勝つための重要な戦略となります。
1. 自社の実績・事例データ
具体的な数字や成果を使って説得力を高めます。
例:「弊社で過去3年間に手がけた外壁塗装200件のデータを分析すると、フッ素塗料を選んだお客様の97%が『耐久性に満足』と回答しています。」
2. 顧客の生の声・体験談
実際のお客様の言葉をそのまま引用します。
例:「『最初は120万円という見積もりに驚きましたが、15年間メンテナンス不要と聞いて納得しました。結果的に年間8万円で済んでいるので、アパートの家賃並みですね』(40代・会社員の田中様)」
3. 業界の内情・現場の実態
専門家だからこそ知っている業界情報を提供します。
例:「実は、外壁塗装業界では『雨の日の作業』が品質に大きく影響します。弊社では湿度60%以上の日は作業を中止していますが、これを守らない業者も多いのが現実です。」
4. 独自調査・アンケート結果
自社で実施した調査データを活用します。
例:「弊社が実施した『外壁塗装の失敗要因調査』(回答者500名)では、最も多い失敗原因は『業者選びの判断基準が不明確だった』(42%)でした。」
- 見出し直下のセクションリードで予告
「このセクションでは、弊社の○○年の経験から得られた実際のデータをもとに解説します。」 - PREP法のE(具体例)部分で詳しく展開
理由の説明の後に、実体験や事例で具体的に示します。 - 数字とエピソードをセットで提示
データだけでなく、そこにまつわるストーリーも一緒に伝えます。
例:「施工後10年経過したお客様宅を訪問すると、『まだ新築のように見える』と近所の方に言われるそうです。これが高品質な塗料を選ぶメリットです。」 - 比較・対比で差別化を明確化
一般的な情報と自社の実例を対比して、独自性を強調します。
オリジナリティ性の高いライティング実践のコツ
- 顧客情報を使用する際は必ず許可を取る
- 具体的な数字は正確性を重視する
- 自社に不利な情報も正直に開示することで信頼性を高める
- 定期的に情報を更新し、常に最新の実例を使用する
8.専門性と信頼性を示すライティング手法 重要
Googleが記事を評価する際に最重要視している「E-E-A-T」のうち、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)をライティングで示す事も、SEO効果を大幅に高める重要な手法です。
特に中小企業にとって、これらを適切に表現することで大手企業に負けない信頼性を構築できます。
- 専門用語の適切な使用と解説
業界の専門用語を正しく使いつつ、一般読者にも分かるよう丁寧に解説します。
- 例:「下塗り(プライマー)とは、外壁と塗料の密着性を高めるための重要な工程です。この工程を省略する業者もいますが、塗料の剥がれや色褪せの原因となるため絶対に必要です。」
- 例:「下塗り(プライマー)とは、外壁と塗料の密着性を高めるための重要な工程です。この工程を省略する業者もいますが、塗料の剥がれや色褪せの原因となるため絶対に必要です。」
- 最新の業界動向・法改正への言及
常に最新の情報をキャッチアップしていることを示します。
- 例:「2023年の建築基準法改正により、一定規模以上の外壁塗装では環境配慮型塗料の使用が推奨されています。弊社では改正前から環境配慮型塗料を積極的に採用してきました。」
- 例:「2023年の建築基準法改正により、一定規模以上の外壁塗装では環境配慮型塗料の使用が推奨されています。弊社では改正前から環境配慮型塗料を積極的に採用してきました。」
- 技術的な分析・考察の提供
表面的な情報ではなく、深い理解に基づいた分析を提供します。
- 例:「一般的に『安い塗料ほど早く劣化する』と言われますが、実際は『塗膜の厚さ』と『下地処理の品質』が耐久性により大きく影響します。」
- 例:「一般的に『安い塗料ほど早く劣化する』と言われますが、実際は『塗膜の厚さ』と『下地処理の品質』が耐久性により大きく影響します。」
専門性を示すライティングの実践のコツ
- 1つの段落で使用する専門用語は2つ程度に抑える
- 専門的見地から読者にとってのメリットまで説明する
- 具体的な年月日や数値を示し、自社の対応状況も合わせて説明する
- 科学的データを引用しつつ、適切な例え話で読者のレベルに合わせて解説する
- 資格・認定・実績の自然な織り込み
自慢にならない程度に、適切な箇所で資格や実績に触れます。
- 例:「一級塗装技能士として20年間の経験から言えることは、『見た目だけでなく建物を守る』という塗装本来の目的を忘れてはいけないということです。」
- 例:「一級塗装技能士として20年間の経験から言えることは、『見た目だけでなく建物を守る』という塗装本来の目的を忘れてはいけないということです。」
- 業界での立ち位置の明示
業界内での役割や貢献を具体的に示します。
- 例:「弊社は地域塗装業協会の理事として、業界全体の技術向上にも取り組んでいます。そこで得られた最新技術を、常にお客様への施工に反映しています。」
- 例:「弊社は地域塗装業協会の理事として、業界全体の技術向上にも取り組んでいます。そこで得られた最新技術を、常にお客様への施工に反映しています。」
- 第三者からの評価の活用
客観的な評価や受賞歴を適切に記載します。
- 例:「2022年には『顧客満足度No.1』(○○調査機関調べ)を受賞しましたが、これも長年の丁寧な施工と アフターフォローの結果だと考えています。」
権威性を示すライティングの実践のコツ
- 資格そのものより、それがお客様にどんなメリットをもたらすかを具体的に説明する
- 業界への貢献がお客様にどう還元されるかを明確に示し、継続的な活動であることを強調する
- 評価の詳細(調査機関、規模、基準)を明記し、評価された理由・背景まで説明する
- 情報の出典・根拠の明示
主張に対する裏付けを必ず示します。
- 例:「国土交通省の『建築物の外壁等の調査・改修指針』によると、外壁塗装の適切な周期は10〜15年とされています。」
- 例:「国土交通省の『建築物の外壁等の調査・改修指針』によると、外壁塗装の適切な周期は10〜15年とされています。」
- 透明性のある情報開示
都合の良い情報だけでなく、注意点やリスクも正直に伝えます。
- 例:「フッ素塗料は耐久性に優れていますが、初期費用が高く、また特殊な下地処理が必要なため、すべての建物に適しているわけではありません。」
- 例:「フッ素塗料は耐久性に優れていますが、初期費用が高く、また特殊な下地処理が必要なため、すべての建物に適しているわけではありません。」
- 連絡先・所在地の明確な記載
記事の信頼性を担保するため、会社情報を適切に開示します。
- 例:「ご不明な点がございましたら、○○市○○町1-2-3の弊社までお気軽にお問い合わせください。(一級塗装技能士の田中が直接対応いたします)」
- 例:「ご不明な点がございましたら、○○市○○町1-2-3の弊社までお気軽にお問い合わせください。(一級塗装技能士の田中が直接対応いたします)」
- 責任ある表現の使用
断定的すぎず、かつ曖昧すぎない、責任ある表現を心がけます。
- 例:「弊社の経験では」「一般的には」「お客様の状況によっては」などの前置きを適切に使用し、誤解を招かない表現を選びます。
信頼性を示すライティングの実践のコツ
- 公的機関や権威ある団体の資料を引用し、発行年や版数まで正確に記載する
- メリットとデメリットをセットで説明し、お客様の状況に合わせた提案姿勢を示す
- 具体的な数値や割合を示しつつ、条件や前提、例外的なケースについても言及する
E-E-A-Tを含めた効果的なライティングをするために
これらの手法は単独で使うのではなく、記事全体に自然に散りばめることが重要です。
1つの段落で複数の要素を組み合わせ(例:専門性のある分析+権威性のある実績+信頼性のある出典)、読者に「この会社・この人は本当に信頼できる専門家だ」という印象を与えることで、SEO効果と顧客獲得効果の両方を最大化できます。
9.読みやすく分かりやすい見た目にする
どれほど良い内容を書いても、見た目が整っておらず読みにくいと読者は離脱してしまいます。
特にスマートフォンはPCに比べ画面が小さいので、何も考えずに記事を作成すると画面が文字でいっぱいになりがちです。
1行が長くならないよう意識したり、余白や装飾を工夫することで、滞在時間の向上とSEO効果の大幅な改善が期待できます。
1. 1文を短くして読みやすくする
長い文章は読者の負担になるため、1文は70文字を目安に簡潔にまとめます。
また、適切な改行と装飾で視認性を向上させます。
❌悪い例
「外壁塗装工事において最も重要なのは下地処理の品質ですが、多くの業者が工期短縮やコスト削減のために高圧洗浄を1日で済ませてしまい、その結果として塗料の密着不良や早期の剥がれが発生してしまうケースが後を絶ちません。」
⭕良い例
外壁塗装で最も重要なのは、下地処理の品質です。
しかし多くの業者は、工期短縮のために高圧洗浄を1日で済ませてしまいます。その結果、以下のトラブルが発生します:
- 塗料の密着不良
- 早期の剥がれ
- 施工不良による再工事
適切な下地処理には、最低でも2〜3日の乾燥期間が必要です。
2. 適切な改行と段落分け
情報のまとまりごとに段落を分け、読者が理解しやすい構成にします。
- 1段落は3〜4行以内に収める
- 関連する情報をグループ化する
- 段落間に適度な余白を設ける
1. ボックス処理・囲み装飾
重要な情報や注意点を目立たせます。
例えば、ここも青く細い線のボックスで囲まれています。
2. 箇条書き・番号リストの効果的な活用
複数の情報を整理して伝える際に使用します。
- 手順を示す場合: 番号リスト(1、2、3…)
- 選択肢を示す場合: 箇条書き(・、■、●)
- メリット・デメリット: 記号の使い分け(✓、×)
3. 文字装飾で重要部分を強調
読み飛ばされがちな重要情報を確実に伝えます。
- 太字:最重要キーワードや結論
- 文字色:重要なキーワード等
4. 余白とマージンの調整
適度に余白を設定して窮屈な印象を避け、圧迫感なく構造が理解しやすい見た目にします。
- 見出し前後の余白を十分に取る
- 段落間にスペースを設ける
- 左右の余白も考慮する
実践のコツ
記事を書いた後、必ずスマートフォンで表示確認を行いましょう。
PCでは読みやすくても、スマートフォンでは読みにくいということがよくあります。
また、家族や同僚に「パッと見て読みたいと思うか」を確認してもらうことも効果的です。
10.段落ごとに読者の疑問を一つずつ解消する
SEO効果の高い記事を書くためには、読者の頭の中に浮かぶ疑問を先回りして、段落ごとに一つずつ解消していくことが重要です。
これにより、読者は「知りたいことがどんどん解決されていく」という満足感を得られ、最後まで読み続けてくれます。
1. 検索キーワードから関連する疑問を洗い出す
記事の本文を展開してゆく中で、読者が次に疑問に思うことを想定します。
例:「外壁塗装 費用」の記事を展開してゆく中で派生する疑問
- 「なぜ業者によって見積もりが違うの?」
- 「安い業者に頼んで大丈夫?」
- 「追加費用は発生しない?」
- 「どの塗料を選べばいいの?」
2. 疑問の優先順位を決める
読者が疑問に思う内容に優先度をつけ、その順序で段落を構成します。(場合によっては見出しレベルで構成)
3. 各段落で1つの疑問を完全に解消する
中途半端に答えるのではなく、その疑問について読者が納得できるまで説明します。
疑問解消型ライティングのテンプレート
- 段落1:最重要の疑問への回答 「○○について最も多い疑問は『△△』です。結論から言うと、□□なので××です。」
- 段落2:理由・根拠の説明 「この理由は、業界の仕組みにあります。具体的には…」
- 段落3:具体例・データの提示 「実際の例で説明すると…」
- 段落4:次の疑問への橋渡し 「ここまでで○○については理解できたと思いますが、次に気になるのは△△ではないでしょうか。」
実践例:「外壁塗装 費用」記事での疑問解消の流れ
- 「30坪でいくらかかるの?」→ 80-120万円の相場を提示
- 「なぜこんなに価格差があるの?」→ 塗料の違いを説明
- 「どの塗料を選べばいいの?」→ 選び方の基準を解説
- 「安い業者は危険?」→ 適正価格の見極め方を説明
- 「追加費用を避けるには?」→ 契約時の注意点を提示
SEO対策ライティングのやり方についてのよくある質問
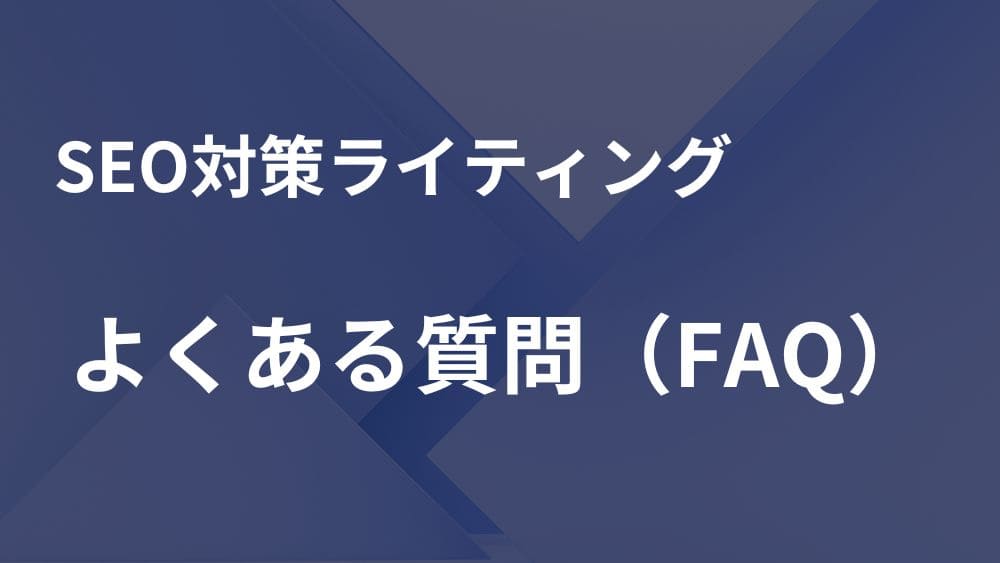
SEOライティングの手法を学んでも、実際に取り組み始めると様々な疑問が生まれるものです。弊社がこれまでサポートしてきた中小企業の経営者や担当者の方から、特に多く寄せられる質問をまとめました。
これらの質問と回答を事前に知っておくことで、迷うことなくSEOライティングに取り組めるようになり、効率的に成果を出すことができます。きっとあなたが抱いている疑問への答えも見つかるはずです。
まとめ|SEOライティングは「読者×検索エンジン」の両立が鍵
SEO対策したライティングで成果を出すためには、検索エンジンに評価される技術的な要素と、読者にとって価値ある内容の両方が必要です。
やり方としては、キーワードの自然な配置、読者の検索意図への的確な回答、そして継続的な改善が成功の鍵です。
最初は完璧を目指さず、無理なく出来る頻度で記事作りをスタートしましょう。
3〜6ヶ月後には必ず効果を実感できるはずです。
「一人でやるのは正直、大変そう…」と感じたあなたへ
SEOライティングの手法を学んでも、「一人で継続するのは現実的に厳しそう」と感じるのは当然です。
- 「本業で忙しい中、毎月2〜4記事を書き続けられるだろうか?」
- 「競合分析やキーワード選定を、間違いなく判断できるだろうか?」
- 「効果が出るまで3〜6ヶ月、モチベーションを維持できるだろうか?」
- 「記事を書いても順位が上がらない時、何を改善すればいいかわかるだろうか?」
等、このような不安を感じているなら、ブルイージスの無料相談を一度お試しください。
「一人でやる」のではなく「一緒に仕組みを作る」ことで、無理なく継続できるSEO集客を実現いたします。