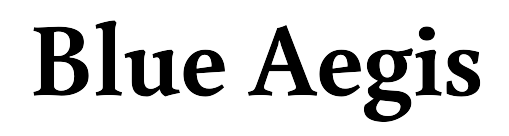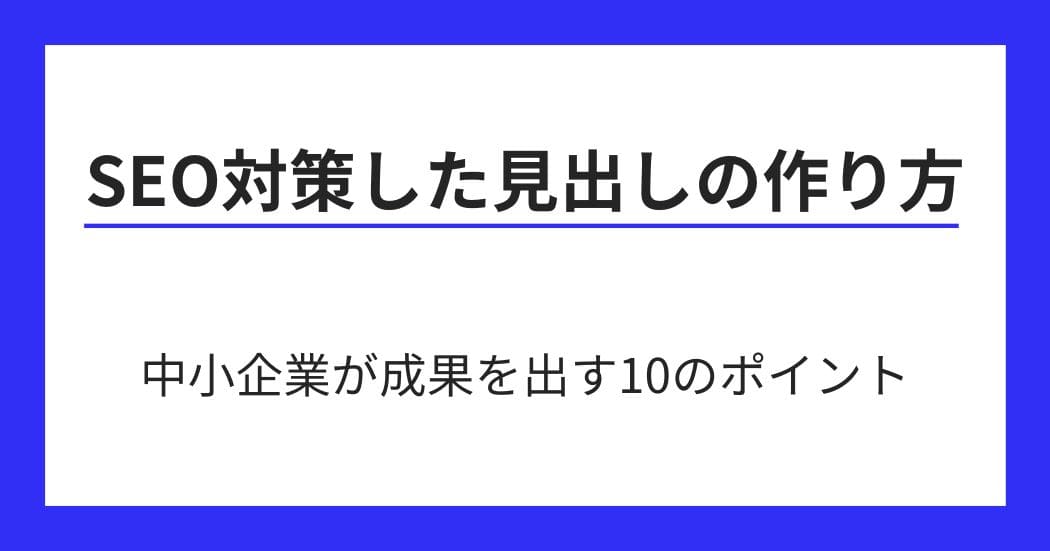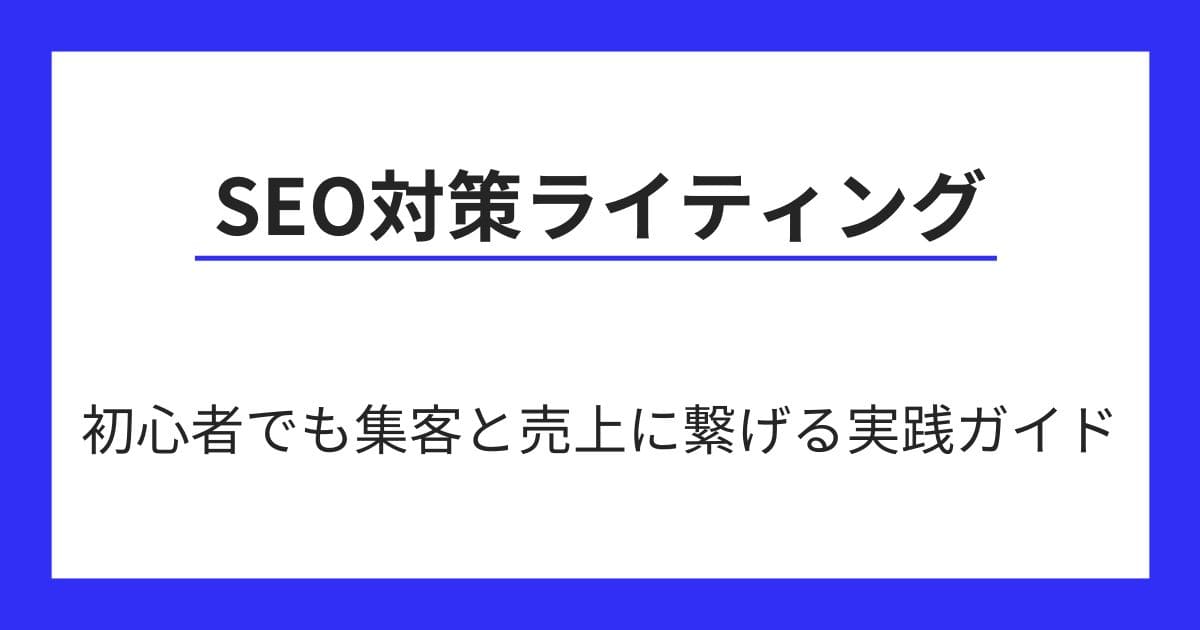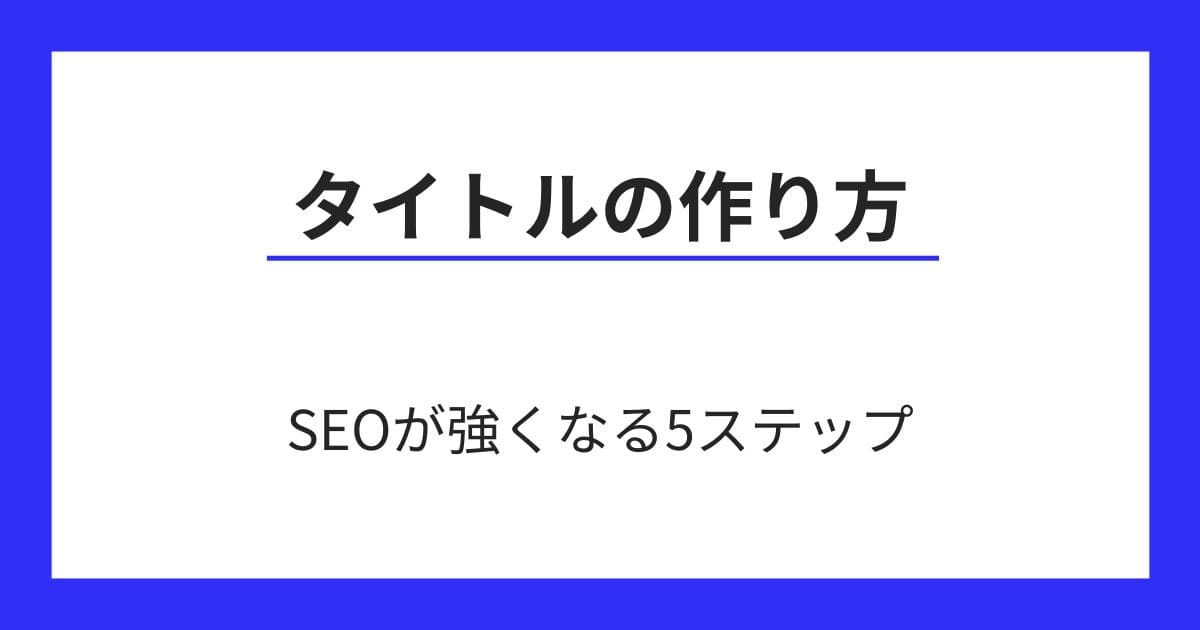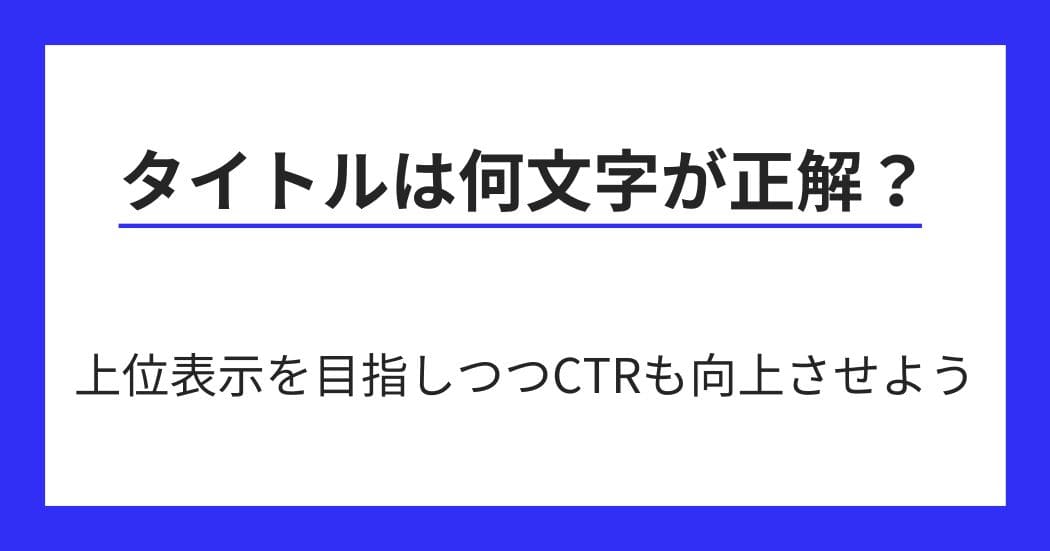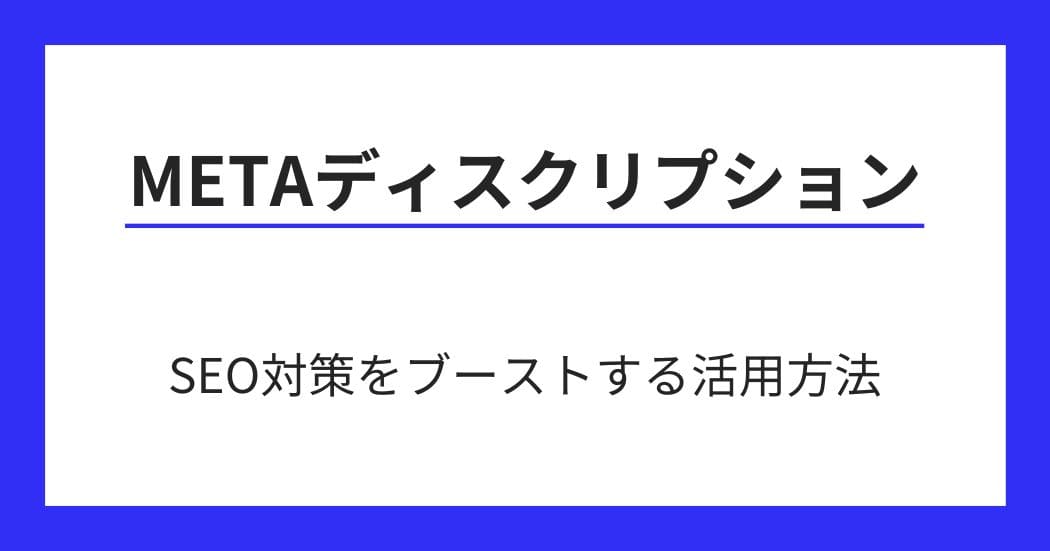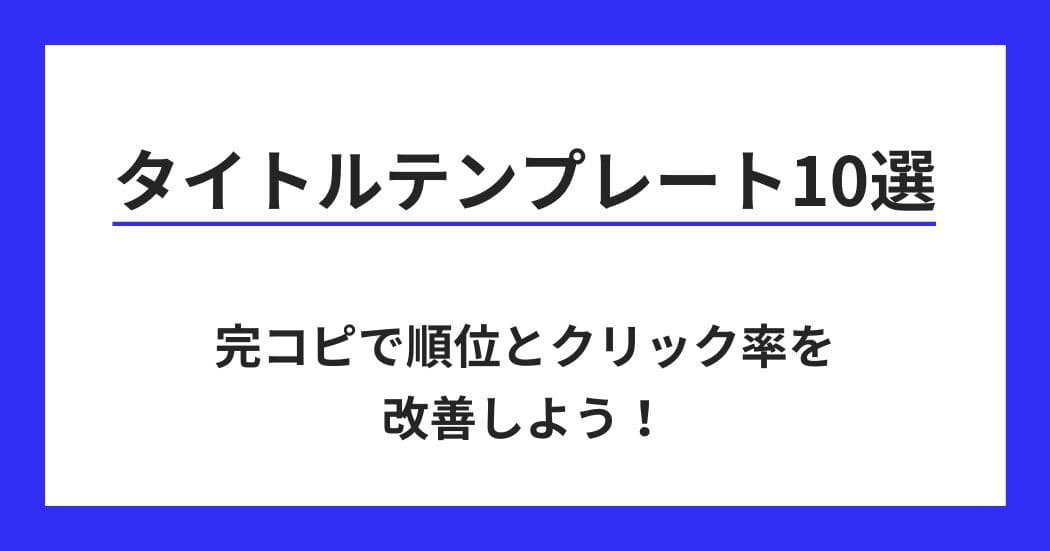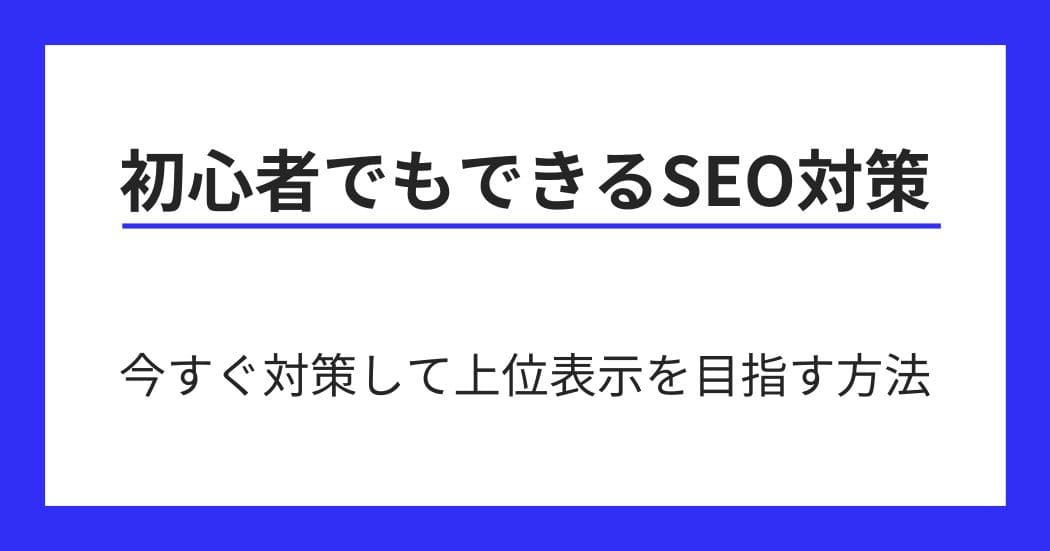中小企業のオウンドメディアでSEOによる集客成果を出す場合、記事の見出しは非常に重要です。
その理由は、誰にでも出来るSEO対策でありつつも、難易度が高くないからです。
SEOに対応出来る専門的な人員がいなくても、手分けをすれば何とか対応できるのが、見出しによるSEO対策。
本記事では、中小企業が限られたリソースの中で最大の成果を出すための、実践的な見出し作成法をお伝えします。
SEO対策された見出し構造の作り方
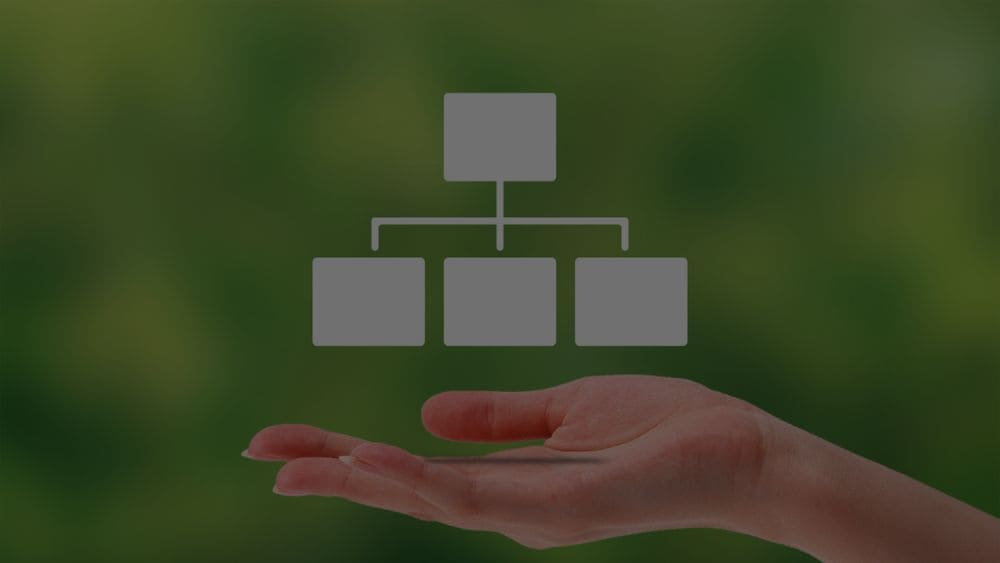
高いSEO効果を出すためには、見出しを単体で考えるのではなく、構造としてSEO対策を行なう必要があります。
なぜなら、記事全体の見出しの構造を整えることで、記事のテーマはもちろん、各見出しで何を伝えようとしているのかを、はっきりと示す事ができるからです。
特に検索エンジンに対して、「見出し構造で記事のテーマや各見出しの内容を明確に伝える」事は、SEO対策としてはとても大切です。
検索エンジンが記事の内容を理解するための重要な手がかりになるからです。
では、さっそくSEOに強い見出しの作り方を解説してゆきますね。
見出しの構造化はタグの使い分け理解から
見出しにおけるSEO対策の基本は、H1からH3までの見出しタグの構造を適切に使い分けることです。
まず、見出しタグには階層に沿った種類があり、「H1」「H2」「H3」で表す事が出来ます。
- H1タグ:記事全体のタイトル=本でいえば「書名」
- H2タグ:各章の大見出し=本でいえば「章」
- H3タグ:章内の小見出し=本でいえば「節」
- H4~H6タグ:存在はしているが、細かすぎてあまり使われない。
これらのタグを指定することで、見出しとして機能すると共に見出しの種類が指定できます。
設定の仕方は、使用しているCMS等の操作によりますが、とても簡単です。
見出しが設定されていると、メディア記事上で見出しとしての装飾が行なわれたり、目次として使われますので、人間にも検索エンジンにとっても、記事の構造やテーマ、内容が理解しやすくなります。
例えばこの記事の場合は、以下の画像ような見出し構造・構成になっています。
見出し構造は、場合によってはH4タグまで深掘ることもあります。
ただし、あまり深くなると構造も複雑になりますので、頻繁にH4まで深掘りが必要な記事の場合は記事として扱っているテーマが大きすぎる可能性が大です。
テーマそのものをもっと絞り込んだ記事にするほうが、SEO的にも上位表示しやすくなる、と言ったような判断にも使えるのが見出し構成です。
ほとんどのメディアの場合、H1はタイトルと同様に扱われているので、記事中に使用するのはH2~H3(もしくはH4)までです。
例えば、「小学校で学ぶ教科」について書く場合は、見出しタグを以下のような階層構造で表せます。
H1:小学校で学ぶ主要教科の一覧(=タイトル)
├H2:国語
│ ├H3:漢字の学習
│ └H3:作文の書き方
├H2:算数
│ ├H3:足し算・引き算
│ └H3:掛け算・割り算
└H2:理科
├H3:植物の観察
└H3:実験の方法こうして、見出しをH1~H3(場合によりH4)階層構造化することで内容が整理され、読者にとっても理解しやすく、検索エンジンのクローラー(サイトを巡回するロボット)にとっても理解、そして評価しやすい記事を作る事ができます。
記事の内容を正しく伝えないと、SEOの評価も正しく行なわれないので、見出しを構造化して正しく伝えるというのは、基本ですがとても大切なSEO施策だという事が分かります。
H1見出し=記事のテーマを端的に伝える
H1見出しは、その記事で最も重要な見出しです。
記事全体のテーマを一言で表現し、読者が「この記事を読むべきかどうか」を瞬時に判断できるようにする必要があります。
- 具体性があること
- ❌「SEOについて」
- ⭕「中小企業が月1万円の予算で始められるSEO対策」
- 対象読者が明確であること
- ❌「ホームページの作り方」
- ⭕「個人事業主のための初心者向けホームページ作成ガイド」
- 得られるメリットが分かること
- ❌「見出しタグの使い方」
- ⭕「SEO対策した見出しの作り方|中小企業が成果を出す10のポイント」
つまり、H1で表したいことはタイトルと同義になるので、ほとんどの場合、H1見出しはタイトルは同じものが使用されます。
もちろん、この記事もH1見出しとタイトルは同じです。
H2見出し=章立てで大枠を示す
H2見出しで表される中見出しは、ページの目次としても利用される記事の骨組みです。
なので、見出しとしてもSEO対策という点でもとても重要です。
ページを訪れた読者が「目次」を見ただけで記事の全体像を把握できるよう、章立てて大枠を示します。
- 検索意図に沿った構成にする
読者が知りたいことの順番に沿ってH2を配置します。
例えば「ふるさと納税 やり方」で検索する人に対するH2の順序- まず「ふるさと納税とは何か」を知りたい
- 次に「具体的なやり方・手順」を知りたい
- 最後に「注意点・よくある間違い」を知りたい
- 並列関係を意識する
同じレベルのH2タグは、同じ重要度の内容にします。- ❌「基本知識」「H1タグについて」「注意点」
- ⭕「基本知識」「作成方法」「注意点」
- 適度な文章量を意識する
目安として、一つのH2配下の本文が1,000文字を超える場合は、H3で細分化を検討しましょう。
H3見出し=具体策や詳細を分かりやすく示す
H3見出しは、H2見出しの内容をより具体的に、詳細に説明するために使用します。
読者が実際に行動に移せるレベルまで情報を細分化するのがポイントです。
- 実行可能な単位に分ける
- H2「海外旅行の準備」
- H3「パスポートの取得方法」
- H3「航空券の予約手順」
- H3「持ち物リストの作成」
- H2「海外旅行の準備」
- 読者の疑問に直接答える
- H2「家庭菜園の始め方」
- H3「どんな野菜が初心者向け?」
- H3「必要な道具は何?」
- H3「どのくらいの費用がかかる?」
- H2「家庭菜園の始め方」
- 番号や順序を活用する
- H2「カレーの作り方」
- H3「手順1:材料の下準備」
- H3「手順2:野菜を炒める」
- H3「手順3:煮込みと仕上げ」
- H2「カレーの作り方」
多くの読者は記事を「流し読み」します。
H3見出しを見ただけで「何をすればいいか」が分かるように工夫することで、見出しを見て読者が必要と思う箇所だけ本文を読むという使い方が出来ます。
記事の活用の仕方を複数化することが出来ますし、読者側に委ねることができるので読者の理解度と満足度を高めることができます。
SEOで成果を出す見出し設計10のポイント

では実際にSEO効果を高める見出し設計の、具体的なポイントを10個お伝えします。
これらのポイントを意識するだけで、検索順位と読者満足度の向上を同時に実現できます。
H1見出しは1ページに1つ
最も重要な大見出しであるH1見出しは、1つのページに1つだけ使用しましょう。
そして、SEO対策という意味で取り組むのであれば、H1はタイトルと同じにしてください。
1冊の本に複数の「大見出し=タイトル」があったら混乱するからです。
- H1「初心者のための料理レシピ完全ガイド」:記事タイトル
- H1「料理レシピ集」← H2にするべき
- H1「和食の作り方」← H2にするべき
- H1「洋食の作り方」← H2にするべき
WordPressを含む多くのホームページ作成ツールでは、ページタイトルが自動的にH1になるよう設定されているため、追加でH1を作らないよう注意しましょう。
本文の見出しはH2を使用する
記事の本文部分で使用する最初の見出しは、H2タグを使います。
H1は前項で説明したとおり、タイトルと同義で自動的に使われている事がほとんどです。
- H1:全体見出し=記事のタイトル(ページ全体のテーマ)
- H3:いきなり小見出し ← H2を飛ばしている
- H4:さらに小さな見出し
- H3:いきなり小見出し ← H2を飛ばしている
- H1:全体見出し=記事のタイトル(ページ全体のテーマ)
- H2:第1章の見出し
- H3:第1章の詳細1
- H3:第1章の詳細2
- H2:第2章の見出し
- H2:第3章の見出し
- H2:第1章の見出し
本分をライティングする際の見出しは、必ずH2見出し~使用するようにしてください。
全体を俯瞰できる論理的な流れを設計する
見出しは、読者が「知りたいこと」の順番に沿って、論理的かつ分かりやすい構成することが重要です。
H2見出しの内には関連する内容のH3見出しがある、という階層構造を作りましょう。
読者の理解度と満足度が格段に向上します、検索エンジンのクローラーにとっても把握しやすい構造となります。
- 問題提起→解決策→結果
- H2「なぜ家庭菜園で野菜が育たないのか?」
- H3「土の質が悪い場合」
- H3「水やりのタイミングが間違っている場合」
- H2「野菜を元気に育てる5つの方法」
- H3「良い土作りの手順」
- H3「適切な水やりのコツ」
- H2「実践後に期待できる収穫量」
- H3「トマトの場合の収穫目安」
- H3「きゅうりの場合の収穫目安」
- H2「なぜ家庭菜園で野菜が育たないのか?」
- 基礎知識→実践方法→応用・注意点
- H2「ジョギングの基本的な効果」
- H3「体力向上のメカニズム」
- H3「ダイエット効果の仕組み」
- H2「今すぐできるジョギングの始め方」
- H3「準備するもの」
- H3「初回のペース設定」
- H2「よくある怪我のパターンと対策」
- H3「膝の痛みを防ぐ方法」
- H3「筋肉痛への対処法」
- H2「ジョギングの基本的な効果」
- 現状分析→目標設定→具体的手順
- H2「現在の体力レベルを正しく把握する」
- H3「簡単な体力テストの方法」
- H3「結果の見方と判断基準」
- H2「達成可能な健康目標を設定する」
- H3「年代別の目標設定例」
- H3「無理のない計画の立て方」
- H2「目標達成のための運動計画」
- H3「週単位のスケジュール例」
- H3「継続するためのコツ」
- H2「現在の体力レベルを正しく把握する」
読者の検索意図を理解し、読者が「次に何を知りたいか」を推測して見出しを配置することで、最後まで読んでもらえる記事になります。
また、検索エンジンからの評価向上にも直結します。
見出しには主要キーワードを自然に含める
記事に設定されているキーワードを見出しに含めることで、その見出しのテーマが設定されたキーワードと強く結びついていることを、検索エンジンのクローラーに伝える事が出来ます。
特にH2見出しには出来るだけキーワードを含めるようにしましょう。
ただし、無理のないようにあくまでも「自然に」キーワードを含めることが重要です。
対策キーワード:「ふるさと納税 やり方」
「ふるさと納税 やり方 ふるさと納税 やり方を解説」← キーワードの詰め込み
対策キーワード:「ふるさと納税 やり方」
- H2:ふるさと納税のやり方を3ステップで解説」
- H2:初心者でも簡単!ふるさと納税のやり方
自然にキーワードを含めるコツ
- 読者の検索意図を考える
「ふるさと納税 やり方」で検索する人は、具体的な手順を知りたがっています。 - 関連語句も活用する
「方法」「手順」「仕組み」「始め方」など、同じ意味の言葉も使いましょう。 - 見出しを声に出して読む
不自然に感じる見出しは、読者にとっても分かりにくいものです。
1見出し1テーマの原則を守る
見出しを付ける時の基本原則として「1つの見出しに1つのテーマ」を徹底しましょう。
1つの見出しの中に複数のテーマに詰め込むと、読者が混乱しますし検索エンジンもテーマを、正確に理解できなくなってしまいます。
そして、執筆者も記事を作ってる最中に混乱し記事の品質にも良い影響はありません。
1見出し1テーマの原則を守り、シンプルなライティングを行ないましょう。
- 読者の理解促進
数のテーマが混在すると、読者は「結局何の話?」と混乱してしまいます - 検索エンジンの正確な理解
Googleのロボットが見出しから記事の内容を正確に把握できます - 記事構造の明確化
各見出しの役割が明確になり、記事全体の論理構造が整理されます
悪い例と良い例の比較
❌「家庭菜園の土作りと水やりと害虫対策について」 → 3つのテーマが混在している
⭕「家庭菜園の土作りの基本手順」
「正しい水やりのタイミング」
「初心者でもできる害虫対策」 → 各見出しが1つのテーマに集中している
それぞれの見出して扱うテーマが1つに絞れていれば、その見出しの内容を一言で要約することができるはずです。
見出しを作った後は「この見出しで何を伝えたいのか」を一言で説明できるかテストしてみましょう。
テーマが1つに絞れているかのチェック方法
見出しを作った後は、以下の方法でテーマが適切に絞られているかを確認しましょう。
- 見出しの内容を「〇〇について」の一言で説明できるか試す
- 「と」「や」などの接続詞が必要になっていないかチェック
- その見出し配下で伝えている内容が1つのテーマに集中しているか確認
見出しは画像ではなくテキストで表現
見出しは必ずテキスト(文字)で作成しましょう。
画像で作った見出しは、検索エンジンが内容をはっきりと理解できません。
画像で見出しを作ってデザインにこだわりたい、という気持ちは理解できますが、それよりも読者とGoogleへの分かりやすさを優先しましょう。
- 検索エンジンが間違い無くはっきりと読み取れる
Googleのロボットは画像の中の文字を正確に読み取ることができ無い場合があります。 - 読み上げソフトに対応
視覚に障害がある方が使用する読み上げソフトも、画像の文字は読み上げできません。 - スマートフォンでの表示速度
画像よりもテキストの方が読み込みが早く、ページ表示速度の向上につながります。 - 汎用性がある
見出しとしてそのまま使用したり、コピー&ペーストすることが出来ます
競合にない切り口を盛り込む
同じキーワードで上位表示を狙う競合サイトと差別化するため、独自の視点や切り口を見出しに盛り込みましょう。
これにより、読者と検索エンジンに「このページは他と違う」と感じてもらえます。
- 業界特化の視点
- 一般的:「料理上達のポイント」
- 特化版:「一人暮らし男性専用料理上達の3つのポイント」
- 失敗経験からの学び
- 一般的:「家庭菜園の始め方」
- 独自版:「3回失敗して分かった家庭菜園成功の本当のコツ」
- 時代の変化に対応
- 一般的:「健康管理の基本」
- 最新版:「在宅ワーク時代に対応した次世代健康管理法」
- 具体的な制約条件
- 一般的:「節約術のコツ」
- 具体版:「月収20万円以下の一人暮らし節約術」
競合他社と同じような見出しばかりでは、読者に選んでもらえません。
御社ならではの経験や専門性を活かした独自の切り口を見つけることが重要です。
日々業務の中での気付きや感じていることや、お客様との会話にヒントは多くあります。
以下の3つの視点から考えてみましょう。
独自性を見つける方法
- あなたの業界特有の悩みは何か?
- お客様からよく聞かれる質問は?
- 他社では対応していない特殊なニーズはないか?
ユーザーの読みやすさと理解を最優先する
SEO対策も大切ですが、最終的に記事を読むのは「人間」です。
読者にとって分かりやすく、理解しやすい見出しを作ることが、結果的に最も効果的なSEO対策になります。
Googleも「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」と公式に伝えています。
- 専門用語を避ける
❌「BMIとメタボリックシンドロームの改善手法」
⭕「体重と生活習慣病を改善する方法」 - 短文で表現する
❌「家族に最も効果的に喜んでもらえる手料理レシピの詳細について」
⭕「家族が喜ぶ手料理レシピ3選」 - 読者の立場で考える
❌「当店の商品概要」
⭕「あなたのお悩みを解決する3つの商品」
見出しを作る際は、読者が本当に理解できる表現になっているかをセルフチェックしましょう。
専門知識がある人には当たり前の表現でも、初心者には分からない表現になっていることがよくあります。
スマホでも読みやすい簡潔さを意識する
現代では多くの人がスマートフォンを使って、ウェブサイトにアクセスを行なっています。
内容にも寄って異なりますが、平均的には80%~90%程度が、スマートフォンからのアクセスだと考えおいてください。
スマートフォンのような小さな画面でも読みやすい、簡潔で明瞭な見出しを心がけましょう。
- 文字数を抑える
- スマートフォンでは1行に表示できる文字数が限られます
- 目安:15~25文字程度
- 重要な情報を前半に
- ❌「詳細な解説と具体例付きの家庭菜園のコツ」
- ⭕「家庭菜園のコツ【具体例付き】」
- 改行位置を意識
- 意味のまとまりで自然に改行されるよう調整
- 単語の途中で改行されないよう注意
見出しの作成途中に何度かスマートフォンの画面でどう見えるかを確認しつつ見出し作成を進めましょう。
全てが出来上がってから問題点を見つけると、かなり大きな修正工数が必要になる場合があります。
Google Chromeなら開発者ツールを活用して、スマホ用のプレビューを確認しながら進めると効率的です。
「右クリック→検証」もしくはF12キーから起動できます。
見出しとして共通の装飾や強調で視認性を向上
見出しは、本文テキストと明確に区別できるよう、適切な装飾を施しましょう。
統一されたデザインにより、読者が記事の構造を直感的に理解できます。
- 階層に応じたサイズ設定(例)
- H1:最も大きく(例:28px)
- H2:H1より小さく(例:24px)
- H3:H2より小さく(例:20px)
- 色の統一
- 同じレベルの見出しは同じ色
- ブランドカラーとの調和
- 余白の調整
- 見出しの上下に適切な余白
- 本文との区別を明確に
- 一貫性のあるデザイン
- 全ページで同じルール
- 読者が慣れ親しめる統一感
読者が「ここが見出しだ」と瞬時に判断できる見た目にすることで、記事全体の読みやすさが大幅に向上します。
読みやすさ、分かりやすさが向上することで滞在時間の延長にもつながり、SEO効果も期待できます。
WordPressであれば、初期状態で全体的に統一感のある設定が行なわれていますが、カスタマイズして変更することも可能です。
SEO対策した見出しが成果に直結する理由

見出しの改善は投資対効果が非常に高いSEO対策の一つで、少しの工夫で大きな成果の違いを生み出すことができます。
ここでは、SEO対策した見出しがなぜ集客力の向上、そして成果に繋がるのか?
その仕組みを3つの観点から詳しく解説します。
Googleは見出しを手掛かりに記事を理解する
Google検索エンジンは、まるで図書館の司書のようにインターネット上の膨大な情報を整理しています。
整理するときに大切な情報となるのが、「見出しタグ」の情報です。
H1~H3,4の見出しタグ情報を整理することで、「この記事は何についての記事で、どこに何が書いてあるのか」という、極めて重要な情報を短時間に把握する事ができるからです。
人が本を読むとき、まずタイトルを見て目次をパラパラとめくってどのような内容の本なのかを把握する行為は、まさにGoogleがやっている事と同じ事をやっている状態です。
まずはH1でその記事のテーマ(=タイトル)を理解し、そしてH2、H3と小さい見出し構造で章や節を確認しています。
- H1タグで全体のテーマを把握
記事のメインテーマが何かを理解します - H2タグで章構成を確認
どのような内容が含まれているかを把握します - H3タグで詳細な情報を理解
具体的にどんな情報が提供されているかを判断します
各見出しが適切に設定されていると、Googleはあなたの記事を正確に理解することが出来ます。
そして、検索キーワードに対して「この記事は読者の疑問に答えている」と判断できれば、検索結果で上位に表示される可能性が高くなります。
読みやすい見出しは滞在時間・回遊率を高める
SEO対策において、「読者がページにどのくらい滞在したか」「他のページも見てくれたか」は非常に重要な指標です。
読みやすく理解しやすい見出しは、これらの数値を劇的に改善する効果があります。
読者は記事を読む前に、まず見出しを流し読みして「この記事には自分の知りたい情報がありそうか」を判断します。
見出しが分かりやすければ、読者は安心して本文を読み進めることができます。
- 目次での判断がスムーズ
見出しが明確だと、読者は「この記事を読む価値がある」と瞬時に判断できます - 読み進める動機が維持される
各章の見出しで次に何が書かれているかが分かると、読者の興味が持続します - 必要な情報に素早くアクセス
知りたい部分だけを読みたい読者も、該当する見出しをクリックして目的の情報にすぐたどり着けます
優れた見出しを持つページを読み、そして容易に内容を理解した読者は、「この会社は情報を分かりやすく説明してくれる」という信頼感を持ちます。
その結果、他のページも見てみようという気持ちを自然と持ちます。
一つのページをきっかけに他の記事を読んだり、提供している会社に興味が湧いてサービスページを見た経験が、あなたにもあると思います。
検索順位だけでなく成約率にも影響する
見出しを改善すると得られる効果は、SEO効果による見込み顧客の増加だけではありません。
集客以上に影響の大きい、「成約率」にも影響があります。
SEO対策されている見出しは、読者の精読率の上昇に寄与し「この会社は信頼できる」「この商品・サービスは自分に合っている」という印象を与えます。
また、記事を通じて信頼感を高めることで、会社情報やサービスページ等も閲覧され、更に信頼が強化されます。
こうした信頼と回遊の結果、「この会社に相談してみよう」という気持ちへと変化し、ページからの問い合わせ率や相談率の上昇につながります。
見出しが構造化され分かりやすくなると、書き手側もかなり楽に良い記事を制作することが出来るようになります。
リソースの限られた中小企業にとって、SEOの専門知識や専門人員がいなくてもすぐに取り組める為、中小企業や個人事業主が集客をやる上で欠かせない施策だと著者は考えています。
まとめ
SEO対策した見出しの作り方と、成果を出すための見出し設計のポイントについて解説してきました。
SEO対策した見出しは、検索エンジンと読者の両方にページの内容を正しく伝える重要な要素です。
見出しタグのH1〜H3を階層構造で使い分け、読者が一目で内容を理解できる見出しを作りましょう。
SEO効果による検索順位の向上はもちろん、成約率の向上も同時に実現できます。
見出しのSEO対策は少ない投資で大きな成果を期待できる施策です。
まずは既存記事の見出しをSEO対策の観点から見直すことから始めてみましょう。
【理屈は分かったけど、うちの場合はどうすればいいの?】
この記事を読んで見出しの重要性は理解できたものの、こんな疑問が頭に浮かんでいませんか?
- 「そもそも、うちが狙うべきキーワードって何?競合分析ってどうやるの?」
- 「Webに詳しい人が社内にいないんだけど、本当にできるかな?」
- 「見出し改善だけでSEOは完了なの?他にもやらなきゃいけない事があるのでは?」
このような疑問をお持ちの方は、ブルーイージスの無料相談まで、お気軽にご相談ください。
御社の業界・規模・地域性を踏まえた「御社専用のSEO対策プラン」をご提案します。
継続的に成果を生み出す集客の仕組み化戦略を一緒に作ってゆきましょう。