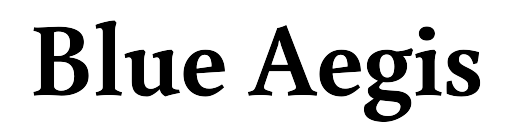「ホームページはあるのに問い合わせが来ない」とお悩みではありませんか?
多くの中小企業経営者が同じ課題を抱えています。
せっかくホームページを作ったのに成果につながらず、結局は営業活動に奔走しなければならない状況が続いているのではないでしょうか。
しかし、同じような規模、業種の会社でも、ネットやウェブを通じて安定して問い合わせを獲得している企業が存在します。
一体何が違うのでしょうか?
この記事では、営業リソースの限られた中小企業が、HPからの問い合わせを増やすための実践的な方法と、見込み客に困らない企業に共通する3つの特徴をご紹介します。
ITスキルや大きな投資をしなくても、今日から始められる具体的なステップをお伝えします。
なぜ多くの中小企業のホームページは問い合わせを生まないのか?
ホームページを持っていても問い合わせにつながらない原因は、単に「見た目」や「デザイン」の問題ではありません。
思うような成果が出ない背景には、いくつかの共通した課題が隠れています。
「見られて終わる」ホームページになっている
多くの中小企業のホームページは、会社の基本情報や事業内容を掲載するだけの「デジタルなパンフレット」になっています。
訪問者はほーむぺーじの内容を見た後に、ただ一言「ふーん」と呟いてホームページから去っていきます。
「弊社は○○を提供しています」、「○○年の実績があります」といった情報だけでは、訪問者の心を動かし、問い合わせという「次のアクション」につなげることはできません。
問い合わせが生まれる仕組みの欠如
ホームページからの問い合わせは偶然の産物ではありません。
訪問者を「興味を持った閲覧者」から「問い合わせをする見込み客」へと変換する仕組みが必要です。
ホームページやウェブサイトから、問い合わせを生まない企業サイトの多くは、
- 訪問者が抱える具体的な課題への言及がない
- 問い合わせるメリットが明確でない
- 問い合わせのハードルが高すぎる(情報を求めすぎる、手順が複雑など)
といった特徴があります。
これらの特徴に代表される原因によって、潜在的な問い合わせの機会を逃す原因となっています。
ありがちな誤解と対策方針
「ホームページは作れば勝手に問い合わせが来る」とか「デザインを綺麗・今風にすれば問い合わせが来る」という誤解は、失敗をうむ多くの原因です。
実際には、ホームページは作ればいいのではなくて、「問い合わせを生み出す仕組み」を考慮して設計する必要があります。
また、「広告をたくさん出さなければ集客できない」という思い込みも要注意。
確かに広告は有効な手段ですし、出せばすぐに効果が見えます。
しかし、中長期という目線で成果を最大化するのであれば、まずは既存のホームページを「問い合わせ獲得装置」の土台として最適化することが先決です。
見込み客に困らない企業の共通点①:「訪問者の行動導線」を徹底設計している
問い合わせが絶えない企業のホームページには、訪問者を自然に「問い合わせ」へと導く明確な道筋が設計されています。
ユーザー心理に基づいた情報設計の重要性
訪問者は「何となく」サイトを見ているわけではありません。
彼らは何らかの課題や疑問を持って貴社のサイトにたどり着いています。
問い合わせが生まれるホームページ作りの第一歩は、まずこの「訪問者の課題」に的確に応えることから始まります。
例えば、生産性向上のコンサルティングを提供する会社であれば、
- 業務効率化したいが、何から手をつければいいか分からない
- 社員の残業が多すぎて悩んでいる
- 同業他社に比べて利益率が低い
といった具体的な悩みに対応するコンテンツを前面に出すことで、訪問者は「自分の課題を理解してくれている」と感じ、興味を持ち始めます。
具体的な導線設計の方法
では、どうすれば問い合わせを産み出す事ができるのか?
ホームページからの問い合わせを増やすのに効果的な導線は、以下のステップで構成するのが王道です。
- 共感と課題の明確化:訪問者が抱える具体的な悩みを示し、「理解されている」と感じさせる
- 解決の方向性の提示:その課題に対する解決策の概要を示す
- 具体的なメリットの説明:解決することで得られる具体的なメリットを提示
- 信頼性の証明:事例や実績、お客様の声lなどで解決できる根拠を示す
- 次のステップの明確化:「問い合わせ」という行動のハードルを下げる工夫をする
この流れが、トップページから各サービスページ、そして問い合わせフォームまで一貫して設計されていることが重要です。
成功事例と実践ポイント
実際に問い合わせ数を大幅に増やした事例を見てみましょう。
地方のリフォーム会社A社では、ホームページの改善によって驚くべき成果を上げています。
この会社は以前、単なる会社情報の掲載だけのホームページを運営していました。
スマートフォン対応も不十分で、問い合わせにつながる設計がされていませんでした。
そこで次のような改善を実施しました。
- 問い合わせフォームの簡略化:訪問者が最小限の情報入力だけで依頼を送信できるようにしました。名前、連絡先、簡単な要件のみの入力で済むようにすることで、問い合わせの障壁を大きく下げることに成功しています。
- ビフォーアフター事例の掲載:施工前後の写真と詳細な説明を追加し、訪問者が具体的なイメージを持てるようにしました。これにより「自分の家もこうなるかも」という想像を促進し、問い合わせへの一歩を踏み出しやすくしています。
- 地域特化型SEO対策:「〇〇市 屋根リフォーム」など、地域名と業種を組み合わせたキーワードで検索順位を向上させました。地域に特化することで、実際に工事可能なエリアからの質の高いアクセスを集めることに成功しています。
この取り組みの結果、A社は問い合わせ数が以前の3倍に増加しました。
検索エンジン経由の訪問者も月間500人以上増えました。
さらに重要なのは、問い合わせの質も向上し、成約率が上がったことで売上が前年比120%にアップしたことです。
実践のポイント
- 問い合わせフォームは必要最小限の情報のみを求める(電話番号や住所など詳細情報は初回問い合わせでは求めない)
- 具体的な事例写真や成果を見せることで、訪問者の不安を解消する
- 自社の強みが発揮できる地域や分野に特化したコンテンツを作成する
- トップページだけでなく、サービス詳細ページにも適切に問い合わせボタンを配置する
このA社の事例が示すように、問い合わせ増加に必要なのは「訪問者の立場に立った導線設計」です。
訪問者が何を知りたいか、どんな不安を抱えているか、そしてどうすれば行動を起こしやすくなるかを常に考慮したサイト設計が重要なのです。
見込み客に困らない企業の共通点②:「問い合わせする理由」を明確に提示している
そもそも、ホームページに訪れる人は、すぐに問い合わせをしようと考えているわけではありません。
多くの訪問者は情報収集の段階であり、「なぜ今、この会社に問い合わせるべきなのか」という明確な理由がなければ行動に移しません。
見込み客に困らない企業は、この「問い合わせする理由」を明確に提示することで、訪問者の背中を押しています。
問い合わせの障壁を取り除く方法
あなたの会社のホームページ訪問者が、問い合わせをしない、ためらう理由は様々存在します。
- 問い合わせたら営業攻勢をかけられるのでは?
- まだ検討段階なのに問い合わせしても大丈夫だろうか
- この会社が自分の課題を本当に解決できるのか不安
- 問い合わせても迅速に対応してもらえるだろうか
これらの不安や懸念を解消するために、問い合わせという成果を出すサイトでは、以下のような工夫がされています。
- 問い合わせ後の流れを明示する:「お問い合わせいただいた後、24時間以内に担当者からご連絡します」など、次に何が起こるかを説明
- 気軽さを強調する:「お見積りだけでも歓迎します」、「ご相談は無料です」といった表現で、気軽に問い合わせできることを伝える
- 不安を先回りして解消する:「営業電話が苦手な方はメールでのやり取りも可能です」など、懸念事項に先回りして対応
効果的な「次のステップ」の提案方法
問い合わせを増やすためには、訪問者の状況や性格に合わせた、複数の「次のステップ」を用意することも効果的です。
即決タイプ向け
- 「今すぐお問い合わせ」
- 「無料見積りを依頼する」
情報収集タイプ向け
- 「資料をダウンロードする」
- 「事例集を請求する」
- 「メールマガジンに登録する」
慎重タイプ向け
- 「よくある質問をチェック」
- 「お客様の声を読む」
- 「無料診断を受ける」
これらの選択肢を適切に配置することで、どの段階の訪問者でも「次のステップ」を踏み出せるようになります。
具体的な改善事例
IT企業A社の事例をご紹介しましょう。この企業はサービスサイトの直帰率が高く、問い合わせ数が伸び悩むという課題を抱えていました。
そこで次のような改善策を実施しました。
- 問い合わせ動線の最適化:各ページに適切なCTAボタンを配置し、ユーザーがどのページからでもスムーズに問い合わせできるようにしました。
- フォームの入力項目の簡略化:必須項目を7個以内に抑え、ユーザーの入力負担を大幅に軽減しました。
- フローティングCTAボタンの設置:スクロールしても常に画面上にCTAボタンが表示されるようにし、ユーザーがいつでも問い合わせアクションを取れるようにしました。
これらの取り組みの結果、驚くべき成果が得られました。
問い合わせ数が月間15件から32件へと約2倍に増加し、直帰率は62%から38%へと大幅に改善。さらにコンバージョン率(CVR)も1.2%から2.8%へと向上しました。わずか3ヶ月という短期間での成果で、驚くべきスピード感です。
見込み客に困らない企業の共通点③:「自動的な関係構築」の仕組みを持っている
見込み客に困らない企業は、ホームページを単なる「問い合わせ受付窓口」としてではなく、「長期的な関係構築の起点」として活用しています。訪問者との一期一会の出会いを大切にし、その場で問い合わせに至らなくても、継続的な接点を確保する仕組みを構築しているのです。
人間関係と同じように、ビジネスにおいても信頼関係の構築には時間がかかります。「自動的な関係構築」の仕組みを持つことで、初回訪問時には準備ができていなかった訪問者も、時間をかけて大切な顧客へと育てることができるのです。
即決しない見込み客を逃さない仕組み
では、どのようにして長期的な関係を作って行けば良いのか?
そもそも、ほとんどの訪問者は、すぐに問い合わせをしないと伝えましたが、それは次のような理由からです。
- まだ情報収集の段階である
- 他社と比較検討中を行なっている
- 予算や時期が未定である
- 社内での合意が必要で、まだ合意に至っていない
こうした「熟度の低い見込み客」を育てていくための施策が、メールマガジンや資料ダウンロードといった「問い合わせよりもハードルの低い接点」を用意することです。
見込み顧客のメールアドレスを取得できれば、その後継続的に価値ある情報を届け、徐々に関係を深めていくことができます。この「即決しない見込み客との継続的な関係構築」こそが、安定した問い合わせ獲得の鍵なのです。
自動ナーチャリングの基本設計
見込み客との関係構築(ナーチャリング)を自動化するには、仕組みを整える必要があります。
具体的には、
- 資料ダウンロードなどの低ハードル接点の設置:資料、チェックリスト、簡易診断など、メールアドレスと引き換えに価値ある情報を提供します。(いわゆるホワイトペーパーなどです)
- ステップメールの活用:資料ダウンロード後、自動的に一連のメールを段階的に送信。徐々に信頼関係を構築していきます。
- 段階的な提案設計:初回は簡単な無料相談、次に小さな有料サービス、そして本格的な契約へと、段階的に提案のレベルを上げていきます。
この自動ナーチャリングにより、「まだ準備ができていない見込み客」が、「問い合わせる準備ができた顧客」へと変化していくのです。
中小企業でも実践できる具体的な手法
「自動ナーチャリング」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、小規模企業でも始められる方法はあります。
1. メールマーケティングツールの活用
比較的安価で使いやすいメール配信ツールがあります。 メール配信だけで有れば、3,000円程度のプランで十分スタートできます。
2. ダウンロード資料の作成
「〇〇業界の成功事例集」、「〇〇選びの7つのポイント」など、見込み客が本当に欲しい情報をコンパクトにまとめます。
3. 基本的なステップメールの設定
・1通目:資料のダウンロードのお礼と追加情報の提供
・3日後:よくある質問と回答の紹介
・7日後:事例紹介と簡単な相談の案内
・14日後:特別提案や期間限定サービスの案内
BtoB企業であるY社の事例をご紹介します。
Y社では新しくホワイトペーパーや事例集を作り、それらのダウンロードフォームを設置しました。
そして、ダウンロード後に計画的なステップメールを配信するように設定しました。
ダウンロード後の1通目のお礼メールから始まり、徐々に活用方法や導入事例を共有して最終的に無料トライアルへと誘導。
その結果、3ヶ月間で受注件数が増加し、ステップメールを通じて見込み顧客の関心度が高まり、商談化率が大きく向上したのです。
見込み客に困らない企業は、「今すぐ問い合わせる人」だけでなく「将来的に問い合わせる可能性のある人」とも継続的な関係を構築しているのです。
これにより、一度きりのホームページ訪問を無駄にせず、長期的な問い合わせ獲得につなげています。
今日から始められる!HPからの問い合わせを増やすための実践ステップ
ここまで見てきた「見込み客に困らない企業の3つの共通点」を踏まえて、あなたの会社でも今日から始められる具体的なアクションプランをご紹介します。一度にすべてを変える必要はありません。まずは小さな一歩から始めましょう。
まずはここから始める「最初の一歩」
問い合わせ増加への道のりは、次の3ステップから始めることをおすすめします。
1. 現状分析:訪問者の行動を知る
まずはGoogleアナリティクスなどのツールを使って、現在のホームページの閲覧状況を確認しましょう。どのページが最も見られているか、どこで離脱が多いのか、どのような経路で訪問者が来ているのかを把握します。
これにより、「どこを改善すれば最も効果的か」という優先順位が見えてきます。例えば、トップページの直帰率が高ければ、トップページで伝えている事やトップページからの導線設計を見直す必要があります。
2. 問い合わせフォームの簡素化
最も手軽に始められる改善は、問い合わせフォームの簡素化です。必須項目を最小限(名前、連絡先、問い合わせ内容程度)に減らし、入力の手間を減らしましょう。
また、フォームの前に「お問い合わせありがとうございます。24時間以内にご連絡いたします」など、問い合わせ後の流れを明記することで、訪問者の不安を軽減できます。
3. 問い合わせボタンの配置見直し
各ページの適切な位置に、目立つ問い合わせボタンを配置しましょう。特に以下のポイントに注意します。
- 長いページでは複数箇所に設置する
- スマートフォン表示でも見やすい位置に配置
- 「お気軽にご相談ください」など、ハードルを下げる文言を添える
これらの基本的な改善だけでも、問い合わせ数の増加が期待できます。
1週間で取り組める具体的なアクション
最初の一歩を踏み出した後、1週間程度で取り組める次のステップとして、以下のアクションをおすすめします。
1. 訪問者の悩みに直接応えるコンテンツの追加
お客様がよく抱える質問や課題をピックアップし、それに対する解決策をトップページや主要なランディングページに追加します。
「○○でお悩みではありませんか?」という問いかけと、それに対する具体的な解決方法を示すことで、訪問者の共感を得やすくなります。
2. 成功事例・ビフォーアフターの掲載
可能であれば、実際のお客様の声や成功事例をホームページに追加しましょう。
特に「Before→After」の変化が分かりやすい形で示すと、訪問者は自分自身の状況と重ね合わせやすくなります。
3. 問い合わせしやすい雰囲気づくり
「まずはお気軽にご相談ください」、「見積もりだけでもOK」、「○分程度の無料相談を承ります」など、初回問い合わせのハードルを下げるメッセージを追加します。
効果測定と継続的な改善のポイント
問い合わせ数を継続的に増やしていくためには、効果測定と改善のサイクルが欠かせません。
1. 数値の定期チェック
週に1回程度、Googleアナリティクスなどを使いホームページの閲覧状況を数字で確認しましょう。具体的には、以下の数字を確認します。
- ホームページの訪問者数
- 各ページの直帰率
- 問い合わせフォームの表示回数と完了率
- 問い合わせ数
2. A/Bテストの実施
可能であれば、問い合わせボタンの色や配置、見出しの文言など、一度に1つの要素だけを変更して効果を測定するA/Bテストを実施しましょう。
3. 顧客からのフィードバック収集
実際に問い合わせをしてくれた方に「どのページを見て決めたか」、「何が決め手になったか」を聞くことで、効果的な要素が見えてきます。
問い合わせを増やすための取り組みは、一度の改善で終わりではありません。訪問者の反応を見ながら、継続的に行なう事がとても大切です。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果につながっていきます。
まとめ
ホームページからの問い合わせを増やすことは、決して難しいことではありません。
見込み客に困らない企業の3つの共通点を理解し、計画的に取り組むことで、あなたの会社でも成果を上げることができます。
この記事でご紹介した3つの共通点をもう一度おさらいしましょう。
- 「訪問者の行動導線」を徹底設計している
訪問者の悩みに共感し、適切な情報を提供することで、自然に問い合わせへと導く仕組みを作り上げています。 - 「問い合わせする理由」を明確に提示している
訪問者の不安や疑問を解消し、問い合わせすることのメリットを明確に伝えることで、行動の障壁を取り除いています。 - 「自動的な関係構築」の仕組みを持っている
すぐに問い合わせに至らない見込み客とも継続的に関係を構築し、時間をかけて信頼を育む仕組みを整えています。
これらの共通点は、大規模なホームページのリニューアルやプロへの外注がなくても、少しずつ取り入れることができます。
まずは問い合わせフォームの簡素化や、訪問者の悩みに応えるコンテンツの追加など、できるところから始めてみましょう。
重要なのは「訪問者の立場に立って考える」こと。
自社の情報発信だけでなく、「訪問者が何を求めているか」、「どうすれば行動を起こしやすくなるか」を常に意識してホームページを改善していくことが、問い合わせ増加の鍵となります。
今日から始められる小さな一歩が、明日の大きな成果につながります。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひ貴社のホームページを「問い合わせが生まれる仕組みの土台」へと進化させてください。