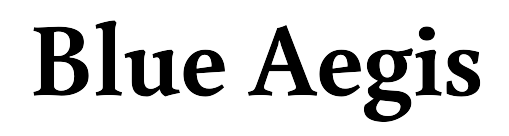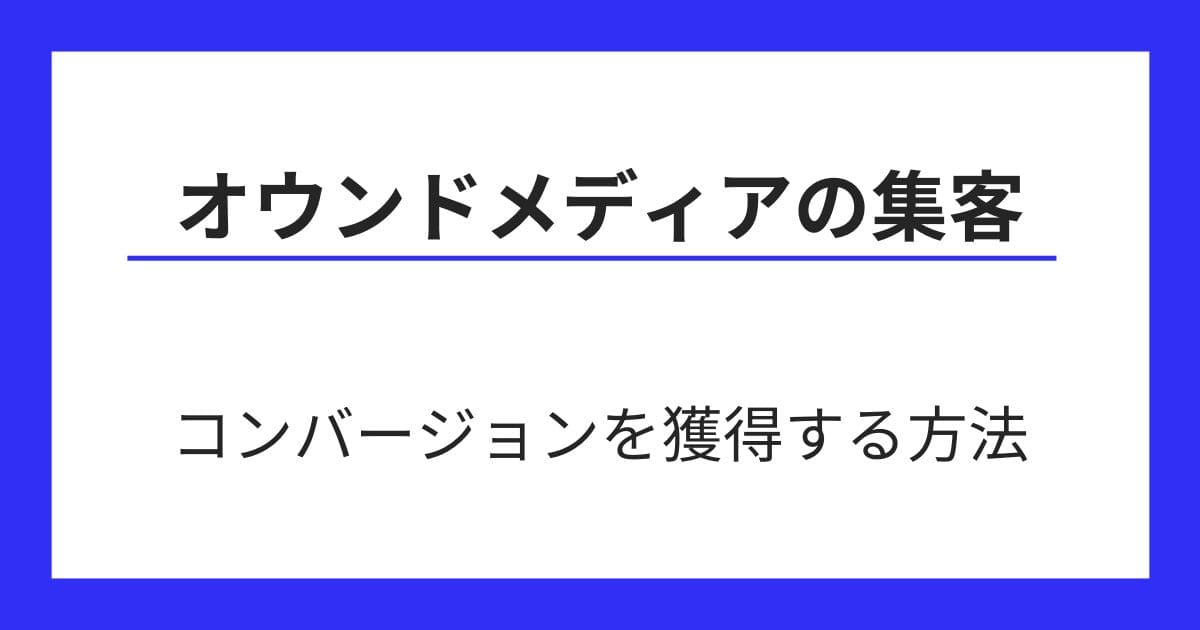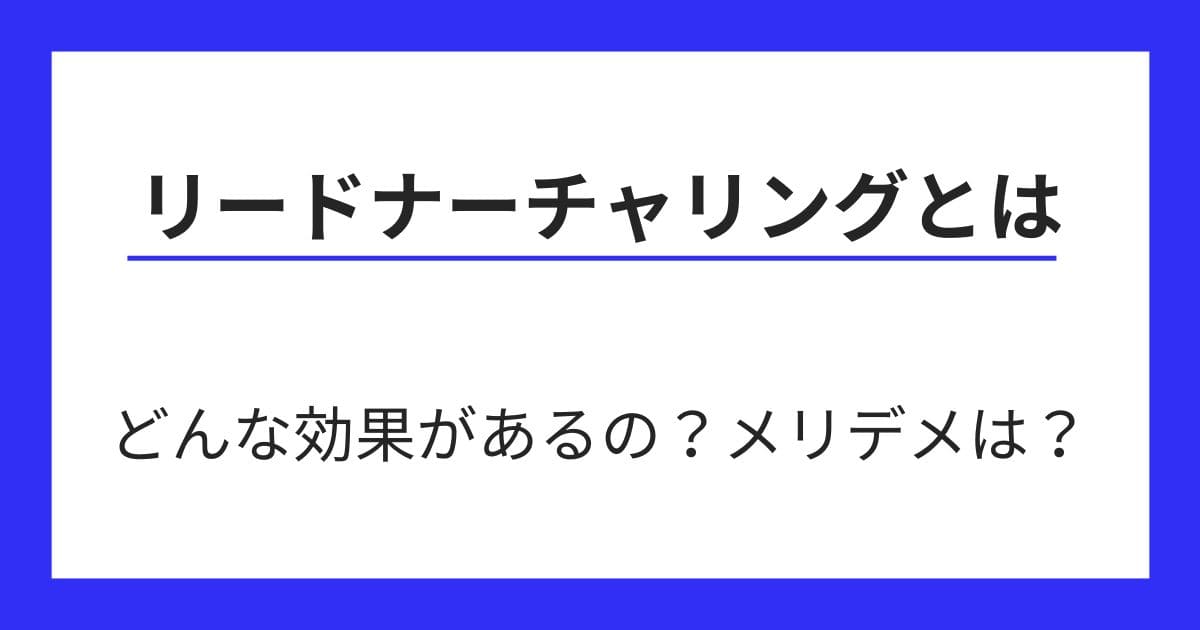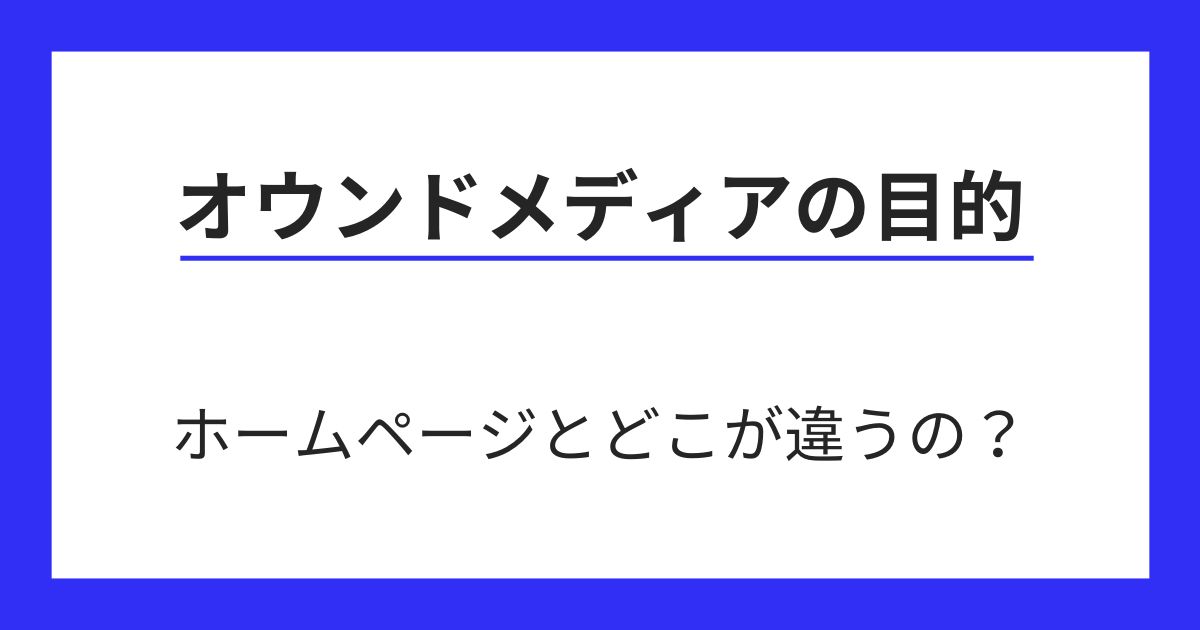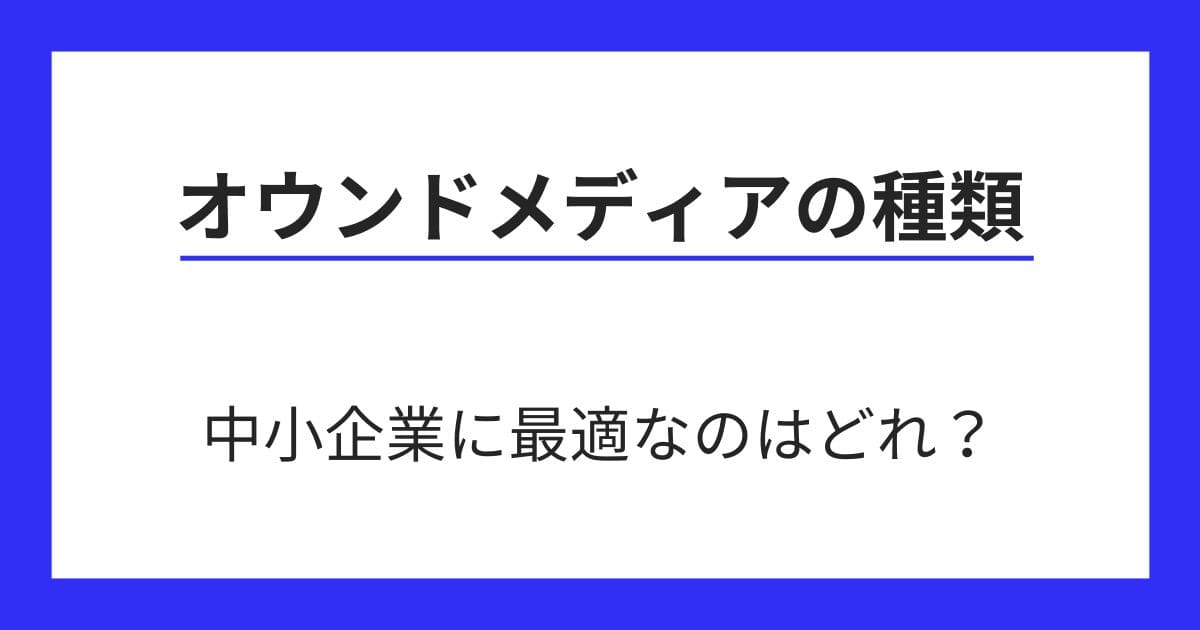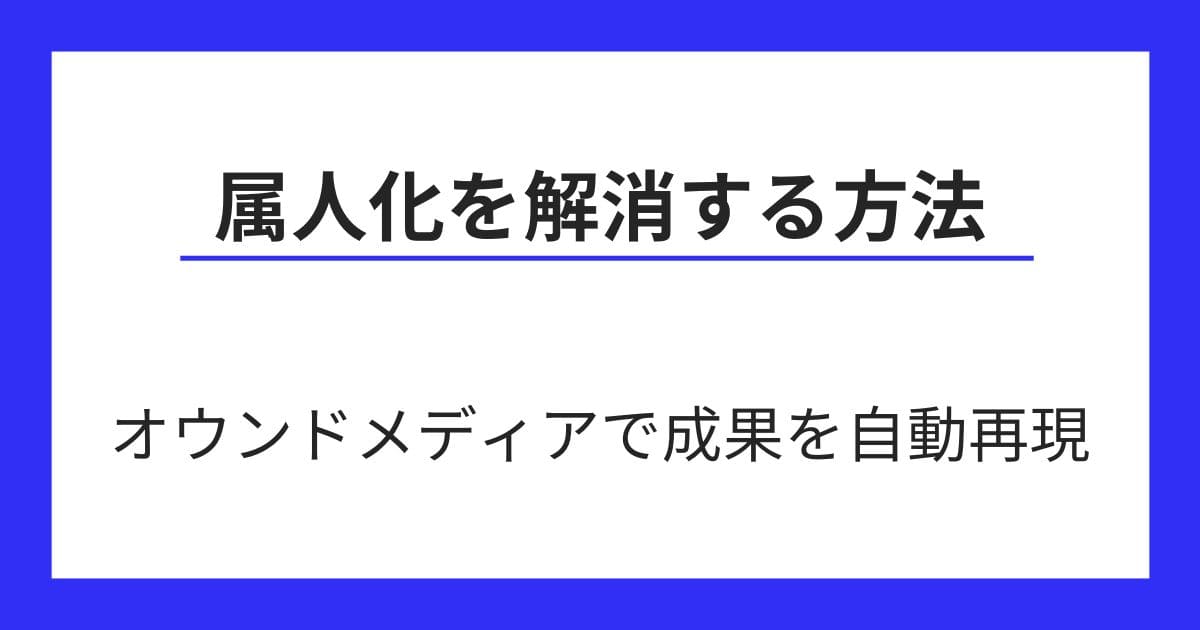「オウンドメディアで記事を書いても、問い合わせや相談につながらない」
こうした悩みを抱えておられるなら、本記事がお役に立てると思います。
オウンドメディアでコンバージョンを獲得するには、明確な「型」があります。
記事で集客し、CTAで行動を促し、メールで段階的に育成する。この流れを「仕組み」として設計すれば、中小企業でも属人的な営業に頼らず、継続的にコンバージョンを生み出すことができます。
この記事では、オウンドメディアでコンバージョンを獲得するための具体的な方法を、中小企業の現場で実践できるレベルで解説します。
オウンドメディアを「ただの情報発信」から「成果を生み出す仕組み」へと進化させ、24時間365日働き続ける資産に変えていきましょう。
【結論】オウンドメディアでコンバージョンを獲得する方法は?
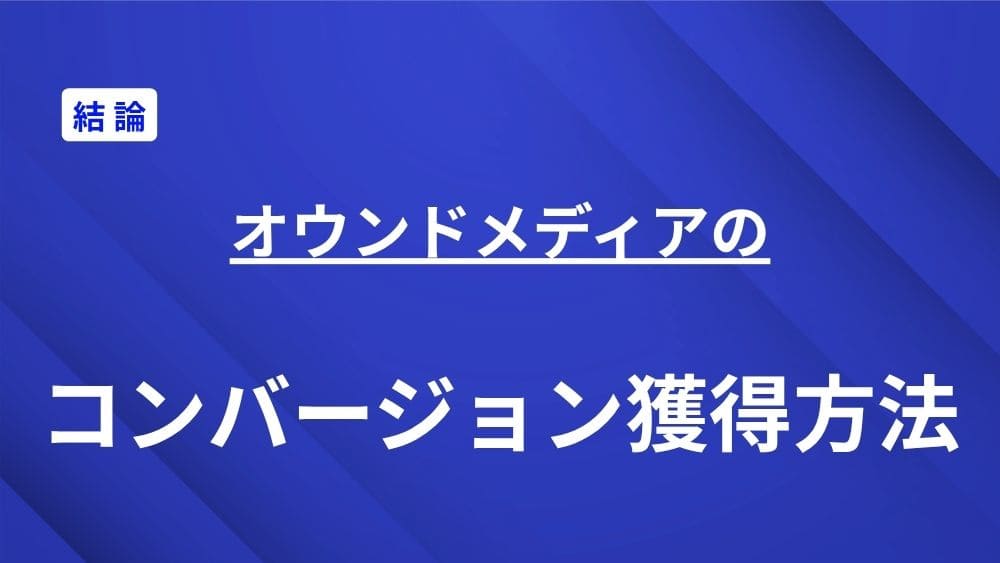
オウンドメディアでコンバージョンを獲得するには、記事で集客し、CTAで行動を促し、ナーチャリングで育成する流れを仕組み化することが重要です。
重要なポイントは以下の5つです。
【この記事のポイント】
- SEOで記事にアクセスを集め、検索意図に応える内容で満足を得る
- 記事内に複数のCTAを設置し、マイクロコンバージョン(メルマガ登録・資料DL)に誘導する
- ステップメールを活用し心理ステージに沿って段階的に育成、コンバージョンへ繋げる
- PV・CTAクリック率・フォーム送信率を計測し、問題箇所を特定する
- 月次レビューで改善サイクルを回し、継続的に成果を向上させる
この5つを「仕組み」として設計することで、属人的な営業に依存せず、オウンドメディアが自動的にコンバージョンを生み出し続けます。
以下、それぞれの具体的な方法を詳しく解説していきます。
オウンドメディアでコンバージョンを獲得する方法

多くの中小企業が抱える、オウンドメディアで「コンバージョンが発生しない」という課題に対応するため、コンバージョンを獲得する方法を具体的に解説します。
この課題を解決するには、集客から行動完了までの導線を、読者の心理に寄り添いながら設計する必要があります。
関連記事:オウンドメディアとは何?
オウンドメディアにしっかりとアクセスを集める
コンバージョンを増やすための第一歩は、オウンドメディアへのアクセス数を確保することです。どれだけ優れた導線設計や魅力的なオファーを用意しても、そもそも訪問者がいなければ成果は生まれません。
コンバージョン数はアクセス数とコンバージョン率の掛け算で決まります。

たとえば、月間1,000アクセスでコンバージョン率が2%なら、月20件のコンバージョンが想定されていることになります。これを月40件に増やすには、アクセス数を2,000に増やすか、コンバージョン率を4%に改善するか、あるいはその両方が必要になります。
中小企業にとって最も費用対効果の高いオウンドメディアへの集客手段は、SEOによる自然検索流入です。広告のように継続的な費用が発生せず、一度上位表示されれば安定的にアクセスを集められます。
SEOで成果を出すには、検索意図に合致した記事を作成することが不可欠です。オウンドメディアでコンバージョンを獲得する為に、意識しておくべき検索キーワードには大きく分けて2つのタイプがあります。
- Knowクエリ(情報収集型)
「◯◯とは」「◯◯の方法」など知識を得たい段階の検索です。検索ボリュームが大きく、多くのアクセスを集められる一方で、すぐにコンバージョンには至りにくい傾向があります。 - Buyクエリ(購買検討型)
「◯◯ おすすめ」「◯◯ 費用」「地域名+サービス名」など、具体的な行動を検討している段階の検索です。検索ボリュームは少なめですが、コンバージョン率は高くなります。
理想的なアクセス獲得戦略は、Knowクエリで流入数を増やしながら、Buyクエリで確実にコンバージョンを獲得するという両輪のアプローチです。
ただし、オウンドメディアを立ち上げたばかりで記事本数が少ない段階では、まず記事数を増やすことを優先してください。
一般的には、60本程度の記事がないと検索エンジンからの評価が得られにくく、どれだけ良質な記事を書いても上位表示されにくいためです。
SEO以外にも、SNS(FacebookやX)での情報発信、既存顧客へのメール配信、リスティング広告など、複数のチャネルからの流入も視野に入れましょう。
特にオウンドメディアを立ち上げた初期段階では、SEO効果が出るまでに時間がかかります。即効性のある施策と組み合わせることが重要です。
関連記事:オウンドメディアに集客出来ない原因はSEOではない?
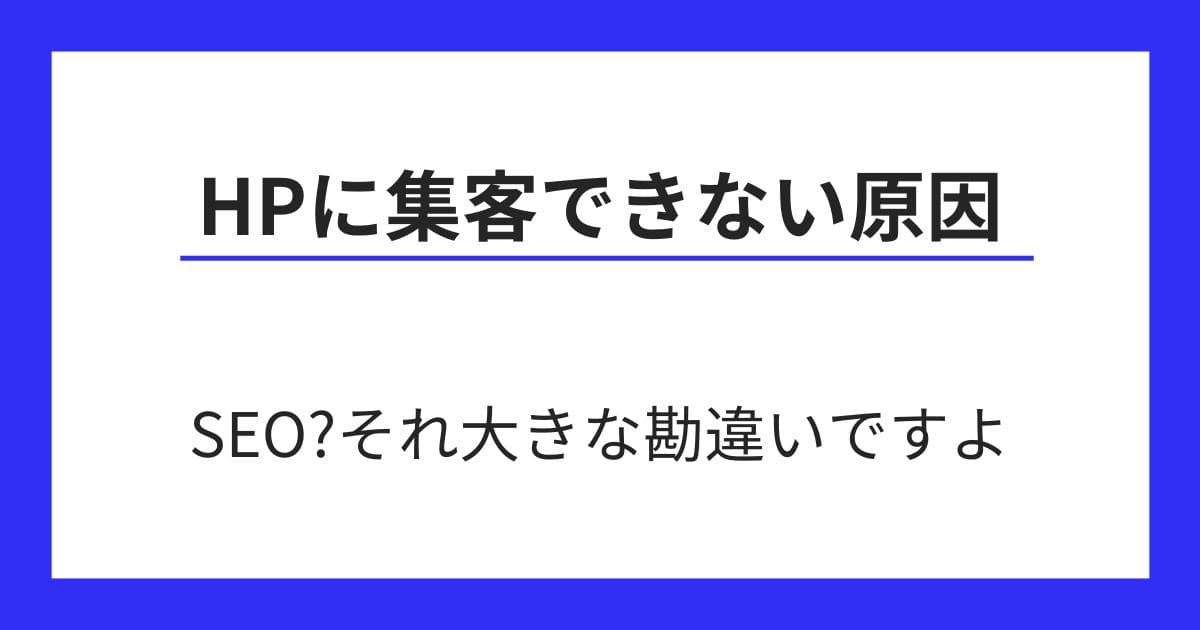
関連記事:オウンドメディアに簡単に集客する方法
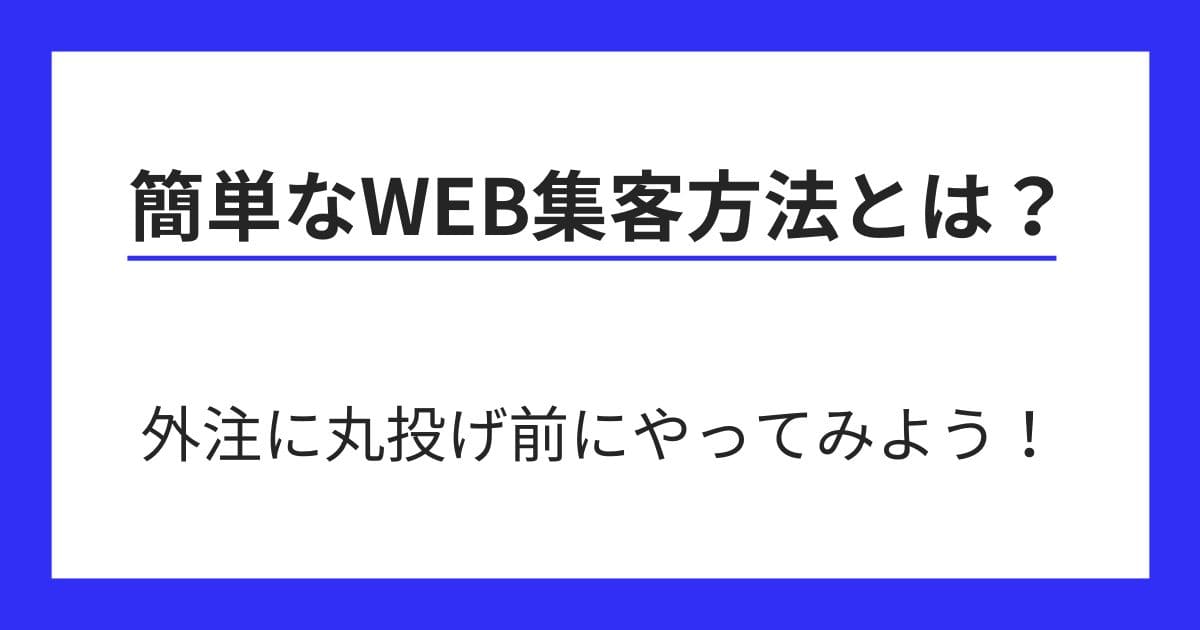
記事で読者の検索意図に応え満足を得る
アクセスを集めることに成功しても、訪問した読者が記事に満足しなければ、その後のコンバージョンにはつながりません。
コンテンツの質こそが、すべての成果の起点となります。
読者がオウンドメディアの記事にたどり着くのは、何かしらの「知りたいこと」や「解決したい悩み」があるからです。検索意図に対する答えが不十分だったり、期待と違う内容だったりすると、読者は数秒で離脱してしまいます。
逆に、記事を読んで「これは役に立った」「この会社は詳しいな」と感じた読者は、その企業に対して信頼感を抱きます。
この信頼の蓄積がなければ、個人情報を渡してホワイトペーパーをダウンロードしたり、問い合わせフォームに入力したりという行動は起きません。
でも、ここで疑問が沸きませんか?
じゃあ、満足度の高い記事とはどういった記事なのか?って事です。
読者を満足させる記事とは、専門性×分かりやすさ×網羅性の3つが揃った記事です。
専門性とは
その分野の深い知識やノウハウ、実務経験に基づいた情報によって感じられます。
たとえば歯科医院のオウンドメディアであれば、「虫歯治療の最新技術」や「インプラントと入れ歯の使い分け」といった専門的な内容を、実際の臨床・治療経験を交えて解説することで専門性が伝わりますよね。
表面的な一般論では読者の心は動きません。
知見とノウハウに基づいた深掘りした記事にすることが大切で、つまりそれが専門性です。
分かりやすさとは
専門用語を避けるか、使う場合は必ず補足説明を入れ、中学生でも理解できる文章で書くことで得られます。
引越し業者のオウンドメディアであれば、「養生」という業界用語がありますが、その言葉をそのまま使うのではなく、「養生(建物の床や壁を傷つけないよう保護すること)」と説明を加えるだけで、読者の理解度は大きく変わります。
網羅性とは
検索意図の土台にある、読者が本当に知りたい情報をその記事だけで完結させる為に、必要な情報を1記事にまとめることです。
たとえば飲食店向けPOSシステムの機能について検索した読者について想像してみましょう。この読者は「POSシステムの機能」について検索していますが、その検索行動の根底にある事は「POSシステムの導入を検討していて、比較検討を行なっている」という事が想定されます。
その前提に立つと記事として作るべきなのは、POSシステムの基本機能の説明だけでなく、導入費用、導入事例、他システムとの比較、よくある質問まで情報の網羅性を高めることで、読者は複数の記事やサイトを行き来する必要がなくなります。
中小企業のオウンドメディア担当者がよく心配するのは、「こんなに詳しく書いて大丈夫だろうか」「ノウハウを出しすぎではないか」という点です。
しかし、「この情報を無料で公開して大丈夫?」と心配になるレベルの情報を出すからこそ、読者は価値を感じるのです。
例えば、整体院のオウンドメディア記事で「腰痛を自分で改善するストレッチ方法」を、写真付きで詳しく解説したとします。
一見すると「これを見て自分で解決されてしまったら来院しないのでは?」と思えます。…が、実際には逆です。
詳しい情報を提供することで「これだけ専門知識がある先生なら信頼できる」と感じた読者が、セルフケアでは限界を感じたときに、真っ先に相談先として選ばれることになるからです。
こうして記事で読者を満足させることができたなら、次はその満足した読者を適切なアクションへ誘導する仕組みが必要です。
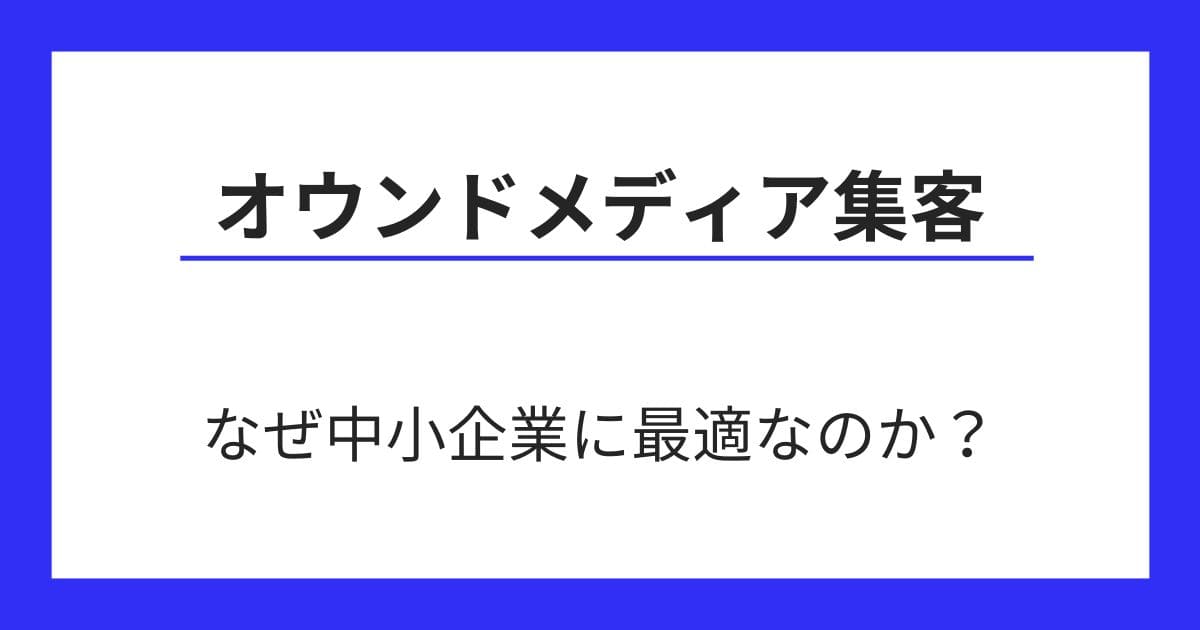
記事中に複数のCTAを置く
良質な記事で読者を満足させても、次のアクションを促す仕組みがなければ、読者はそのままページを離れてしまいます。
ここで重要になるのがCTA(Call To Action:行動喚起)です。
多くのオウンドメディアでは、コンバージョン獲得のためにCTAを「記事の最後に1つだけ」設置していますが、これでは機会損失が発生します。なぜなら、すべての読者が記事を最後まで読むとは限らないからです。
記事の途中で「知りたいことが分かった」と感じた読者や、時間がなくて流し読みしている読者は、記事の中盤で離脱してしまいます。
このとき、記事下にしかCTAがなければ、興味を持った読者との接点を逃すことになります。
効果的なCTA設置の基本は、読者の目に触れる複数の場所に配置すること。具体的には以下の場所にCTAを設置すると、クリック率が上がります。
タイトル直下または目次の前後
1〜3行程度のシンプルなテキストCTAを設置します。
たとえば社労士事務所のオウンドメディアであれば、「就業規則の見直しチェックリストを無料ダウンロード」といった形です。記事を読み始める前の段階で、「このサイトには役立つ資料があるな」と認識してもらえます。
H2セクションの終わり
記事の文脈に合わせたCTAを入れます。
防犯カメラ販売会社の記事で「家庭用防犯カメラの選び方」というH2セクションの後なら、「防犯カメラ選びの比較表をダウンロード」というCTAが自然です。記事の流れを邪魔せず、読者が「ちょうど欲しかった」と感じるタイミングで提示できます。
記事の最下部
バナー形式やボックス形式で目立つCTAを配置します。最後まで読んでくれた読者は興味関心が高い状態なので、ここでしっかりと行動を促します。
画面下部の固定バナー
これはスマートフォンで記事を読んでいるときに、画面の最下部に常に表示されるCTAです。
読者がどのページを見ていても、スクロールに関わらず常に視界に入るため、コンバージョンにつながりやすくなります。
ただし、CTAを複数設置する場合には注意点もあります。
あまり多くのCTAを設置すると、「くどい」印象を与えるため、設置場所はしっかりと読者からどう見えるかを評価した上で決定しましょう。
また、記事中のCTAはテキストリンク形式にすることで、記事の流れを邪魔せずに自然に溶け込ませることができます。
CTAの色、文章に気を配る
CTAを適切な場所に設置しても、「何を伝えるか(言葉・文章)」と「どう見せるか(デザイン・色)」が最適化されていなければ、クリック率は大きく下がります。
限られたアクセス数を最大限活かす必要のある中小企業こそ、この2点を徹底的に磨くべきです。
CTAボタン(行動喚起ボタン)の色を目立たせる
CTAボタンやバナーは、サイト全体のデザインに溶け込みすぎると読者の目に留まりません。かといって、デザインから完全に浮いた色にすると違和感を与えます。
一般的には、緑、オレンジ、青がクリック率の高い色ではあります。その理由は色は視認性が高く、行動を促す色として心理的に作用するためです。
ただし、これはあくまで一般論。自社のオウンドメディアのキーカラーとの対比を意識することが大切です。
「正解となるCTAボタンの色」はオウンドメディア毎に異なるので、A/Bテストを繰り返し最も相性のよい色を探しましょう。
読者視点の利点(ベネフィット)を明示する
多くのオウンドメディアやホームページで見られる「お問い合わせはこちら」というボタンの文言。
この文言は企業側の都合を伝えているだけです。読者にとってのメリットが何も示されておらず、「このボタンを押したい」という心理的誘惑は起きません。
その心理状態ではこのボタンは押されないので、押したくなる理由を作る必要があるという事です。
たとえば会計ソフト販売会社のオウンドメディアであれば、「お問い合わせはこちら」ではなく「経理業務を50%削減できる無料デモを試す」とすることで、読者は「自分にとって何が得られるのか」を明確にイメージでき、ボタンを押したくなります。
心理的ハードルを下げるキーワードを使う
「無料」「限定」「チェックリスト」「ガイド」「テンプレート」といった言葉は、読者の行動を後押しします。
たとえば不動産会社のオウンドメディアなら、「今すぐ資料請求」というボタンよりも「オーナー向け空室対策の無料チェックリストをダウンロード」の方が、具体性があり、無料という安心感もあるのでクリックされやすくなります。
記事の文脈に合わせたCTAコピーにする
すべての記事に同じCTAを設置している企業が多いですが、これは効果を下げる原因になります。
印刷会社のオウンドメディアを例にしますが、「名刺デザインのコツ」というテーマの記事には「名刺デザインテンプレート集を無料ダウンロード」というCTAがぴったりと合いますよね。
しかし「チラシの効果的な配布方法」をテーマとした記事に、先ほどと同じ「名刺デザインのコツ」のCTAを出しても、文脈が合わず違和感があります。これだと、押したくなりません。
この記事テーマの場合であれば、「チラシ配布計画シート無料DL」の方がより自然で、押したくなりませんか。
このように、記事のテーマとCTAのオファーを一致させることで、読者は「ちょうど今知りたかった情報だ」と感じ、クリック率が向上します。
読者の状態に応じた段階的コンバージョンを設計する
オウンドメディアの記事にやってきた読者の中には、まだ情報収集をしているだけの人もいれば、具体的にサービスや商品を比較検討している人もいます。
情報収集段階の読者に「問い合わせ」を求めても、心理的ハードルが高すぎて行動は…しませんよね。
そこで必要なのが、読者の状態・温度感に応じた段階的コンバージョンの設計です。
マイクロコンバージョン
マイクロコンバージョンとは、ホワイトペーパーのダウンロード、チェックリストの入手、メルマガ登録など、比較的ハードルの低い行動を指します。
まだ購買意欲が高くない読者でも、「無料で役立つ情報がもらえるなら」と行動しやすくなります。
マイクロコンバージョンをによって、読者のリード情報(名前やメールアドレスなど)を獲得できれば、それを起点にしてメールやLineを活用して継続的に読者と接点を持ち、「教育(ナーチャリング)」が行えるようになります。
読者に対して段階的に必要な情報を提供することで、「欲しい」と感じてもらうことができるので、メインコンバージョンへと橋渡しすることができます。
例えば弁護士事務所のオウンドメディアだとしましょう。「相続手続きの流れ」という入門的な記事を読んでいる人は、まだ具体的に依頼を検討している段階ではありません。
この段階で「今すぐ無料相談」を促しても、「まだそこまで考えていない」ので、何も起きることはありません。しかし「相続手続きチェックリスト無料ダウンロード」なら、「今後のために資料だけもらっておこう」と行動する可能性が高まります。
メインコンバージョン(商談への直接接続)
メインコンバージョンとは、「無料相談の申し込み、問い合わせ、見積もり依頼、購入など」、商談や成約に直接つながる行動を指します。
すでに比較検討段階にある読者やマイクロコンバージョン後に教育済みの場合には、メインコンバージョンのほうがより有効です。
「相続税対策 弁護士 費用」といったキーワードで検索してきた読者は、そのキーワードが意図するところから、具体的に依頼先を探している可能性が高い状態だということが分かります。
この場合は「初回相談無料・30分で現状診断」といったメインコンバージョンが前面に出ていた方が、スムーズに商談へつなげられます。
マイクロCVからメインCVへ育てる仕組み
※CV=コンバージョン
マイクロコンバージョンで獲得した読者は、最適化した教育(ナーチャリング)によって心理ステージを移動させ、メインコンバージョンへと誘導します。
住宅リフォーム会社であれば、マイクロコンバージョンである「リフォーム費用の相場ガイド」をダウンロードした読者に対して、ステップメールで以下のような情報を段階的に送付します。
「リフォーム事例集」
↓
「補助金活用ガイド」
↓
「よくある失敗事例」
↓
「成功事例集」
自分にとって役立つ情報を何度も送ってくれるリフォーム会社に対して、読者は専門性を感じますし、この会社なら大丈夫かもしれないという信頼の感情を抱きます。
そのタイミングで「無料見積もり診断」へと誘導すれば、いきなり問い合わせを求めるよりも高い確率でメインコンバージョンにつながります。
このように、読者の温度感に合わせた段階的な設計をすることで、「今すぐ客」だけでなく「将来客」も取りこぼさずに、自社の見込み客リストとして蓄積することができます。
記事タイプ別のCTA出し分け基準
記事のキーワードや検索意図に応じてCTAを出し分けることで、より精度の高い訴求を行なう事ができます。
読者の心理状態に沿ったオファーが行えるので、より質の高いコンバージョンを狙えますし、獲得できるコンバージョンの数も増加します。
- 「◯◯とは」「◯◯の方法」などの入門・情報収集キーワード
チェックリスト、ガイドブック、基礎資料などのマイクロCVを設置 - 「◯◯ 費用」「◯◯ 比較」「地域名+サービス名」などの比較検討キーワード
無料相談、無料診断、見積もりなどのメインCVを設置 - 「◯◯ おすすめ」「◯◯ 選び方」などの中間キーワード
マイクロCVとメインCVの両方を併記し、読者に選んでもらう
入力フォームを改善する
CTAをクリックした読者の全員が、入力フォームを経てコンバージョンするわけではありません。およそ50~70%は、入力フォームの段階で離脱してしまいます。
せっかく記事で満足してもらい、CTAをクリックしてもらっても、入力フォームで離脱されては意味がありません。
そこで、入力フォームの最適化(EFO:Entry Form Optimization)を行い、コンバージョン直前の機会損失を防ぎます。
行動するつもりでフォームを開いたのに、途中で諦めてしまう読者をいかに減らすかが勝負、ということです。
読者が入力フォームで離脱する主な原因は以下の4つあります。
- 入力項目が多すぎて面倒
- どう入力すればよいか分かりにくい
- エラー表示が不親切で修正方法が分からない
- スマートフォンで入力しづらい
これらの問題を解決するために、中小企業でも実践できるEFO施策を紹介します。
入力項目を最小限に絞る
入力フォームで最も重要なのは、本当に必要な項目だけに絞ることです。
いわゆる普通の問い合わせフォームなのに、15項目もの入力欄を設けているケースなどもあります。
例えば以下のような項目ラインナップです。
- 氏名
- メールアドレス
- 電話番号
- 会社名
- 住所
- 従業員数
- 売上規模
- 相談内容
- 希望日時
- 当社を知ったきっかけなど
普通に考えて、「面倒だな」と感じますよね。
特にマイクロコンバージョンや初回の問い合わせ段階で必要な情報は、氏名・メールアドレス・電話番号・相談内容の4項目程度で十分です。
詳細情報は実際に商談するタイミングで聞けばよいのです。
「営業で使うから」「マーケティング分析に使うから」という、こちら側目線の理由でついつい項目を増やしたくなりますが、フォームの通過率が下がれば本末転倒です。
まずはコンバージョン数を最大化することを優先しましょう。
入力例を明示して迷わせない
「どう入力すればよいか分からない」という迷いは、離脱の大きな原因です。各入力項目には必ず入力例を表示し、迷いなく「スッと」入力できるようにしましょう。
たとえば電話番号の欄に「0x0-1234-56xx」と薄いグレーで表示しておくだけで、「ハイフンは必要なのか」「携帯電話でもいいのか」といった迷いがなくなります。
こうした、本当に少しの気遣いによって、入力率や離脱率が変わります。
読者目線で考える事が大切です。
リアルタイムでエラーを表示する
入力内容にエラーがある場合、すべて入力し終わって送信ボタンを押した後に「メールアドレスの形式が正しくありません」と表示されると、読者は大きなストレスを感じます。
理想的なのは、入力中または入力直後にリアルタイムでエラーを知らせる仕組みです。
メールアドレス欄にメールアドレスをコピーしたら、半角スペースが入っていた場合、その場で「メールアドレスに半角スペースが含まれています」と表示する、電話番号が桁数不足なら、「10桁または11桁で入力してください」と即座に教える。
こうすることで、最後にまとめて修正する手間がなくなり、離脱率が大幅に下がります。
残り項目数や所要時間を明示する
入力項目が多い場合や複数ページで構成されたフォームなどは、「あとどれくらい入力すれば終わるのか」が分からないと、読者は不安になります。
フォームの上部に「入力完了まで約1分」「残り3項目」「1/3ページ目」といった表示を入れるだけで、読者は見通しを持って入力を進められます。
住所の自動入力機能を導入する
郵便番号を入力したら住所が自動で入力される機能は、ユーザーの手間を大きく削減します。
特に郵送系の資料請求フォームの場合などであれば、郵便番号「150-0001」と入力した瞬間に「東京都渋谷区神宮前」まで自動入力されれば、読者は番地以降を入力するだけで済みます。
この小さな配慮が、離脱防止に大きく貢献します。
他ページへのリンクは設置しない
入力フォームとしてポップアップではなくページを表示する場合には、通常の記事ページとは異なり、サイトTOPや他の記事などへ移動するリンクを極力設置しないようにしましょう。
通常の記事ページには表示されているヘッダーメニューやフッターリンクも、フォームページでは非表示にしておくほうが良い結果になることが多いです。
入力途中に他の記事や他のことに気を散らしてしまって、別のページに移動されてしまうことを防ぐためです。
出来るだけフォームの入力に集中出来る環境を作り、フォーム入力を完了するという目的を達成しやすい状況を作るという事です。
また、特にスマートフォンにおいては、誤タップにより別ページに移動してしまい、戻ってきたら入力内容が消えていた、という事態を防ぐためでもあります。
スマートフォンでの入力のしやすさを確保する
現在、多くのオウンドメディアではスマートフォンからのアクセスが50%以上を占めています。BtoCのビジネスであれば、70%を超えることも普通です。
PC向けに最適化されたフォームでは、スマホでは非常に入力しづらいケースがあります。
入力欄が小さすぎてタップしづらい、フォームが画面からはみ出る、キーボードが表示されると入力欄が隠れる、といった問題がないか、必ずスマートフォンを使って確認を行ないましょう。
以上の6つの方法を実践することで、オウンドメディアのコンバージョン率は着実に向上します。
この一連の流れを、読者の心理に寄り添いながら設計することが、中小企業のオウンドメディア成功の鍵です。
関連記事:オウンドメディアの成果を最大化する方法
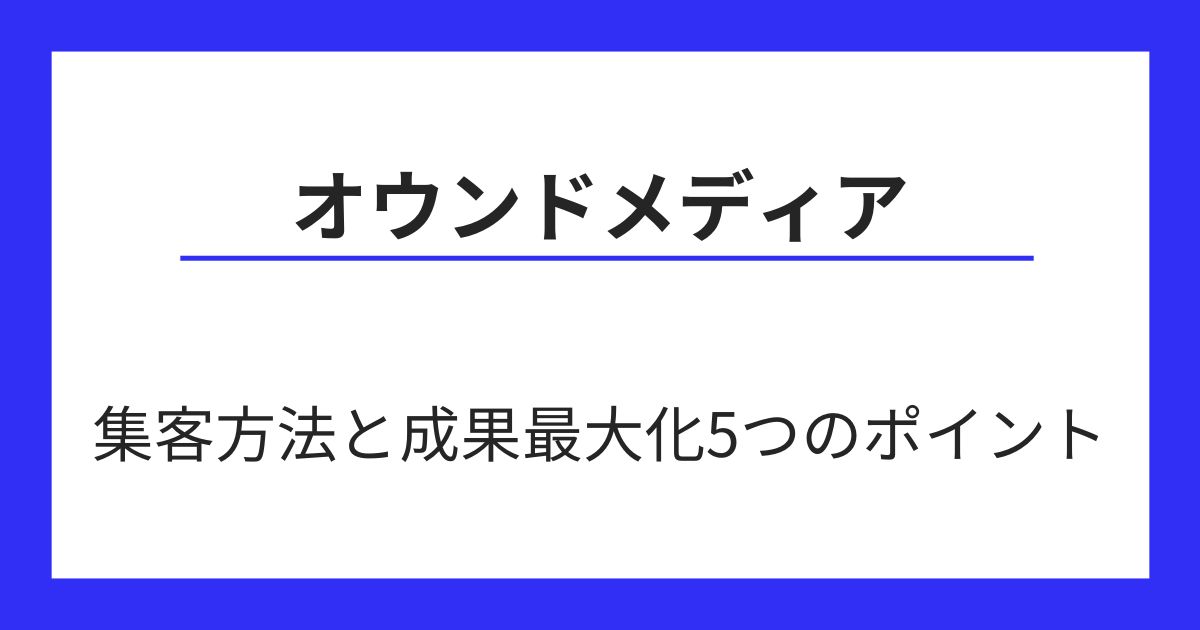
読者の心理ステージ別コンバージョン設計

読者はオウンドメディアにたどり着く時点で、それぞれ異なる心理状態にあります。「まだ何も知らない」段階の人もいれば、「具体的に比較検討している」段階の人等、その心理は大きく4つのステージに分けられます。
認知(興味喚起)
↓
理解(共感・問題意識)
↓
信頼(比較・安心)
↓
行動(申込・相談)
この段階を順に経て、最終的なメインコンバージョンに至ることになるので、各ステージで読者が何を感じ、何を求めているのかを理解し、それに応じたコンテンツとオファーを用意することが、成果を最大化する鍵となります。
認知(興味喚起)
このステージの読者は、自分の課題や悩みに気づき始めた段階です。まだ具体的な解決策を探しているわけではなく、「そもそもこれは何だろう」「なぜこんなことが起きるのだろう」という疑問を持っています。
読者の心理状態
この段階の読者の心理は以下のような状態です。
- まだ緊急性を感じていない(「そのうち調べればいいか」という温度感)
- 専門用語が多いと拒否反応を示す
- 自分に関係があるのかさえ分からない
- 無料の情報で十分だと思っている
この段階で「今すぐ顧問契約」や「無料相談に申し込む」といったオファーを出しても、読者は「まだそこまで考えていない」ので、何も行動することはありません。
この段階で提供すべきコンテンツ
認知段階の読者には、基礎知識を分かりやすく伝えることが最優先です。
この時に重要なのは、読者に「これは自分に関係がある」と気づかせることです。
引越し業者のオウンドメディアで「引越し準備はいつから始めるべきか」という記事なら、「引越しの2ヶ月前から準備を始めないと、希望日に引越せないこともあります」と具体的なリスクを示すことで、「自分も気をつけないといけないな」という意識が芽生えます。
この段階で適切なコンバージョン
認知段階では、以下のようなハードルの低い情報提供型のオファーが適切です。
- 基礎知識をまとめたPDFガイド
- 初心者向けチェックリスト
- 用語集のダウンロード
- メルマガ登録(週1回の役立ち情報配信)
認知段階での成功のポイント
1. 売り込まない
この段階で自社サービスを前面に出すと、読者は警戒します。「情報を提供してくれる親切な会社」という印象を与えることが、後の信頼構築につながります。
2. 次の疑問を示す
記事の最後で、「基礎が分かったら、次は◯◯について知りたくなるはずです」と、次の段階への道筋を示しましょう。整体院のオウンドメディアだとすれば、「原因が分かったら、次は対策方法を知りたいですよね。詳しくはこちらの記事で」と誘導することで、読者を次のステージへ進めます。
3. 専門家としての信頼を築く
基礎的な内容でも、「さすがプロの視点だ」と感じさせる情報を盛り込みます。歯科医院のオウンドメディアで「虫歯予防の基本」を書く際、「実は、食後すぐの歯磨きは逆効果のケースもあります」といった一般的に知られていない専門知識を加えることで、「この歯科医院は信頼できそう」という印象を与えられます。
認知段階は、読者との最初の接点です。
ここでしっかりと興味を引き、「もっと知りたい」という気持ちを育てることが、次の理解段階へのスムーズな移行を生み出します。
理解(共感・問題意識)
認知段階を経た読者は、次に自分の課題をより深く理解し、「これは解決しなければならない」という問題意識を持つ段階に入ります。
このステージでは、読者は具体的な解決策を探し始めており、複数の選択肢を比較検討する準備が整いつつあります。
読者の心理状態
このステージの読者は、以下のように、自分の状況や課題を明確に認識しています。
- 自分の課題を明確に認識している
- 解決策が複数あることを知り始めている
- 「本当に必要なのか」「費用対効果はあるのか」と慎重になっている
- 失敗したくないという不安を抱えている
- まだ特定の企業に決めていないが、選択肢を絞り込みたいと思っている
この段階では、「今すぐ問い合わせ」はまだ早すぎますが、認知段階よりも一歩踏み込んだアプローチが可能になります。
この段階で提供すべきコンテンツ
理解段階の読者には、課題への共感と、解決策の選択肢を示すコンテンツが有効で、読者は「この記事は自分のための記事だ」と感じ、最後まで読み進めてくれます。
また、メリットだけでなくデメリットも正直に伝えることが信頼構築につながります。
この段階で適切なコンバージョン
理解段階では、判断材料となる実践的な情報をオファーとして提示します。
- 比較検討資料(他社サービスとの違いを公平に比較)
- 選び方ガイド(自社製品に限らない選定基準)
- 事例集(成功事例だけでなく、失敗事例も)
- 診断ツール(自分に合った選択肢が分かる)
- セミナー・ウェビナーの案内
読者は「自分で判断するための材料が欲しい」と考えているため、押し売り感のない情報提供が響きます。
理解段階での成功のポイント
1. 選択肢を公平に提示する
自社サービスだけを推すのではなく、「こういう場合はA、こういう場合はB」と、読者の状況に応じた選択肢を示します。
2. 事例で具体的なイメージを持たせる
抽象的な説明だけでなく、具体的な事例を示すことで、読者は自分の状況に当てはめて考えられます。
3. よくある質問に先回りして答える
この段階の読者は多くの疑問を抱えています。「初期費用はいくら?」「契約期間の縛りは?」「途中解約できる?」といった質問に、記事内で先回りして答えることで、読者の不安を解消できます。
4. 次の行動への橋渡しをする
記事の最後で、「ここまで読んで、自分に当てはまると感じた方は、次は実際の事例を見てみましょう」と、次のステージ(信頼段階)へ自然に誘導します。
理解段階は、読者が「解決したい」という意思を固める重要なフェーズです。ここで適切な情報を提供し、共感を示すことで、読者は「この会社なら信頼できそう」という感情を持ち始めます。
信頼(比較・安心)
具体的な選択肢を比較し、最終的な決断をする前に信頼を確認する段階です。
このステージの読者は「やるべきこと」は分かっていますが、「どこに頼むか」「本当にこの会社で大丈夫か」という最後の不安を抱えています。
読者の心理状態
このステージの読者は、もはや「するかしないか」ではなく「どこにするか」を決めようとして、読者は以下の状態にあります。
- どこに頼むのが良いのか、複数の選択肢から比較検討している
- 失敗や後悔をしたくないという不安が強い
- 実績や評判を重視している
- 具体的な費用や条件を知りたがっている
- 「最後の一押し」となる決め手を探している
この段階では、「無料相談」や「無料診断」といったリスクの低いオファーが効果的になります。
ただし、それを受け入れるかどうかは、読者が「この会社なら信頼できる」と感じるかどうかにかかっています。
この段階で提供すべきコンテンツ
信頼段階の読者には、具体的な実績と、安心材料となる証拠を示すコンテンツが必要です。
特に重要なのが具体的な数字と事実です。抽象的な「多くのお客様にご満足いただいています」ではなく、「過去3年間で127件の注文住宅を設計し、お客様満足度92%を達成」と具体的に示すことで、信頼性が大きく向上します。
また、第三者の評価も強力な信頼材料になります。例えば税理士事務所であれば、「日本税理士会連合会の認定資格を保有」「地元商工会議所の推薦事務所」といった外部からの評価や、「顧問先企業の声」「導入企業一覧(許可を得たもの)」といった客観的な証拠が効果的です。
さらに、他社との違いを明確にすることも重要ですが、他社を批判するのではなく、自社の強みと特徴を際立たせる形で伝えます。
この段階で適切なコンバージョン
信頼段階では、リスクを最小化したお試しオファーが効果的です。
- 無料相談(30分〜1時間)
- 無料診断・無料見積もり
- 初回限定の特別価格
- 返金保証付きのトライアル
- サンプル・試作品の提供
この段階の読者は行動する準備ができているため、適切なオファーがあればコンバージョン率は高くなります。
信頼段階での成功のポイント
1. 実績を具体的に示す
「豊富な実績」という曖昧な表現ではなく、数字で示します。
2. 顧客の声を掲載する
実際に利用した顧客の生の声は、どんな宣伝文句よりも説得力があります。具体的な成功体験やエピソードを、顧客の言葉で語ってもらうことで、リアリティが増します。
3. 透明性を示す
料金体系、契約条件、解約規定など、読者が気になる情報を隠さずオープンにします。特に、デメリットや制約事項も正直に伝えることが重要です。
4. 安心材料を重ねる
契約前に読者の感じる不安を一つ一つ解消していきます。リフォーム会社であれば、以下のような安心材料を提示します。
- 建設業許可番号の明示
- 損害保険の加入証明
- アフターサービスの内容(10年保証など)
- 施工中のトラブル対応体制
- 過去のクレーム対応事例
これらを積み重ねることで、読者は「この会社なら安心して任せられる」と感じます。
5. 最後の一押しを用意する
信頼段階の読者は、あと一歩で決断できる状態です。その背中を押すのが、期限付きのオファーや限定性です。
ただし、過度な煽りは逆効果になるため、あくまで読者にとって価値のあるオファーであることが前提です。
6. 次のステップを明確にする
読者が「相談してみよう」と思ったとき、次に何をすればいいかが明確でないと離脱します。
「無料相談のお申し込みは、このフォームから30秒で完了します」「お電話でのご相談は平日9時〜18時まで受付中」と、具体的な行動手順を示すことで、スムーズに次のステージへ進めます。
信頼段階は、読者が最終的な決断を下す直前の重要なフェーズです。ここで十分な信頼材料と安心感を提供できれば、読者は自信を持って次の行動段階へ進みます。
次のステージでは、読者が実際に申し込みや相談という具体的な行動を起こす段階について解説します。
行動(申込・相談)
このステージの読者は「この会社に相談してみよう」「申し込んでみよう」という決断をほぼ固めていますが、最後の最後で躊躇や不安が生じ、離脱する可能性も残っています。
読者の心理状態
すでに「相談したい」「購入してもいい」という気持ちを持っていますが、フォームを前にして「本当に今申し込んでいいのか」「しつこく営業されないか」「本当にこれでいいのか?」といった細かい不安が頭をよぎっています。
- 行動する意思は固まっているが、最後の不安がある
- 入力や手続きが面倒だと感じると離脱する
- プライバシーや個人情報の扱いを気にしている
- 「本当にこれで合っているか」という確認を求めている
- 申し込み後に何が起こるのか不安を感じている
この段階で離脱されることは、最も大きな機会損失です。ここまで来た読者を確実にコンバージョンへ導くための最後の配慮が必要です。
この段階で提供すべき要素
行動段階では、読者がストレスなくスムーズに行動を完了できる環境を整えます。
1. 入力フォームの最適化
フォームの入力項目は必要最小限に絞ります。各入力欄には入力例を表示して迷いなく入力できるようにします。
2. 安心感を与えるメッセージ
フォームの近くに、読者の不安を解消するメッセージを配置します。
- 「個人情報は厳重に管理し、第三者に提供することは一切ありません」
- 「しつこい営業電話は一切いたしません」
- 「ご予約後、24時間以内に確認のメールをお送りします」
- 「キャンセルや日程変更も前日まで無料で承ります」
これらの文言があるだけで、読者は「安心して申し込める」と感じます。
3. 申し込み後の流れを明示
読者は「申し込んだ後に何が起こるのか」を知りたがっています。申し込み後の流れを簡単に解説しておけば、安心して入力フォームに記入できますし、見通しを持って行動できます。
4. 複数の連絡手段を用意
フォーム入力が苦手な読者もいます。特に高齢者や、急ぎの相談がある人向けに、電話での問い合わせも併記しましょう。このような配慮があるだけで、幅広い層の読者を取りこぼしません。
最後の障壁を取り除く
読者が「相談フォーム」まで辿り着いたなら、その読者は複数の記事を読み、サービス内容を理解し、他社と比較し、信頼を感じているはずです。この読者を、「フォームが使いにくい」「入力項目が多すぎる」といった些細な理由で逃すのは、あまりにももったいないことです。
行動段階では、読者の立場に立って、「何が不安か」「何が面倒か」「何が分かりにくいか」を徹底的に洗い出し、一つ一つの障壁を取り除くことが重要です。
アクセスがあるのに問い合わせがない原因を無料で診断しませんか?
ナーチャリングで”本命コンバージョン”へ育てる

オウンドメディア上でメルマガ登録や資料ダウンロードといったマイクロコンバージョンを獲得できたとしても、それだけでは売上にはつながりません。
マイクロコンバージョンによって獲得した「リード」を、本命コンバージョンへと段階的にステップアップする為に「ナーチャリング(顧客育成)」を行ないます。
コンバージョンを育てるナーチャリングの流れ
ナーチャリングは基本的に次の3ステップで進めます。
オウンドメディアの記事を読んだ訪問者に対して、メルマガ登録や資料ダウンロードといったマイクロコンバージョンを設置します。
ステップメールによって、「知る→理解する→信頼する→相談したくなる」という流れを自動的に作り出し、見込み客の心理ステージを引上げます。
たとえば、5通のステップメールで次のような内容を配信します。
- 1通目:登録のお礼と約束の資料
- 2通目:よくある課題や失敗事例の共有(共感)
- 3通目:解決の具体的な方法論の提示(理解)
- 4通目:実際の成功事例やお客様の声(信頼)
- 5通目:無料相談への自然な誘導(行動)
ステップメールで信頼関係が構築できたら、本命コンバージョンである「問い合わせ」や「相談申し込み」へと誘導します。段階的に情報を提供してきたことで、見込み客は「この会社なら信頼できる」という確信を持った状態で相談に進めます。
ステップメール配信で本命コンバージョンし無かった場合も、月1〜2回のメルマガで接点を維持し続けることで、「いつか相談するならここ」という候補として記憶に残り続けます。
ナーチャリングは「自動の仕組み」で機能させる
ナーチャリングの最大の利点は、一度設計すれば自動で機能する点です。
ステップメールは24時間365日、人手をかけずに見込み客を育成し続けます。営業担当が一人ひとりにフォローの電話をかける必要はありません。
オウンドメディアとメールを組み合わせた仕組みが、継続的にコンバージョンを生み出してくれます。
属人的な営業フォローに依存せず、仕組みで自動的にコンバージョンを生み出す。これがBlue Aegisが考える、オウンドメディア集客による成果の仕組みの本質です。
コンバージョンを増やすための計測と改善
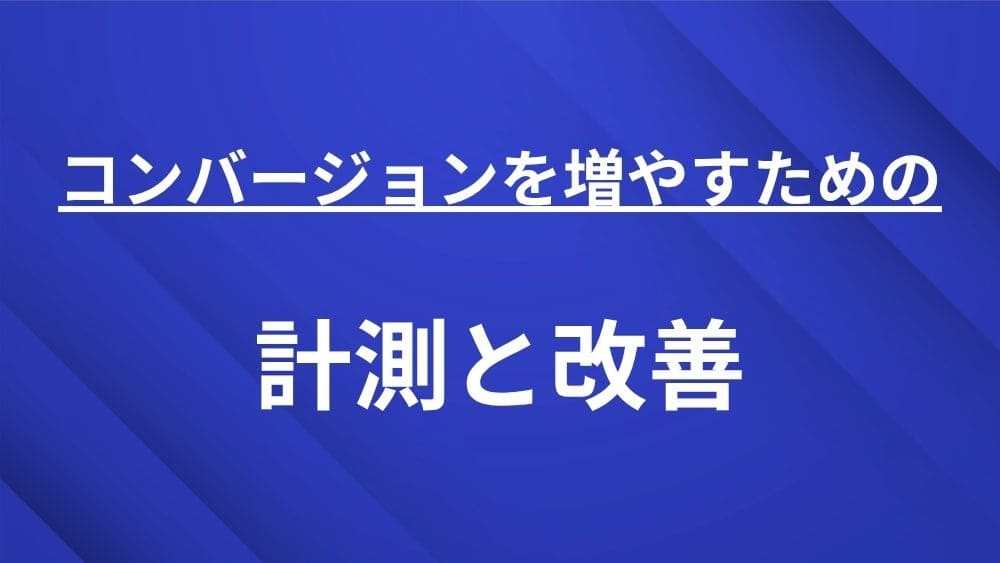
オウンドメディアでコンバージョン(マイクロコンバージョン含む)を獲得する仕組みを作っても、「どこで見込み客が離脱しているのか」を把握し、継続的に改善しなければ成果は伸びません。
このセクションでは、オウンドメディアのコンバージョン改善に必要な指標と、それぞれの改善方法を解説します。
確認するべき指標
オウンドメディアのコンバージョンを改善するには、まず現状を正しく把握することが必要です。コンバージョンまでの流れを次の3つの指標に分解して計測します。
- PV(ページビュー):記事にどれだけ人が来ているか
そもそも記事を読む人が少なければ、コンバージョンは発生しません。まずは記事への訪問数を確認します。 - CTAクリック率:記事を読んだ人の何%がCTAをクリックしているか
記事を読んだ人のうち、メルマガ登録や資料ダウンロードといった次のアクションに進んだ人の割合です。記事が100PVあってCTAクリックが3回なら、CTAクリック率は3%です。 - 3. フォーム送信率:フォームを開いた人の何%が送信完了しているか
CTAをクリックしてフォームまで来た人のうち、実際に送信ボタンを押して完了した人の割合です。フォームを開いた人が10人いて、送信完了が5人なら、フォーム送信率は50%です。
この3つの指標を見れば、どこに問題があるかが一目で分かります。たとえばPVが十分あるのにCTAクリック率が1%未満なら、記事の内容やCTAの設計に問題があります。
CTAクリック率は3〜5%へ到達できるように改善します。
CTAクリック率は良いのにフォーム送信率が低いなら、フォームの入力項目が多すぎるか、分かりにくい可能性があります。フォーム送信率は50%以上を目指しましょう。
月次レビューで改善サイクルを回す
指標を確認するだけでは、オウンドメディアのコンバージョンは改善しません。重要なのは、定期的に数値を見て、改善策を実施し、その効果を検証するサイクルを回し続けることです。
- 月に1回のレビュー習慣を作る
まずは月に1回、30分でも良いので、3つの指標を確認する時間を確保しましょう。「数値が悪くなったら見る」ではなく、「毎月第1月曜日の午前中」のように、定期的にレビューする仕組みを作ります。 - 数値から仮説を立てる
数値を見たら、「なぜこの数値なのか」を考えます。
- CTAクリック率が1%と低い→記事を読んでも行動したくならない?CTAが目立たない?
- フォーム送信率が30%と低い→入力項目が多すぎる?入力例が分かりにくい?
- PVは多いのにCTAクリックが少ない→記事内容とCTAのオファーがミスマッチ?
このように、数値から「何が原因か」の仮説を立てます。
- 改善策を実施して効果を検証する
仮説が立ったら、改善策を実施します。たとえば「CTAが目立たないのでは?」という仮説なら、CTAの色を変更したり、記事の中盤にもCTAを追加したりします。
そして1ヶ月後、再び数値を確認します。CTAクリック率が1%から3%に上がっていれば、改善策が効いた証拠です。変化がなければ、別の仮説を立てて再度施策を試します。 - 小さく始めて継続する
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは「月1回、数値を見る」という習慣を作ることから始めましょう。慣れてきたら、ABテストで複数のパターンを試したり、ヒートマップで細かく分析したりと、徐々にレベルを上げていけば良いのです。
重要なのは、一度きりの改善ではなく、継続的にサイクルを回すことです。月次レビューを仕組み化することで、オウンドメディアは「作って終わり」ではなく、毎月少しずつ成長し続ける資産になります。
まとめ
オウンドメディアでコンバージョンを獲得するには、記事で集客し、CTAで次のアクションに誘導し、ナーチャリングで段階的に育成する流れを作ります。そして計測と改善を継続することで、成果は着実に向上します。
重要なのは、属人的な営業に頼るのではなく、「仕組み」として設計することです。一度構築すれば、オウンドメディアは24時間365日、自動的にコンバージョンを生み出し続けます。
完璧を目指す必要はありません。まずは既存記事にCTAを追加し、メルマガ登録を設置し、月1回の数値確認から始めましょう。
その小さな一歩の積み重ねが、オウンドメディアを成長し続ける資産に変えていきます。
関連記事:中小企業のオウンドメディア集客戦略ガイド
アクセスはあるのに問い合わせが来ない
その原因、3分で見つけませんか?
アクセスはあるのに、問い合わせが増えない原因の多くは、「導線の欠陥」や「心理段階に合っていないCTA設計」にあります。Blue Aegisでは、御社のオウンドメディアを実際に拝見し、
・どの部分で読者が離脱しているのか
・どんなCTAや記事構成がCVを妨げているのか
・どうすれば“問い合わせが発生し続ける導線”に変えられるか
を無料で診断・レポートします。
今の集客方法の“どこを変えれば成果が出るのか”、診断で明確にしませんか?
アクセスはあるのに問い合わせが来ない
その原因、3分で見つけませんか?
アクセスはあるのに、問い合わせが増えない原因の多くは、「導線の欠陥」や「心理段階に合っていないCTA設計」にあります。Blue Aegisでは、御社のオウンドメディアを実際に拝見し、
・どの部分で読者が離脱しているのか
・どんなCTAや記事構成がCVを妨げているのか
・どうすれば“問い合わせが発生し続ける導線”に変えられるか
を無料で診断・レポートします。
今の集客方法の“どこを変えれば成果が出るか”、診断で明確にしませんか?