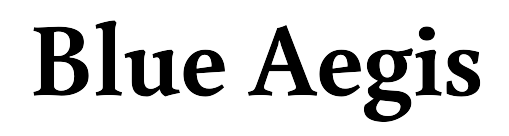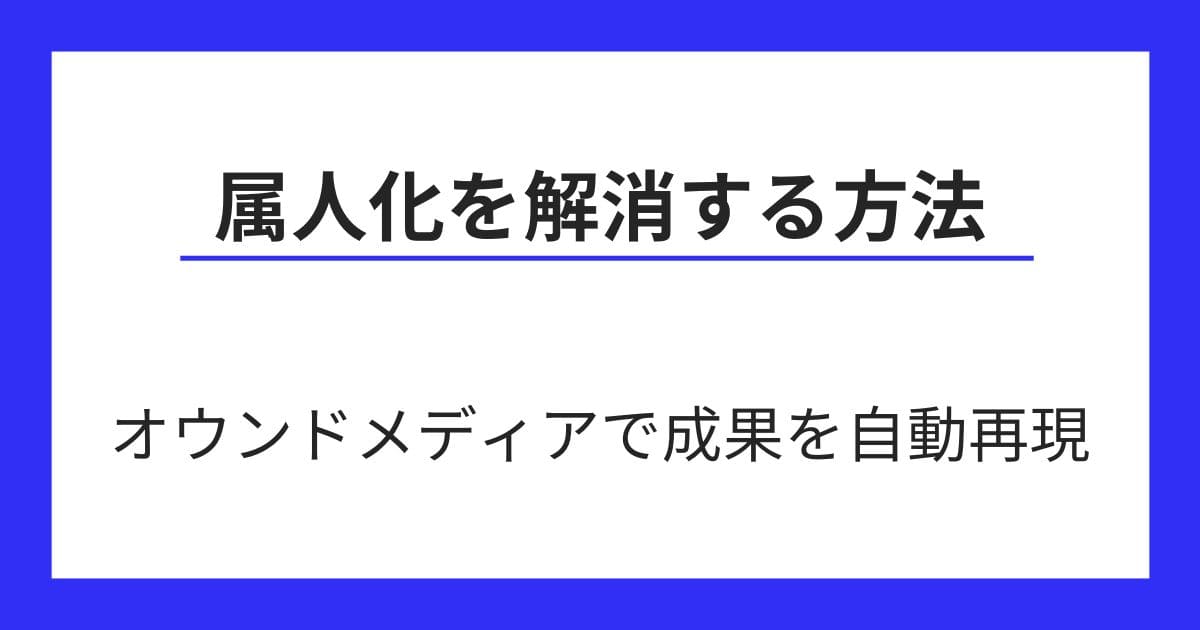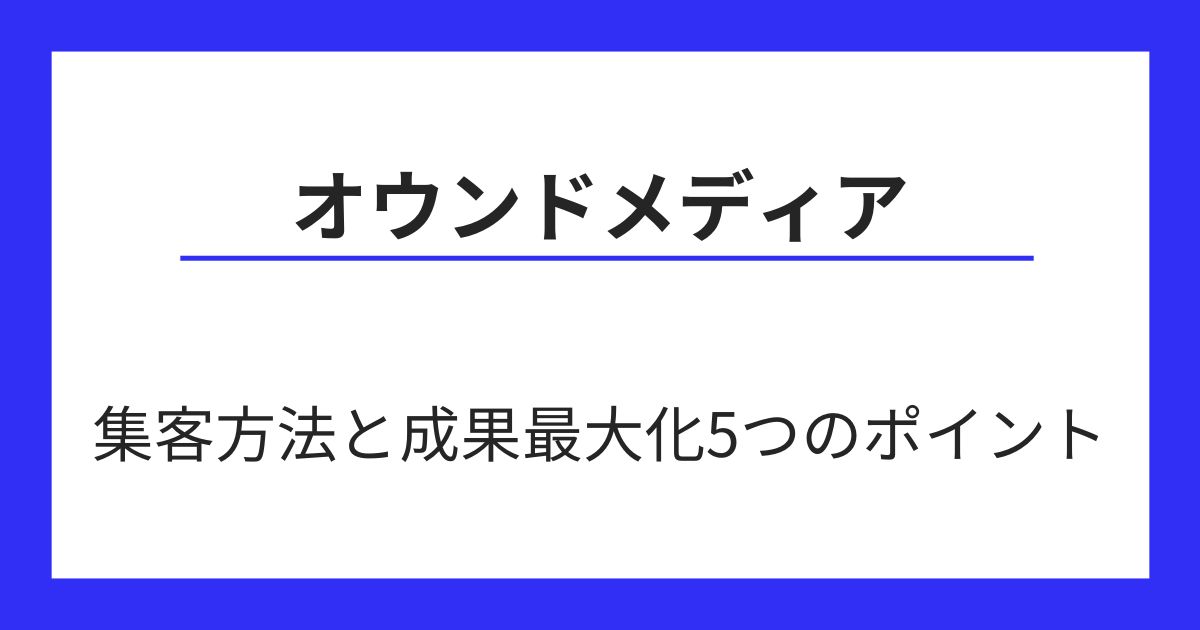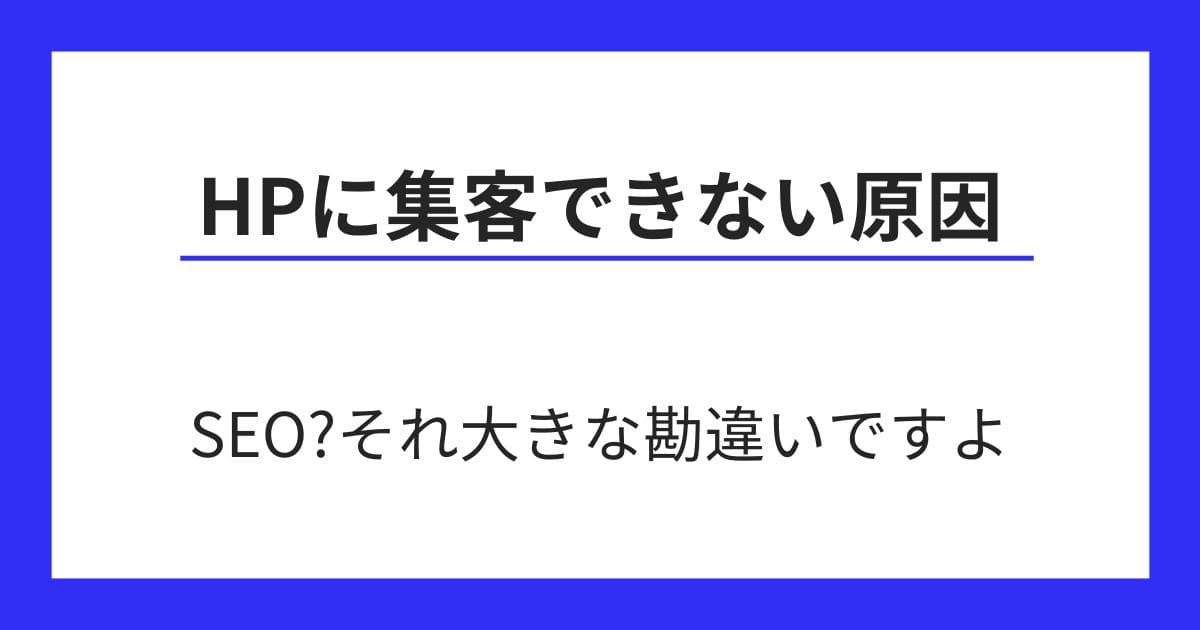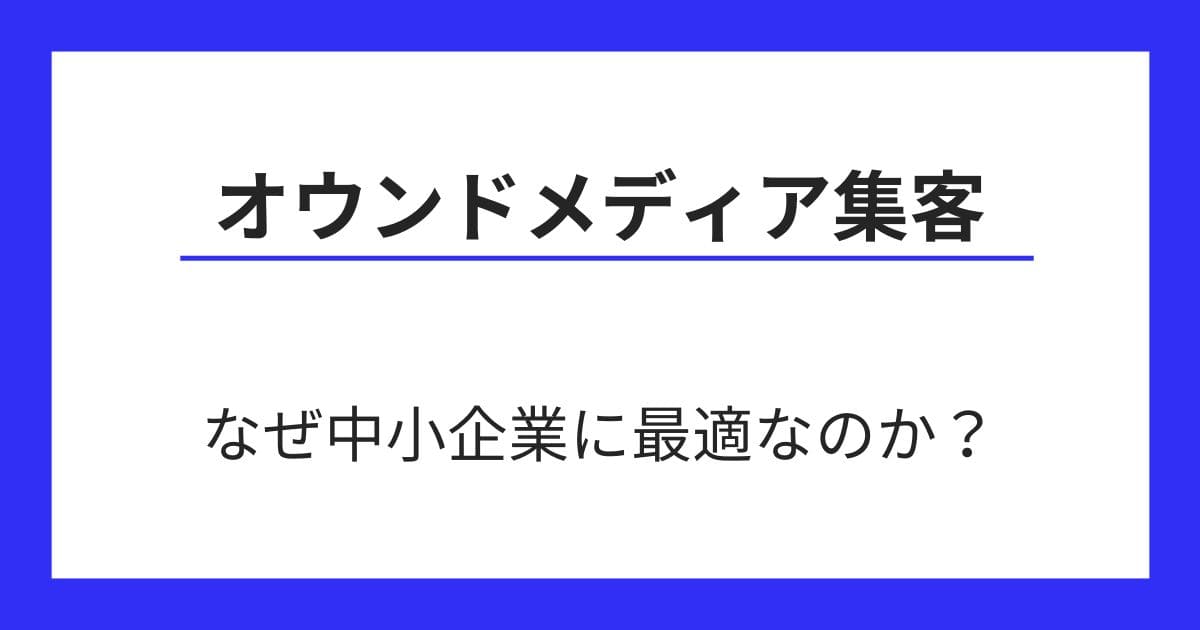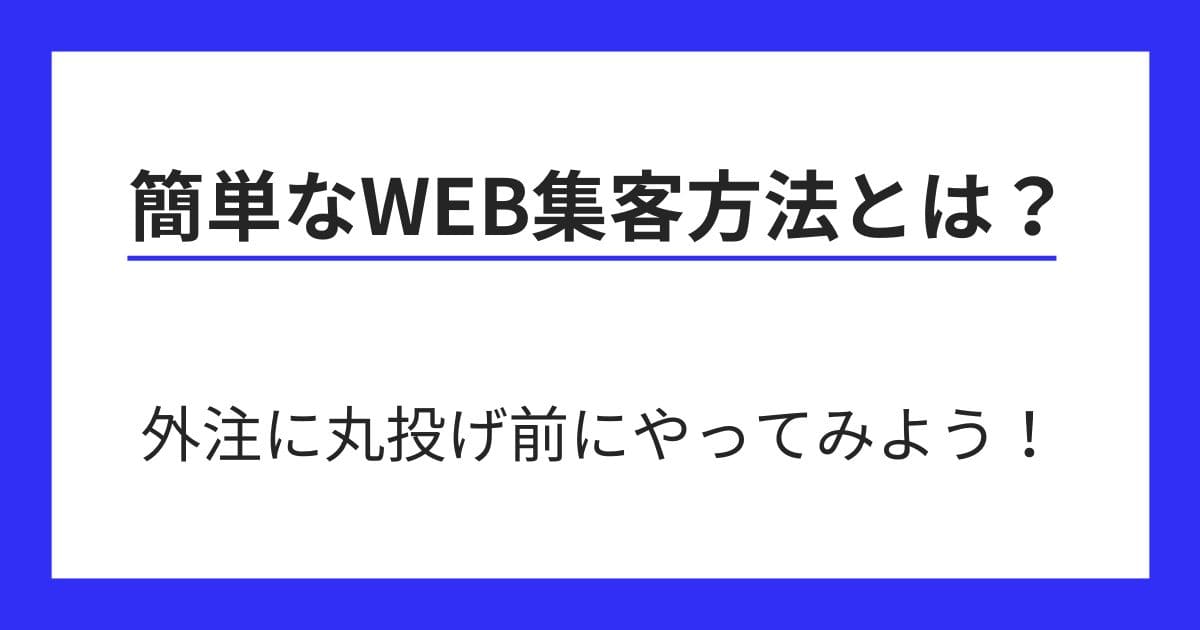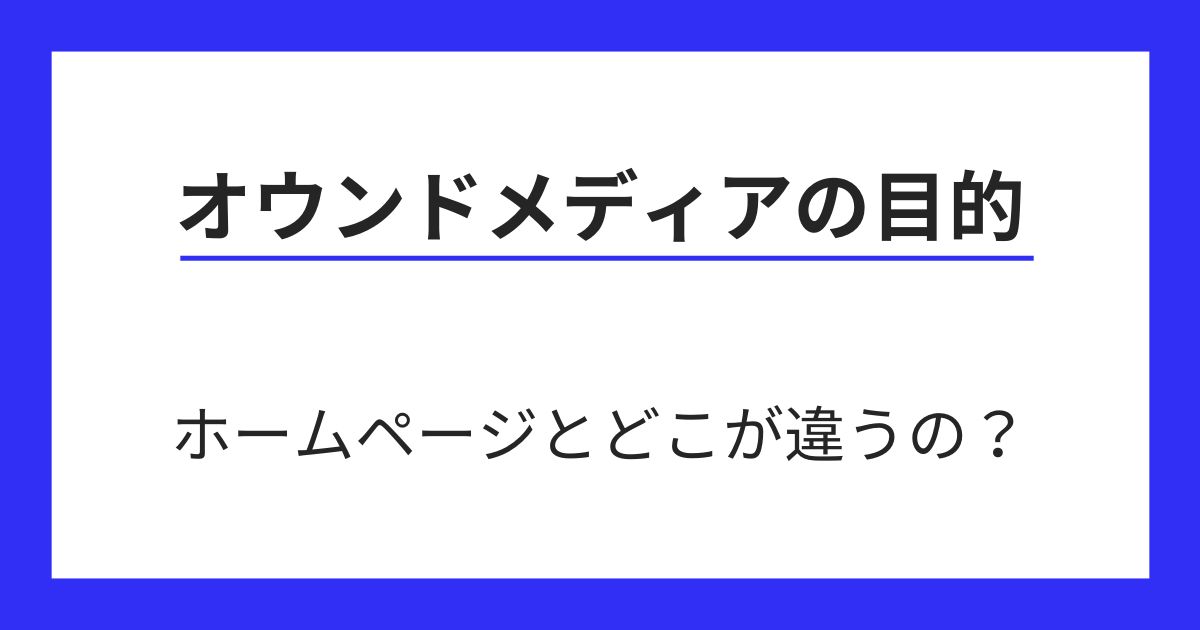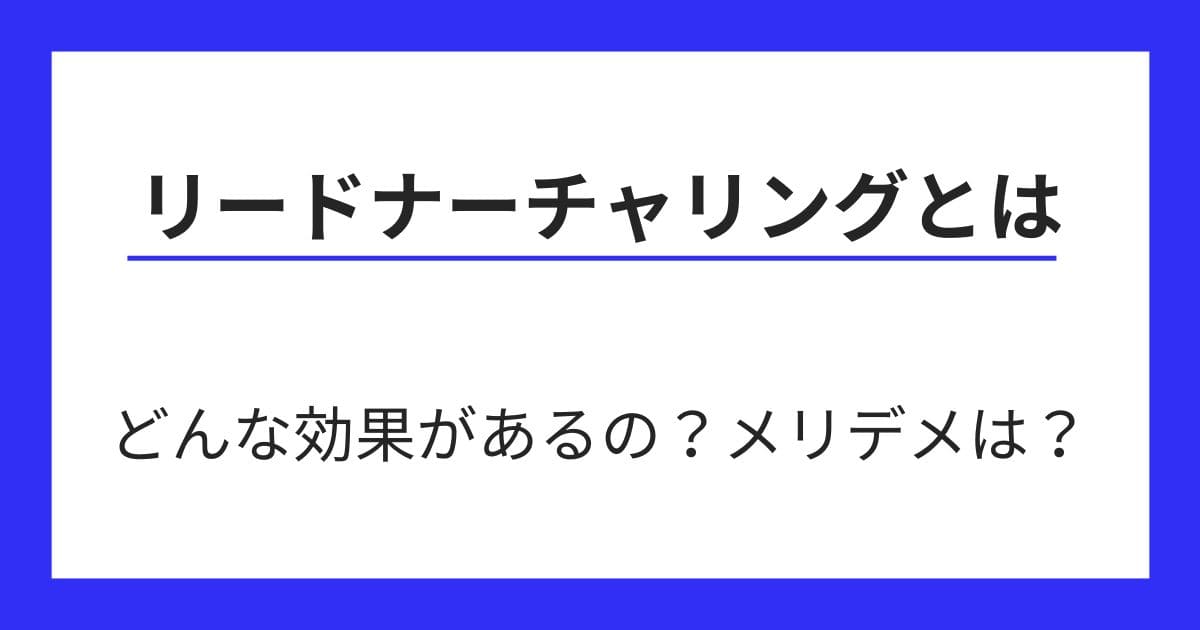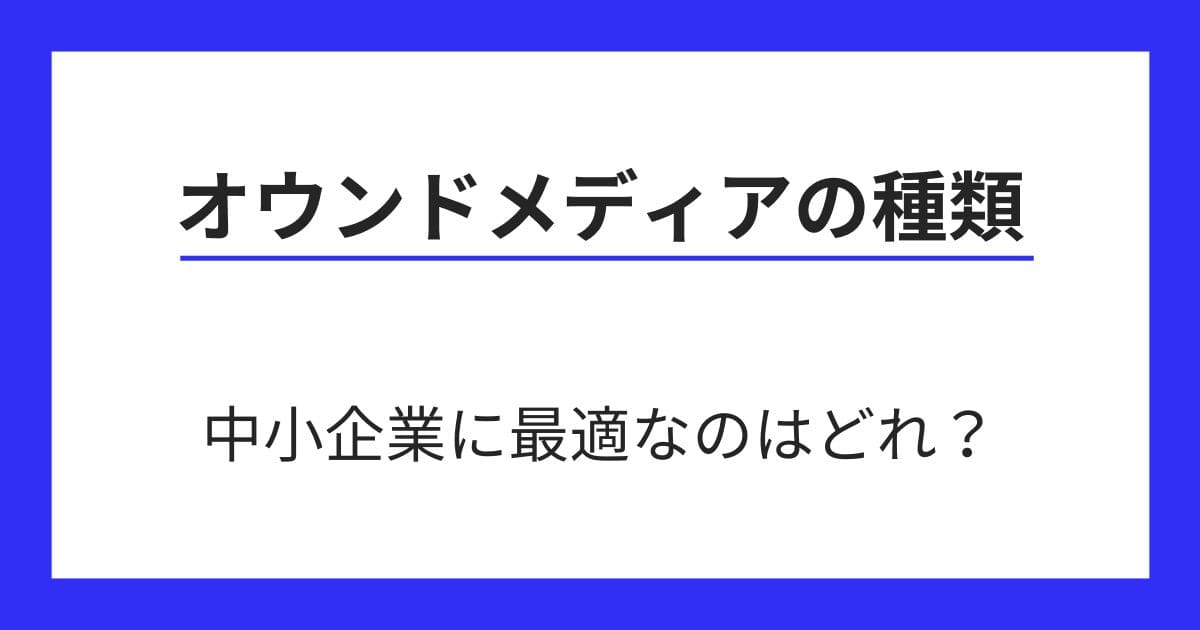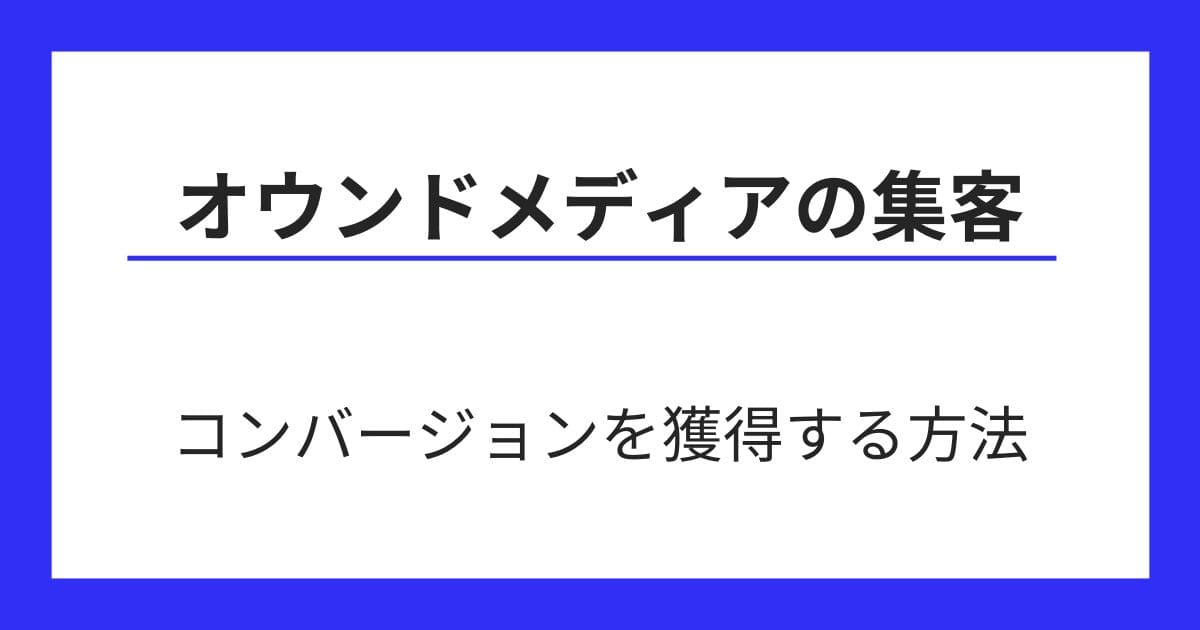営業の属人化は、多くの中小企業が抱える深刻な課題です。
成果が特定の人に依存し、担当者が変わると売上が不安定になる——この状態を放置すれば、会社の成長は止まります。
しかし、属人化は個人の能力の問題ではありません。営業が仕組み化されていない構造の問題です。
この記事では、営業の属人化が起こる根本原因と、オウンドメディアを活用して属人化を解消し、誰が担当しても成果が出る仕組みを作る方法を解説します。
属人化に悩む経営者の方、営業を安定させたい方は、ぜひ最後までお読みください。
【結論】営業の属人化を解消する方法
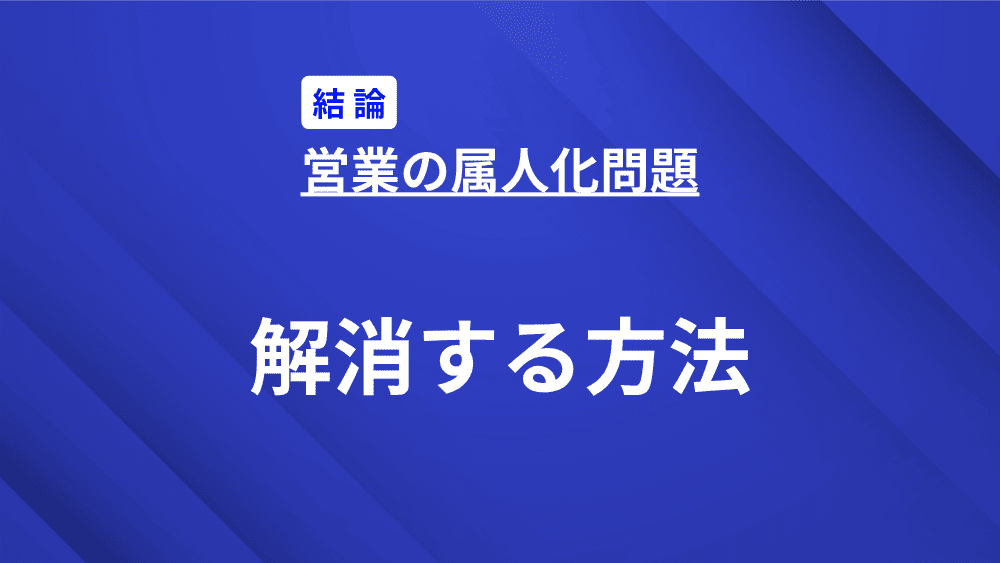
営業成果が特定の人に依存する状態は、情報・スキル・顧客接点が個人に閉じているからです。
営業の属人化を解消する方法には、以下のようなものがあります。
- 営業マニュアルやナレッジベースを整備する
- CRM/SFAツールを導入し、営業活動を可視化する
- 営業研修やOJTを強化し、スキルを標準化する
- オウンドメディアで営業を仕組み化する
中でも最も効果的なのが、“オウンドメディアによって営業を仕組み化すること”です。
営業時の情報やノウハウを記事として資産化し、見込み客教育を自動化することで、24時間稼働する営業装置として機能します。
再現性を持った仕組みを作ることで、誰が担当しても成果が出る構造を実現できます。
なぜ営業は属人化してしまうのか
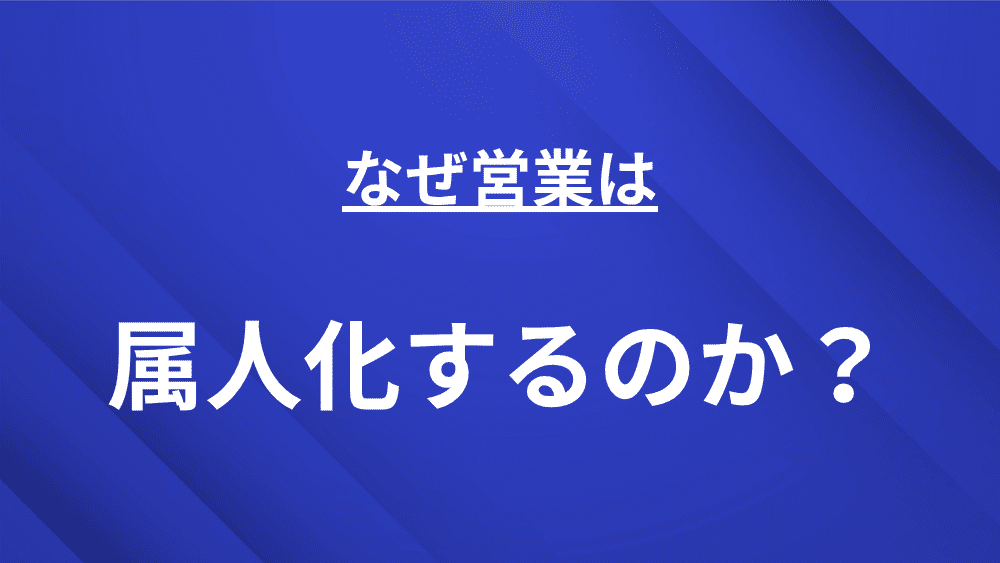
営業の属人化は、偶然起こるものではありません。その根本には、情報・判断・顧客接点が「個人に閉じた構造」になっているという、明確な原因があります。
多くの中小企業では、営業活動が個人の経験や勘に依存し、組織として成果を再現できる仕組みが整っていません。結果として、「あの人がいないと回らない」「担当者が変わると売上が落ちる」という状況が生まれてしまうのです。
ここでは、なぜ営業が属人化してしまうのか、その構造的な原因を具体的に見ていきましょう。
成果が個人スキルに依存している
営業成果が、担当者個人のスキル・経験・感覚的判断に大きく左右される状態。これが属人化の最も大きな要因です。
「この商品の良さをどう伝えるか」
「顧客の悩みにどう寄り添うか」
「クロージングのタイミングをどう見極めるか」
——こうした営業プロセスの全てが、担当者の頭の中にしかない状態になっていませんか?
実際、多くの中小企業では、トップセールスのやり方を他の営業担当が再現できず、「なぜあの人は売れるのか分からない」という状況が起きています。
スキルが言語化・共有されていないため、成功パターンが組織に蓄積されないのです。
結果として、担当者が休んだり退職したりすると、途端に営業成果が落ちてしまいます。これは個人の能力の問題ではなく、仕組みがない構造の問題なのです。
ノウハウ共有の仕組みがない
営業で得た成功パターンや失注理由が共有されず、個人の経験として消えていく——この状態が、属人化をさらに加速させます。
例えば、ある営業担当が「このタイミングでこの資料を見せると、顧客の反応が良い」というノウハウを持っていても、それが他のメンバーに伝わらなければ、組織全体の営業力は上がりません。
また、失注した案件から得られる教訓も、個人の記憶に留まるだけで終わってしまいがちです。「なぜ失注したのか」「次はどう改善すればいいのか」といった学習サイクルが、組織全体で回っていないのです。
ノウハウが共有されない背景には、
「忙しくて共有する時間がない」
「共有する文化がない」
「そもそも何を共有すればいいか分からない」
といった、さまざまな要因があります。
しかし、どんな理由であれ、知見が個人で終わってしまえば、組織としての成長は止まります。
見込み客との接点が個人に依存
新規顧客との出会い方も、属人化の大きな要因です。
多くの中小企業では、紹介・訪問営業・展示会・人脈といった、個人の人間関係に依存した営業チャネルが中心になっています。
これらは即効性がある一方で、担当者が変われば接点が途切れるという脆弱性を持っています。
例えば、あるベテラン営業担当が長年培ってきた人脈から継続的に案件を獲得していたとしても、その人が退職すれば、その人脈は会社に残りません。
また、紹介営業も「紹介してもらえる関係性」を維持できるかは、担当者個人の力量次第です。
一方で、企業として見込み客と出会える仕組み——例えば、検索エンジンやSNS、広告、そしてオウンドメディアといった「誰が担当でも機能する接点」を持っている企業は、属人化のリスクが圧倒的に低くなります。
営業チャネルが個人に依存している限り、「会社としての集客力」は育ちません。見込み客との接点を、組織の資産として体系化することが、属人化解消の第一歩となるのです。
営業の属人化を防ぐために必要な5つのこと

営業の属人化を防ぐには、個人の勘や経験に頼らず、組織として「再現可能な営業構造」を作ることが欠かせません。
そのためには、知識・行動・判断を共有・可視化・循環させる環境を整え、“仕組みが動いて成果を生み出す状態”を目指す必要があります。
ここでは、属人化を防ぐために必要な5つの要素を見ていきましょう。
1.ナレッジを共有する文化を作る
営業で得た知見や成功事例を、チーム全体で共有できる環境を整える。
これが、属人化解消の第一歩です。
【実行内容】
具体的には、営業担当が日々の活動で得た気づきや成功パターンを、定期的にチーム内で報告・共有する習慣を作ります。例えば、週1回のミーティングで「今週うまくいった提案」「顧客からよく聞かれた質問」を共有するだけでも、大きな効果があります。
【仕組み】
共有した情報は、その場限りで終わらせず、ドキュメントやナレッジベースに蓄積していきます。Notionやスプレッドシートなど、シンプルなツールで十分です。重要なのは「探せば見つかる」状態にしておくことです。
【効果】
こうした文化が根付くと、「あの人しか分からない」という状態がなくなります。新人でもベテランの知見を参照でき、チーム全体の営業力が底上げされます。日常的に共有・更新される文化こそが、属人化を防ぐ土台となるのです。
2.営業活動を見える化する
営業活動の進捗・対応履歴を可視化し、誰が見ても状況を把握できる状態にすることで、属人的判断を減らし、再現性ある営業を実現できます。
【実行内容】
顧客ごとの商談履歴、やり取りの内容、提案した資料、次のアクション等を記録し、チーム全体が見れる、探せる形で管理します。Googleスプレッドシートやエクセルでも構いませんが、できればCRMツールを使う事で、より効率的に管理できます。
【仕組み】
見える化のポイントは、「誰が見ても次に何をすべきか分かる」状態を作ることです。例えば、「見積もり提出済み・返答待ち」「追加資料の送付が必要」といったステータスを明確にしておくだけで、担当者不在でも他のメンバーがフォローできます。
【効果】
活動が可視化されると、「この顧客にはどんなアプローチが効いたのか」「どのタイミングで失注しやすいのか」といったパターンが見えてきます。これにより属人的判断を減らし、データに基づいた営業が可能になります。
3.チームで回せる体制を整える
営業を個人ではなくチームで管理・改善できるようにすることで、担当者が変わっても成果を継続できる体制を構築します。
【実行内容】
営業活動を「誰か一人に任せる」のではなく、チーム全体で管理する体制を作ります。例えば、案件の進捗確認を週次で行う、商談のフィードバックをチームで共有する、といった運用です。
【仕組み】
役割分担も重要です。営業担当だけでなく、資料作成をサポートする人、顧客フォローを担当する人など、役割を分けることで、一人に負荷が集中するのを防ぎます。また、定期的な振り返りミーティングを設けることで、チーム全体で改善策を考える文化が育ちます。
【効果】
チームで回せる体制が整うと、担当者が休んでも、退職しても、営業活動が止まりません。「あの人がいないと困る」という状況から脱却でき、安定した営業成果を維持できるようになります。
4.教育・育成を継続できる環境を作る
経験者の知見を若手に伝え、教育を仕組みとして継続することは、属人化を防ぎ、営業品質を保つ鍵となります。
新人が入社したときに、営業のやり方を一から教える必要がある状態は、知識が体系化されていない証拠です。
【実行内容】
営業トークのテンプレート、提案資料のひな形、よくある質問への回答集など、教育に使える資料を用意しておきましょう。
【仕組み】
継続的な育成環境を作るには、OJT(現場での指導)だけでなく、「学べる教材」を整えることが重要です。例えば、過去の成功事例を動画で残しておく、ロールプレイングの機会を定期的に設けるなど、学びの機会を組織として提供します。
【効果】
教育が仕組み化されると、新人が一人前になるまでの時間が短縮され、営業力が安定します。また、ベテラン社員も「自分の知識を伝える」ことで、改めて営業プロセスを整理でき、さらなる成長に繋がります。継続的な学びの循環こそ、属人化を防ぎ、営業品質を保つ鍵となるのです。
5.自動で成果を生み出す構造を描く(”仕組み化”の原点)
営業活動を「人が繰り返す」形ではなく、コンテンツ・データ・ツールが連動し、自動で成果を生み出す構造に設計する。
これが、真の仕組み化です。ここまで紹介した「共有・可視化・体制・教育」は、全て人が主体となって行う活動です。
しかし、それらを結びつけ、「人がいなくても動く仕組み」に昇華させることで、初めて属人化から完全に脱却できます。
【仕組み】
例えば、営業で話している内容をコンテンツ化し、Webサイトやメール、資料として顧客に自動で届ける。顧客の反応をデータで記録し、次にどんなアプローチをすべきかを自動で判断する。こうした仕組みを作ることで、営業活動の多くを自動化できます。
【効果】
共有・可視化・体制・教育といった要素を統合し、“仕組みが動いて成果が出る状態”を実現すると、営業担当者は「仕組みでは対応できない、本当に重要な顧客対応」に集中できるようになります。
これこそが、営業の生産性を最大化し、属人化を超える唯一の方法なのです。
オウンドメディアによる”営業の属人化”の解消方法
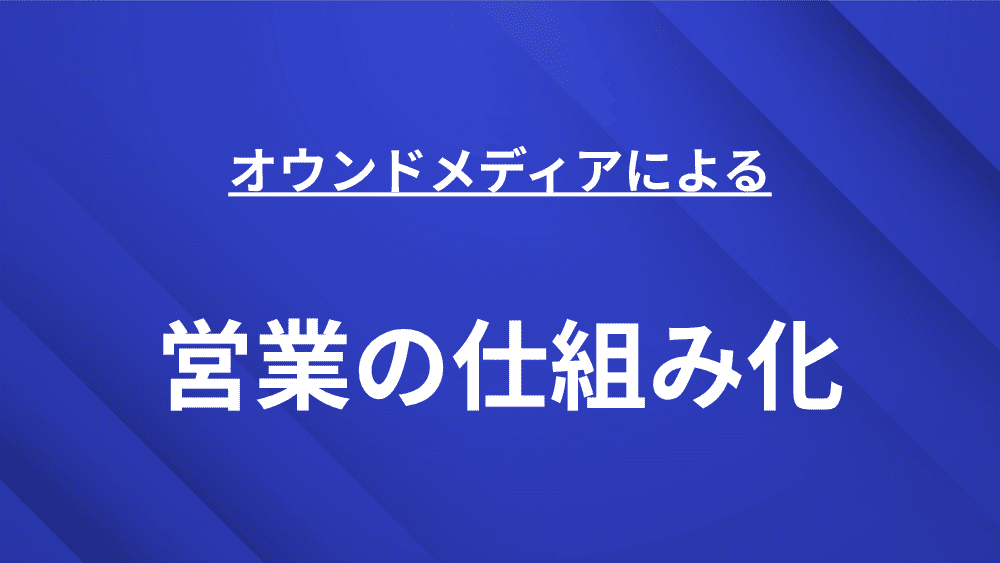
この章では、属人化を防ぐ”実践手段”としてのオウンドメディアを解説します。
オウンドメディアは、これまで営業として人が行ってきた説明・教育・提案をコンテンツ化し、顧客接点を自動化することで、営業の再現性を実現する“自動営業システム”となります。
ここでは、具体的にどのようにオウンドメディアが属人化を解消するのかを確認します。
営業ノウハウを「コンテンツ化」し、誰でも発信できる形にする
営業担当者の経験や顧客対応ノウハウを、記事・動画・資料として体系化し、組織全体で再利用できる形にするのが、オウンドメディアの第一の役割です。
例えば、トップセールスが「お客様からよく聞かれる質問」「導入前に不安に思うこと」「導入後にどんな成果が出るのか」といった情報をや、商談でよく話している内容をブログの記事やFAQページにまとめます。
すると、新人の営業担当でも「この記事を読んでもらえば、基本的な疑問は解消してもらえる」という状態を作れます。営業トークを一から覚える必要がなく、記事を共有するだけで、ある程度の説明が完了します。
また、提案資料や事例紹介もコンテンツ化することで、「あの人が作った資料じゃないと伝わらない」という状況を防げるようになります。
誰でも同じ品質の情報を発信できるようになり、営業品質・提案品質を均一化することができます。
さらに、コンテンツは一度作れば何度でも使えます。
個人の頭の中にしかなかった知識が、会社の資産として蓄積され続ける、これこそが、オウンドメディアによる属人化解消の本質です。
見込み客教育を自動化し、営業前に信頼関係を構築する
従来の営業では、「商品説明→課題のヒアリング→提案→クロージング」という流れを、営業担当者が一から行う必要がありました。しかし、この多くの部分は、実はコンテンツで代替できます。
オウンドメディアに記事を用意しておくことで、見込み客は営業と話す前に、自分のペースで情報を学び、理解を深められます。
「この商品はどんな課題を解決するのか」
「導入するとどんな成果が出るのか」
「導入の流れはどうなっているのか」
こうした情報を記事で提供することで、営業前にある程度の理解と信頼を形成できます。
さらに、この仕組みをより効果的にする方法があります。それが、MA(マーケティングオートメーション)という仕組みです。
MAは、顧客の行動に応じて自動でメールを送ったり、適切なタイミングで情報を届けたりするツールです。
例えば、見込み客がWebサイトで資料をダウンロードしたとします。その後、MAを使って以下のように段階的に情報を配信します。
- 1日後:「導入事例を紹介する記事」をメールで送る
- 3日後:「よくある質問に答える記事」を送る
- 7日後:「導入ステップを解説する記事」を送る
すると、見込み客は営業と話す頃には、すでに「この会社は信頼できそうだ」「この商品は自社に合いそうだ」という状態ができているのです。
この仕組みを作ることで、営業前の信頼形成を自動化でき、属人的な”説明力”を超える成果を再現できます。
営業担当は、より精度の高い提案づくりや深い相談に集中できるようになり、営業効率も大幅に向上します。
メディアが”営業マン”として顧客を動かす
オウンドメディアは、営業が行っていた説明・提案・クロージングを代替する、24時間稼働する営業支援装置です。
例えば、外壁塗装業を営んでいる会社が「外壁塗装 費用 相場」という記事を書いていたとします。
ある住宅オーナーが休日の夜にスマホでその記事を見つけ、「この会社は価格の内訳まで詳しく説明している」「誠実そうだ」と感じて問い合わせをする。
これが、メディアが営業として機能している状態です。
営業担当が寝ている時間でも、休日でも、オウンドメディアは働き続けます。記事を読んだ見込み客は、自分で情報を集め、比較し、納得してから問い合わせをしてくるため、商談の質も高くなります。
また、記事の中に「導入の流れ」や「よくある失敗例」を書いておくことで、見込み客の不安を事前に解消できます。
これは営業担当が口頭で説明する以上に、冷静で客観的な情報として受け取られやすく、信頼構築に効果的です。
つまり、オウンドメディアは単なる情報発信の場ではなく、営業不在でも「伝わる・納得・行動」を実現する、自動営業装置なのです。
顧客行動データを一元管理し、営業判断を再現可能にする
オウンドメディアをCRM(顧客管理システム:顧客情報や商談履歴を一元管理するツール)やMA(マーケティングオートメーション)と連携させることで、顧客の閲覧履歴や反応データを統合管理できます。
例えば、CRM上のある見込み客のデータに、以下のような内容の記録ができたとします。
「料金ページを3回見ている」
「導入事例の記事を熱心に読んでいる」
「問い合わせフォームを開いたが送信していない」
こうした行動データが記録されていれば、
「この見込み客は料金に関心がある」
「導入イメージを具体化したいのだろう」
「問い合わせ直前まで来ているが、何か不安がありそうだ」
と判断できます。
このように、「どのタイミングで、どんなアプローチをすべきか」という営業判断が、勘ではなくデータや記録に基づいて行えるようになります。
この客観的事実に基づく判断が出来るようになると、誰が見ても同じ判断ができるため、属人的な営業スキルに依存する必要がなくなるのです。
また、過去のデータを分析することで、「この行動パターンの見込み客は成約率が高い」「このページを見た人は失注しやすい」といった傾向も見えてきます。こうした知見を営業活動に活かすことで、組織全体の営業力が向上し、成果の再現性が高まります。
オウンドメディアは単なる情報発信ツールではなく、顧客の行動を可視化し、営業活動を最適化するデータ基盤としても機能するのです。
営業の属人化を解消するオウンドメディア設計の3ステップ
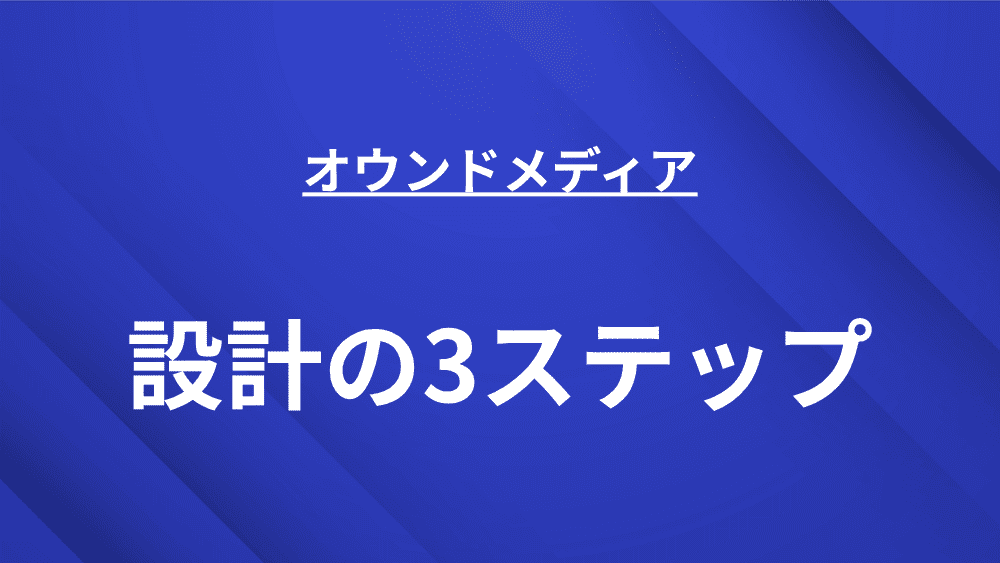
営業属人化を防ぐオウンドメディアの構築は、「可視化→資産化→連動化」の3段階で進めます。
いきなり完璧なメディアを作る必要はありません。まずは営業活動を整理し、そこからコンテンツを生み出し、最後に営業との連携を強化します。
この順序で進めることで、無理なく属人化を解消する仕組みが作れます。
Step1:営業プロセスを可視化し、共通化する
営業活動を分解・整理し、流れを可視化することで、全員が同じ流れ・プロセスで顧客に向き合えるようになります。
まず、現在の営業活動を書き出してみましょう。BtoBの場合であれば「最初の接触→ヒアリング→提案→見積もり→クロージング」といった大まかな流れを整理します。
次に、各ステップで「顧客がどんな情報を求めているか」「営業が何を伝えているか」「顧客がどんな不安を抱えているか」を洗い出します。これは、トップセールスにヒアリングするだけでも十分です。
例えば、以下のように整理できます。
- 最初の接触:顧客は「この会社は何ができるのか」を知りたい
- ヒアリング:顧客は「自社の課題を理解してくれるか」を見ている
- 提案:顧客は「具体的な解決策」と「費用感」を知りたい
- 見積もり:顧客は「価格の妥当性」「他社との違い」を比較している
- クロージング:顧客は「導入後のサポート」「リスク」を不安に思っている
営業プロセスを可視化することで、「誰が営業しても同じ流れで進められる」状態が作れます。また、各ステップで顧客が求める情報が明確になるため、次のステップで必要なコンテンツが明確になり作りやすくなります。
Step2:顧客が知りたい情報をコンテンツ化する
顧客の「質問・不安・比較」を中心に、営業で話している内容を記事化・図解化し、信頼を蓄積します。
Step1で整理した「顧客が知りたい情報」を、一つずつ記事にしていきます。
例えば、以下のようなコンテンツを作ります。
- 「○○とは?初心者でも分かる基礎知識」(最初の接触段階)
- 「○○を選ぶ際の3つのポイント」(比較検討段階)
- 「○○導入の流れと期間」(提案段階)
- 「○○の費用相場と価格の決まり方」(見積もり段階)
- 「○○導入後のよくある質問」(クロージング段階)
営業担当が普段話している内容を、そのまま記事にするだけで構いません。専門的な文章にする必要はなく、むしろ「お客様に話すように書く」ことが重要です。
また、過去に顧客から受けた質問をリスト化し、それをFAQ記事にするのも効果的です。
コンテンツ化することで、営業担当の説明力が「会社の資産」として蓄積されます。見込み客は営業と話す前に記事を読んで理解を深められますし、営業担当は基本的な説明を省いて、より深い提案に時間を使えるようになります。
購入する側にとっても、売る側にとっても、メリットが生まれます。
Step3:営業とオウンドメディアを連動させる(導線最適化)
営業とメディアを分離せず、LP・メール・資料などを一本化し、オンラインとオフラインを繋ぐ導線を設計します。
Step2で作った記事を、営業活動と連動させます。具体的には、以下のような導線を作ります。
オウンドメディア上の導線
- 記事の最後に「資料ダウンロード」や「無料相談」のCTA(行動を促すボタン)を設置
- 資料ダウンロード後、Step2で作った記事をメールで段階的に配信
- 問い合わせフォームから来た見込み客に、関連記事のリンクを送る
- 商談前に「この記事を読んでおいてください」と事前に送る
- 商談中に「詳しくはこの記事で解説しています」と記事を見せる
- 商談後のフォローメールで、関連記事を添付する
- どの記事からの問い合わせが多いかを記録
- 記事を読んだ見込み客とそうでない見込み客の成約率を比較
- データをもとに、記事の内容や導線を改善
オウンドメディアと営業が連動すると、「記事を読んで理解してから問い合わせる」という質の高い見込み客が増えます。営業担当は説明の手間が減り、成約までのスピードも早くなります。
また、データをもとに改善を続けることで、さらに成果が向上するという好循環得を作り出せます。
関連記事:中小企業が成果を最大化するオウンドメディアの全体設計ガイドで属人化を解消する
まとめ|営業を”人に依存させない”仕組みを今から作る
営業の属人化を解消する本質は、仕組み×資産化です。
- 個人の知識を会社の資産に変える。
- 顧客接点を企業の仕組みとして構築する。
- そして、それを自動で動かす
オウンドメディアは、この全てを満たす最も現実的な手段です。
属人化を”防ぐ”のではなく、”超える”仕組みを整えること。それが、次世代の営業戦略の基盤となります。
今からでも遅くありません。あなたの会社の営業を、人に依存させない仕組みに変えていきましょう。
オウンドメディアを“成功する仕組み”に変えるための戦略セッション【無料】
オウンドメディアを始めても成果が出ない最大の原因は、「仕組み(構造)」を決めないまま運用を始めることにあります。
この無料セッションでは、あなたの会社の現状をもとに
- 成果を出すための「目的・導線・体制」の設計ポイント
- どこから着手すべきかの優先順位
- “営業が自動で動く”仕組みの全体像
を整理し、成功の確率を劇的に高める具体的ステップを明確にします。
✅相談後には、自社に必要な戦略の“全体像”と“最初の一歩”が具体的に分かります。
オウンドメディアを“成功する仕組み”に変えるための戦略セッション【無料】
オウンドメディアを始めても成果が出ない最大の原因は、「仕組み(構造)」を決めないまま運用を始めることにあります。
この無料セッションでは、あなたの会社の現状をもとに
- 成果を出すための「目的・導線・体制」の設計ポイント
- どこから着手すべきかの優先順位
- “営業が自動で動く”仕組みの全体像
を整理し、成功の確率を劇的に高める具体的ステップを明確にします。
✅相談後には、自社に必要な戦略の“全体像”と“最初の一歩”が具体的に分かります。
関連記事:中小企業の営業属人化を解消するオウンドメディアの集客戦略を学ぶ