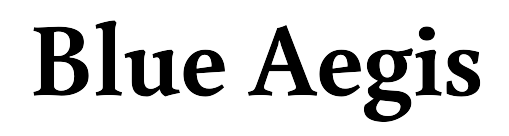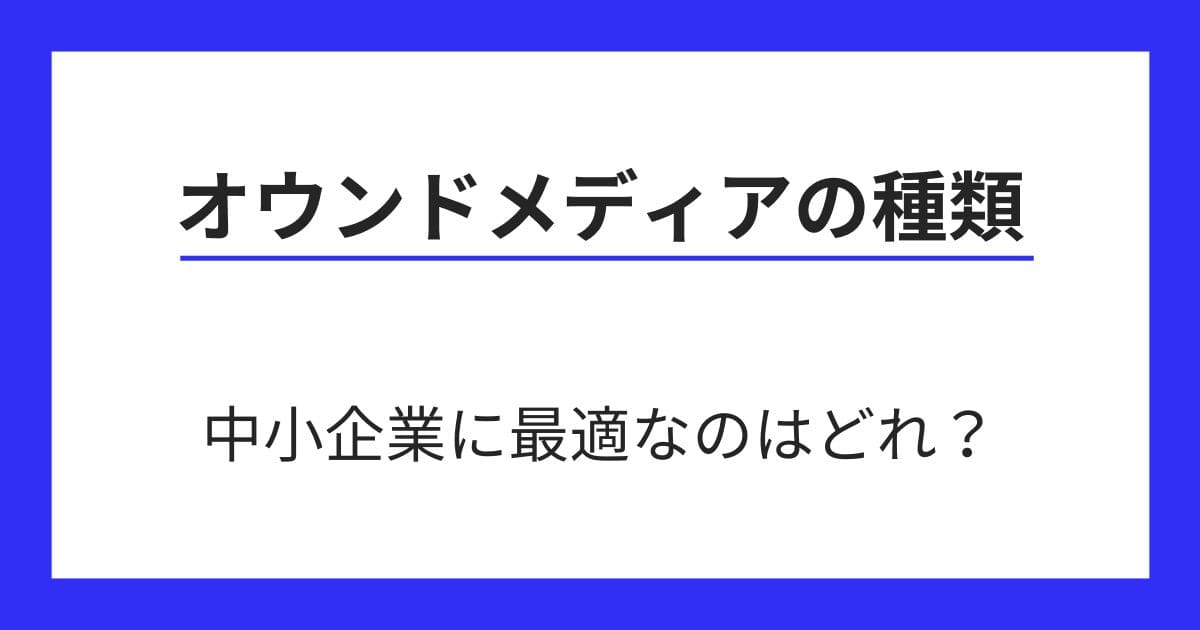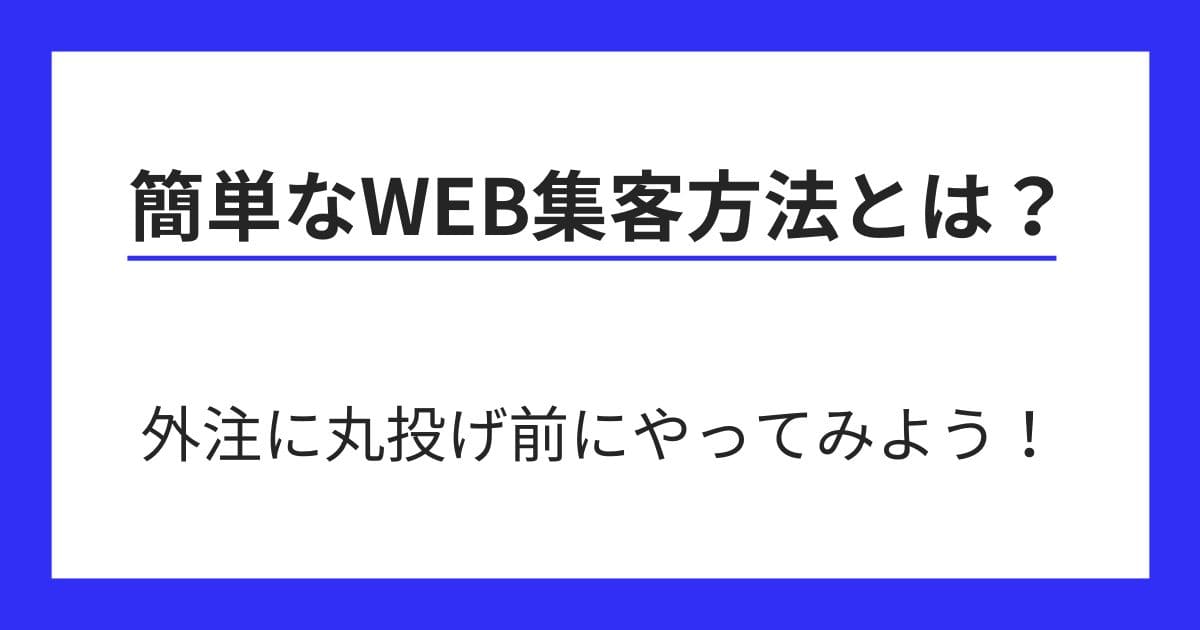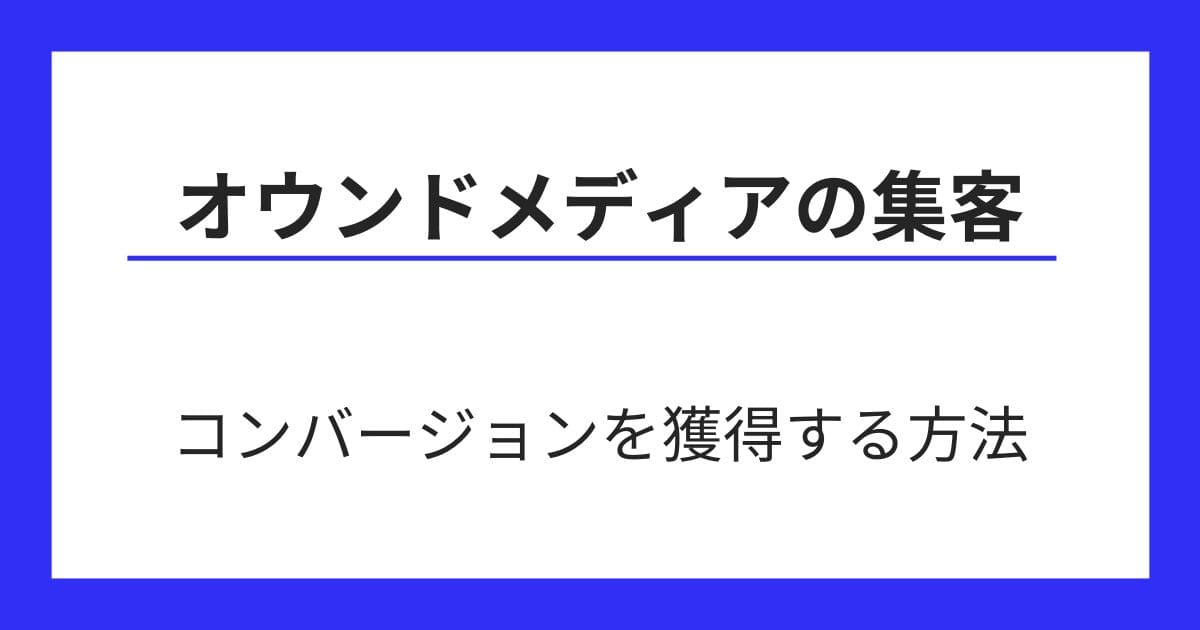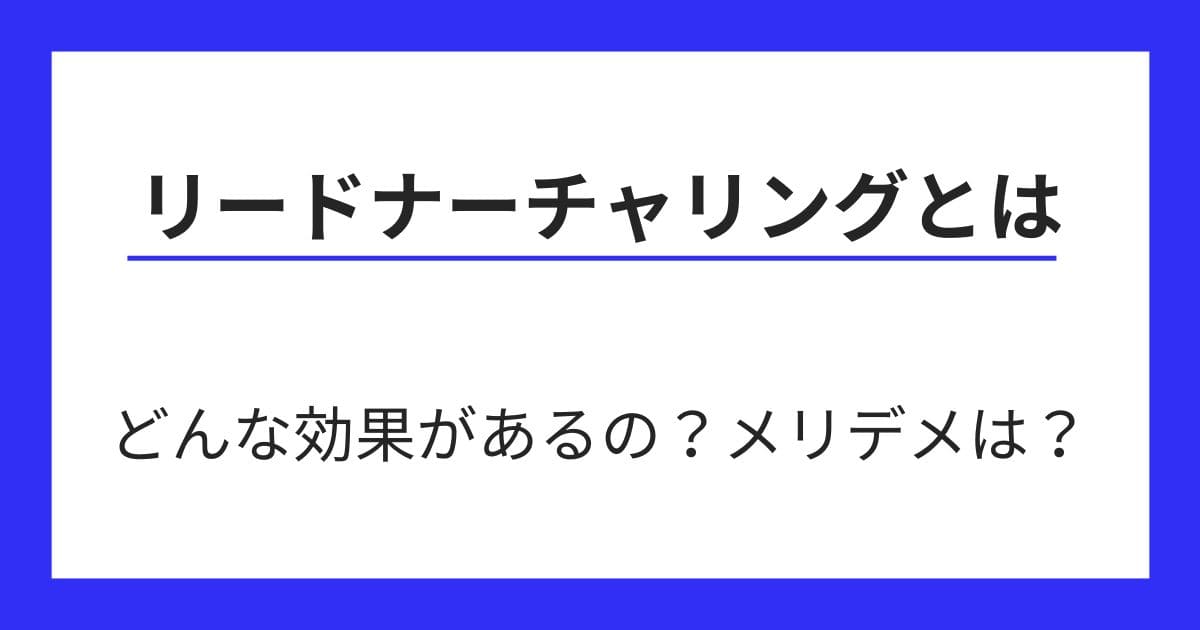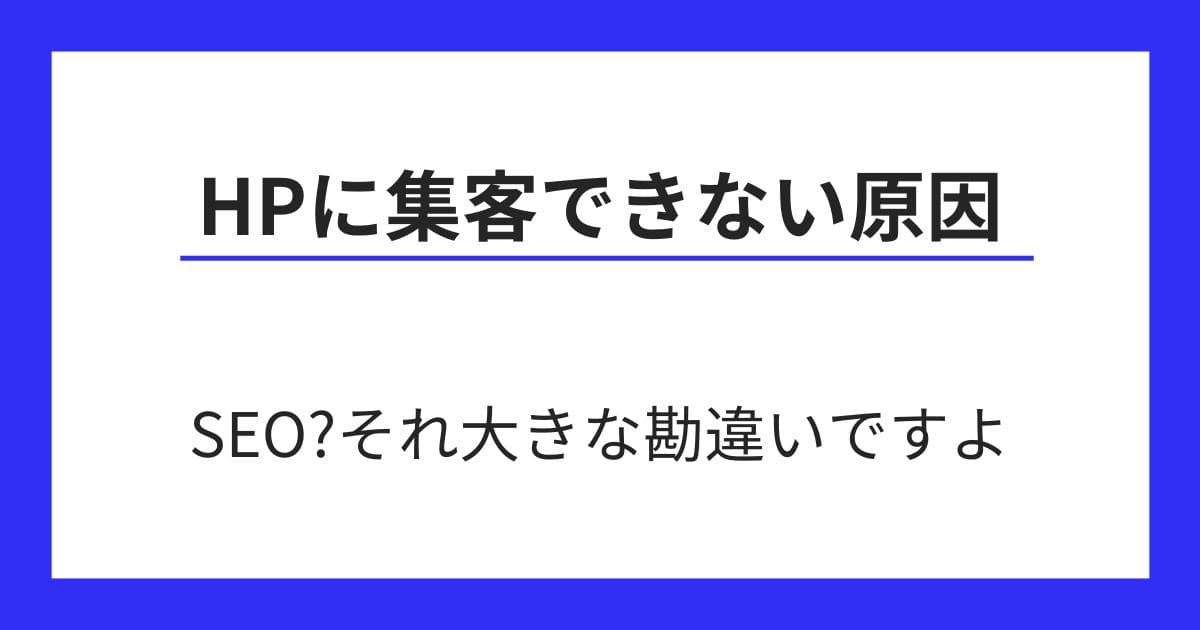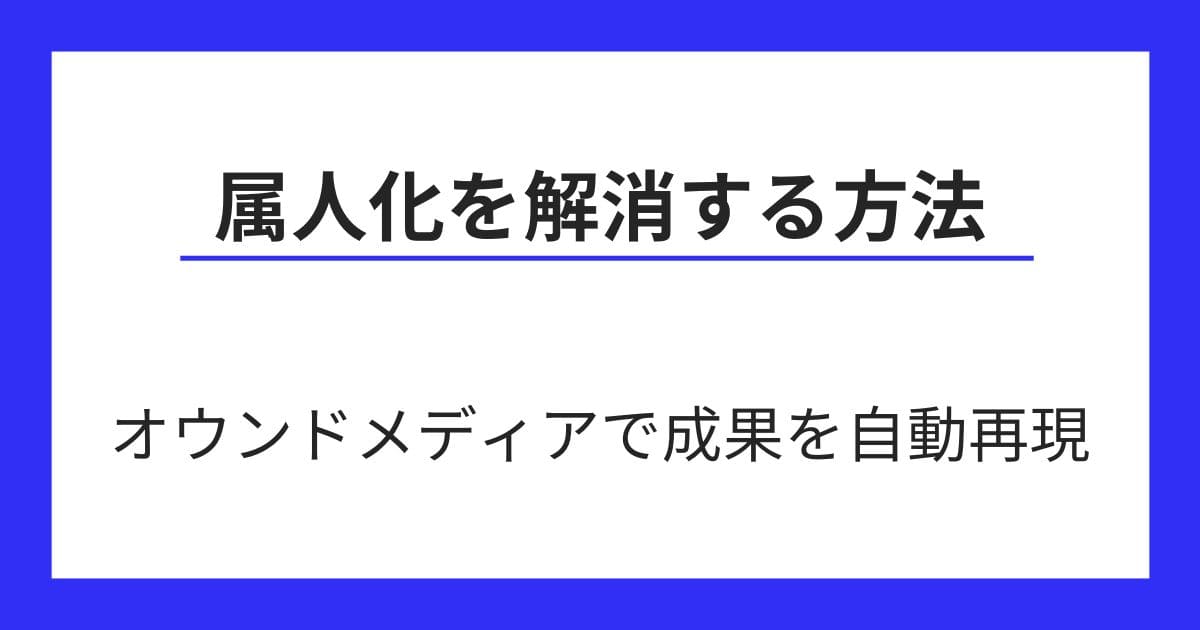オウンドメディアと一言に言っても、その種類も目的も様々だし、定義もよく分からないですよね。
そこでこの記事では、オウンドメディア二度のような種類が存在しているのかを明らかにしつつ、中小企業に最も必要なオウンドメディアとは何か?を解説。
加えて、オウンドメディアに対してトリプルメディア、アーンドメディアとの違いについても合わせて解説しました。
中小企業が戦略的に取り組むべきオウンドメディアの種類を知りたい方は、是非最後までご覧ください。
【結論】オウンドメディアの種類と特徴
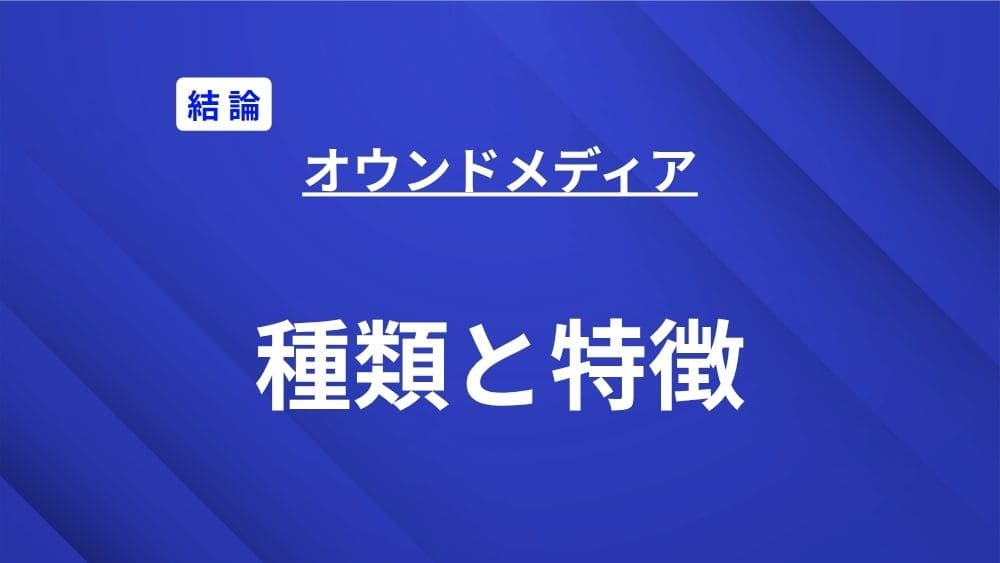
オウンドメディアという言葉は、広義では「ホームページ等を含む、企業が自社所有しているメディア」を意味します。
しかし、日本においては一般的に「オウンドメディア」と表現されるメディアは「企業が自らの知見やノウハウを元に情報発信をして、顧客や見込み顧客、そして関係する人全てとコミュニケーションをする為のWebメディアやWebマガジンの総称」として限定した意味で使われることがほとんどです。
とはいえ、それでもオウンドメディアには複数の種類があり、それぞれの発信形式や目的によって役割が大きく異なります。
ここでは、中小企業でも実際に運用できるオウンドメディアを8種類に整理し、それぞれの特徴と活用方法を分かりやすく解説します。
ホームページ・コーポレートサイト
ホームページ・コーポレートサイトは企業の信頼性を伝え、すべての情報発信の中心となるオウンドメディアの中でも”基盤となるメディア”です。
オウンドメディアとしての認知はあまりメジャーではありませんが、コーポレートサイト(いわゆるホームページ)は、自社の理念・事業内容・実績などを体系的に発信し、すべてのオウンドメディアの母体として機能します。
顧客・求職者・取引先・投資家など、あらゆるステークホルダーが訪れる「企業の顔」としての役割を担っています。
【目的】
- 企業の信頼構築
- 問い合わせ・商談の入り口を作る
- 会社情報の網羅的な提供
【特徴】
- 固定ページ中心で情報の信頼性が高い
- 他のメディア(ブログ・SNS・広告)との連携基盤となる
- 会社概要、サービス紹介、実績などの基本情報を掲載
専門情報発信メディア
見込み客の疑問や課題、自社の持つ知見やノウハウをテーマに、専門的な情報を継続的に発信するオウンドメディアです。
「オウンドメディア」と表現した時に、最も多くイメージされるタイプのメディアではないでしょうか。
SEO(検索エンジン最適化:検索結果で上位表示させる施策)による検索流入を獲得し、集客から見込み顧客の獲得までを担うのが役割です。
「誰かが困っていること」「知りたいこと」に対して、専門家として答えを提供することで信頼と認知を獲得します。
有名どころだと、「トヨタイムズ(トヨタ自動車株式会社)」や「WORKSIGHT(コクヨ株式会社)等があります。
【目的】
- 検索エンジン経由での新規集客
- 見込み顧客の獲得と育成
- 専門性のアピールと信頼構築
【特徴】
- 更新頻度とテーマ設計が成果を左右する
- 中小企業でも取り組みやすい
- 一度公開した記事が長期的な集客資産になる
- ユーザーの悩みや疑問を解決する記事を継続的に発信
採用促進型情報発信メディア
採用候補者ヘ自社の働き方や既に働いている社員からのメッセージなど、”企業文化や働く人の姿”を伝えるオウンドメディアです。
求人情報だけでなく、社員インタビューや社内風景、キャリアパスなどを通じて共感を生み出し、採用数の増加はもちろん、社風や理念に合致した人材を採用する為に運用されます。
「この会社で働きたい」と思ってもらうためのブランディングツールとして機能します。
有名どころだと「mercan(株式会社メルカリ)」や「Discovery Sony(ソニー株式会社)」があります。
【目的】
- 採用ブランディングの形成
- 入社後のミスマッチ防止
- 応募意欲の向上
【特徴】
- 働く人や社内のリアルな姿を発信
- 企業の雰囲気や価値観を伝えられる
- 採用ページ、Wantedly(求人サービス)、社内ブログなどで展開されやすい
- 求職者が知りたい情報を詳しく提供できる
ブランディング型情報発信メディア
企業の理念や商品の世界観を”ストーリー”として伝えるブランディング用のオウンドメディアです。
短期的な集客よりも、中長期的なファン層の形成を目的としています。
商品の機能説明ではなく、「なぜこの商品を作ったのか」「どんな想いが込められているのか」といった背景にある思いや強いこだりをリアルに伝えることで、価格競争に巻き込まれない独自のポジションを確立します。
有名どころだと「となりのカインズさん(株式会社カインズ)」や「ばね探訪(東海バネ工業株式会社)」があります。
【目的】
- 共感・信頼の醸成
- ブランド価値の向上
- ファンやリピーターの創出
【特徴】
- デザイン・ビジュアル・ストーリー性を重視
- SNSや動画コンテンツと連携しやすい
- 企業の理念や商品の世界観を深く伝える
- 直接的な販促よりも感情的なつながりを重視
EC型メディア
自社商品を直接販売する自社構築したECサイトです。
こうしたECサイトは”販売型オウンドメディア”と言えます。
単なる通販サイトではなく、商品情報やレビュー、使い方のコツなど、コンテンツと販売導線を一体化して購買率を高めます。
「情報を得る」と「購入する」が同じ場所で完結するのが特徴です。
EC型のオウンドメディアの有名どころだと「北欧暮らしの道具店(株式会社クラシコム)」や「KALDI COFFEE FARM(株式会社キャメル珈琲)」がありますね。
【目的】
- 自社商品・サービスの直接販売
- リピート購入の促進
- 顧客との直接的な関係構築
【特徴】
- 商品情報・レビュー・コラムを組み合わせた構成
- 情報発信と販売を同時に行える
- 楽天やAmazonなどのモール型ECに比べてSEO対策がしやすい
- 独自のブランド体験を提供できる
メールマガジン(メルマガ)
見込み客や既存顧客に直接情報を届ける、最もパーソナルな発信チャネルです。
顧客との関係性を維持し、再来訪・購買・問い合わせを促すナーチャリング(見込み客の育成)手段、そしてセールスの手段としても機能します。
すでに興味を持っている人に対して、定期的に有益な情報を届けることで信頼関係を深める事の出来るメディアです。
【目的】
- 顧客との関係維持・信頼強化
- 再来訪・再購買の促進
- 新商品やキャンペーン情報の配信
- セールスのきっかけ作り
【特徴】
- 配信設計(頻度・内容・タイミング)が成果を左右
- Webサイトとの連携でリピート率向上が見込める
- 開封率やクリック率などの効果測定がしやすい
- セールス色が強すぎると登録解除されるリスクがある
各種SNSの自社投稿分
X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、YouTubeなどは、一般的には「アーンドメディア(第三者が情報を拡散するメディア)」に分類されます。
しかし、自社アカウントを継続的に運用するという側面では、情報発信の「拡散力」と「即時性」を補完する重要なオウンドメディアだと言えます。
【目的】
- 顧客接点の拡大
- 情報の拡散
- リアルタイム発信
- ユーザーとの双方向コミュニケーション
【特徴】
- 反応スピードが速く、即座にフィードバックが得られる
- 双方向コミュニケーションが可能
- 拡散力が高く、潜在顧客にも届きやすい
【注意点】
- 投稿は流れやすく、長期的な資産化には不向き
- 炎上リスクがあり、慎重な情報発信が必要
- Webサイトやブログと連携することで真価を発揮する
【まとめ】
SNSはオウンドメディアと切り離すのではなく、”入口と拡散装置”として活用するのが理想です。ブログ記事をSNSでシェアしたり、SNSで興味を持った人をWebサイトに誘導したりと、相互に連携させることで効果を最大化できます。
例えば当社であれば、代表三浦のX(@miura_dx)や FaceBook 等のSNSの自社投稿分が、オウンドメディア部分に該当します。
その他のメディア(ホワイトペーパー・動画・導入事例など)
ホワイトペーパー(専門的な情報をまとめたPDF資料)、動画コンテンツ、導入事例など、自社で制作・管理するすべてのコンテンツもオウンドメディアの一部です。
専門性を深く伝え、顧客の理解・信頼・行動を促進します。
特にBtoB(企業向けビジネス)においては、これらのコンテンツによって専門性や再現性を伝えられる為、商談へとつながる重要な役割を果たします。
【目的】
- 専門的情報の提供
- 営業支援
- リード(見込み客)獲得
【特徴】
- 高品質なコンテンツほど長期的な資産として機能
- BtoBではホワイトペーパーが効果的
- BtoC(一般消費者向けビジネス)では動画活用が効果的
- 商談時の説明資料としても活用できる
これら8つ種類のオウンドメディアは、それぞれ異なる目的と特徴、そして強みを持っています。
複数のメリットを組み合わせて効果を最大化するために、大企業のように面で展開したいところですが、中小企業の場合がオウンドメディアを始める際は、すべての種類のメディアを一気に始める必要はありません。
自社の目的と体制に合わせて、優先順位をつけてまずは一点突破することが最善です。
関連記事:オウンドメディアの役割とは何?ホームページとの違い
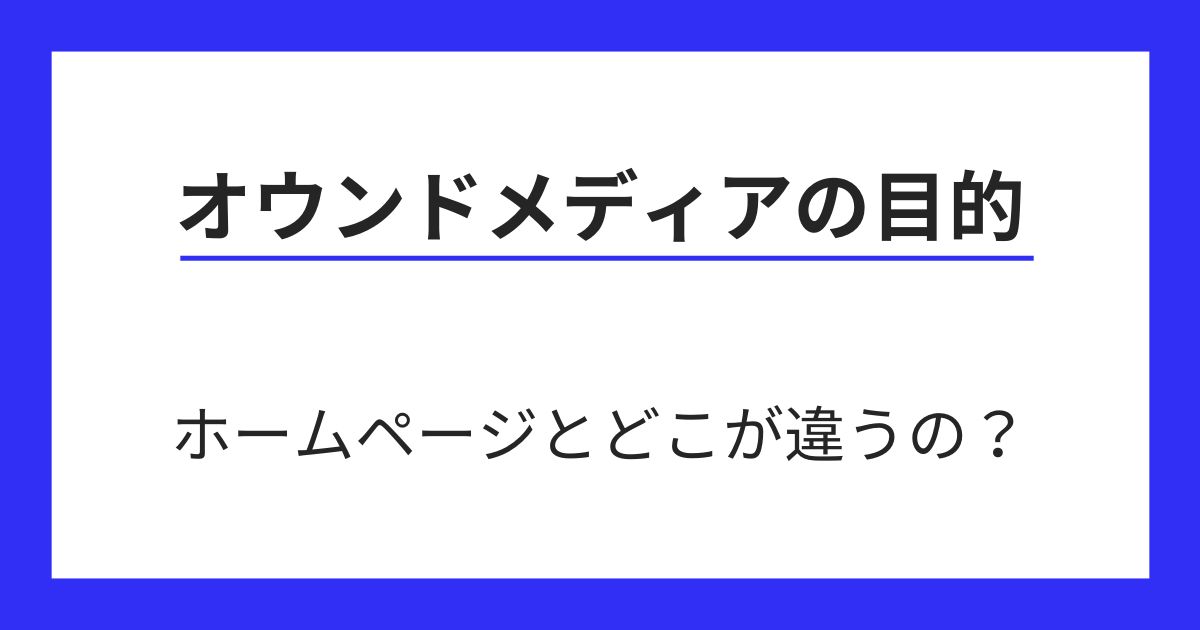
中小企業に最適な種類のオウンドメディア選び3つのポイント
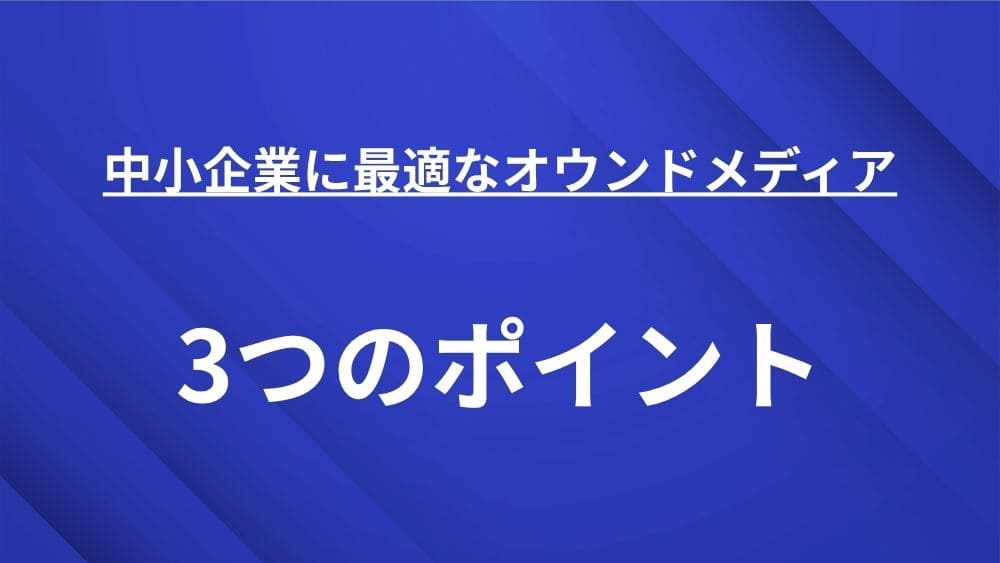
オウンドメディアの種類を理解できると、「自社にはどの種類のオウンドメディアが最適なのか」を判断することができるようになります。
中小企業がオウンドメディアで成果を出すためには、自社の目的に沿ったたオウンドメディアの種類を、戦略的に選択しなければなりません。
ここでは、オウンドメディアを選ぶ際に重要な3つの視点を解説します。
視点①|オウンドメディアの目的を明確にする
オウンドメディアの目的(認知拡大・リード獲得・採用・ブランディングなど)が明確であるほど、作るべきコンテンツや発信内容の方向性が明確になり、成果を出しやすくなります。
また、高い更新頻度が維持しやすくなり、効果測定の基準も定まります。
「誰に」「何を伝えたいのか」を最初に定義することが、成功への第一歩です。
なぜ目的の設定が重要なのか
目的が曖昧なままオウンドメディアを始めると、以下のような問題が発生します。
- どんな記事を書けばいいか分からなくなる
- 成果が出ているのか判断できない
- 社内で協力が得られず、途中で頓挫する
- 費用対効果が測定できず、継続の判断ができない
オウンドオメディアの目的を明確化する事で、これらの問題をクリアにし、最短で成果を出せるオウンドメディアを作る事ができます。
また、目的が明確であれば、「月に10件の問い合わせを獲得する」「採用応募者を年間50名増やす」といった具体的な目標(KPI:重要業績評価指標)を設定でき、進捗を数値で追えるようにもなります。
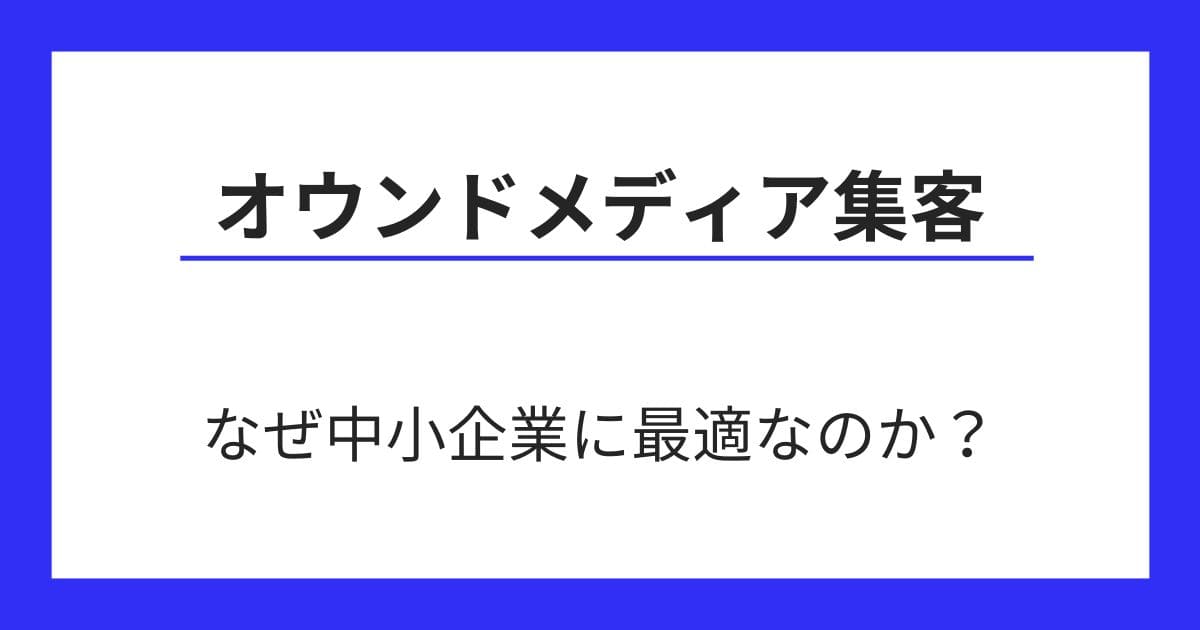
視点②|運用リソースと継続性を考慮する
オウンドメディアはホームページやコーポレートサイト等とは異なり、積極的に記事を更新してゆく動的なメディアです。
記事の更新もSNS発信も、継続できる体制を作ることがとても大切であり、中小企業がオウンドメディアを成功させるための大前提となります。
外注を積極的に活用してリソースを確保する等、現実的な運用体制を設計しておくことで、更新停滞を防ぎ成功確率を大きく引き上げることが出来ます。
オウンドメディアは「始めること」よりも「続けること」の方が圧倒的に難しい施策です。
オウンドメディア運用に必要な業務
オウンドメディアの運用には、想像以上に多くの業務が発生します。
例えば、最もオーソドックスな情報発信型のオウンドメディアだとして、運用に必要な業務を洗い出すと以下のとおりです。
- キーワード調査(どんな言葉で検索されているか調べる)
- 記事の企画・構成作成
- 原稿執筆
- 画像作成・選定
- 校正・編集
- WordPress(ウェブサイト管理システム)への入稿
- アクセス解析(どの記事が読まれているか等の分析)
- 効果測定とレポート作成
- 記事のリライト(書き直し・改善)
- SEO対策の実施
- SNSでの情報発信
- 問い合わせ対応
これらすべてを一人で担当するのは、本業と兼任では現実的に不可能です。
内製でやるにしても外注を活用するにしても、必要なリソースを確保する事は大切です。
中小企業に適した運用体制パターン
では、中小企業に適した運用のパターン例を見てみましょう。
【特徴】
- メリット:外注費がかからない、自社のノウハウが蓄積される
- デメリット:人的負担が大きい、専門知識が必要
- 適している企業:社内にマーケティング経験者がいる、文章を書くのが得意な社員がいる
【最低限の体制例】
- 責任者(方針決定):1名
- ライター(記事執筆):1~2名
- デザイナー(画像作成):兼任でも可
【特徴】
- メリット:プロの品質で効率的、社内負担を軽減
- デメリット:外注費がかかる
- 適している企業:予算は限られているが、質を重視したい
【よくある外注の組み合わせ例】
- 戦略設計・キーワード調査:外注
- 記事執筆:外注
- 編集・最終チェック・投稿:社内
【特徴】
- メリット:最も効率的、専門性の高い運用が可能
- デメリット:費用が最も高い(月30~100万円程度)
- 適している企業:予算に余裕がある、早く成果を出したい
視点③|他のメディアとの連携を前提に設計する
オウンドメディアは単体では成果を最大化することはできません。
ホームページ、SNS、メール、広告などの他チャネルと連携し、メディア全体で成果を最大化する戦略がベストです。
メディア連携が必要な理由1:認知から購買までの導線を作れる
顧客は一度の接触で商品を購入することは稀です。
複数のメディアを積極的に活用して複数の接点を作り出し、徐々に信頼を深めてゆけるように設計します。
- SNSで記事を知る(認知)
- オウンドメディアで詳しい情報を読む(興味・関心)
- メルマガで事例を知る(比較・検討)
- ホームページで問い合わせ(購入)
こうした設計をマーケティング用語では「顧客の旅(カスタマージャーニー)」と呼びますが、この「顧客の旅(カスタマージャーにー)を設計することで、効率的に商談や成約へと導けます。
メディア連携が必要な理由2:メディアの弱点を補える
オウンドメディアを始め各メディアには、それぞれ得手不得手があります。
複数のオウンドメディアを連携する、トリプルメディアを連携することで、それぞれのメディアの弱点を補いつつ、相乗効果を発揮させることができます。
※トリプルメディアについては後述
- オウンドメディア:情報を蓄積し資産化できるが、立ち上げ初期は誰にも見られない
- SNS:投稿を拡散できるが、情報がすぐに流れて資産化しない
- 広告:費用がかかり続ける
これら3つのメディアの連携を意識するだけでも、中小企業がオウンドメディアで着実に成果を出せる可能性が高まります。
オウンドメディアは「孤立した施策」として運用するのではなく、他のマーケティング活動と連携させて、相乗効果を生み出しましょう。
中小企業がまず始めるべきオウンドメディアの種類は?
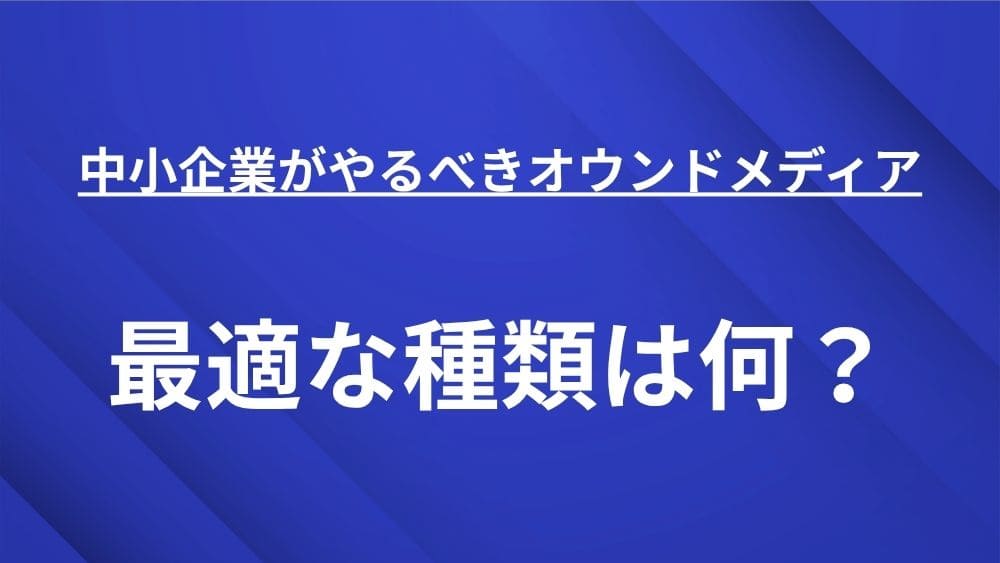
オウンドメディアの選び方を解説しましたが、「結局、どの種類のオウンドメディアを始めればいいの?」と迷う方も多いでしょう。
結論から言えば、中小企業がまず最優先で取り組むべきは、集客を目的としたオウンドメディア(ブログ型情報発信メディア)です。
関連記事:オウンドメディア集客とは?
中小企業が集客型オウンドメディアを最優先すべき理由
理由は極めてシンプルです。
集客を増やし、成約を増やすことで、まずは事業基盤を安定させることが最も大切だからです。
中小企業は、大企業と違って使えるリソース(人・お金・時間)が限られています。
そのため、目的と優先順位を明確化し最小のリソースで最大の成果を出せるように、オウンドメディアに取り組むべきです。
【中小企業が目指すべきオウンドメディアの優先度】
- 【優先度:高】集客・売上確保
- 【優先度:中】ブランディング
- 【優先度:中~低】採用強化
この順序には大きな意味があります。
1. 売上がなければ、他の施策に投資できない
いくら素晴らしいブランディングをしても、いくら魅力的な採用サイトを作っても、売上がなければ事業は継続できません。
オウンドメディアを運用するための人件費や外注費も捻出できなくなります。
まずは集客を増やして売上を安定させ、その収益を使って次の施策に投資する。
これが中小企業の現実的な成長ステップです。
2. 集客型オウンドメディアは効果が測定しやすい
ブランディングや採用の効果は、成果を数値で測定するのが非常に難しくなります。
一方で集客型のオウンドメディアであれば、以下のような数字を簡単に取得できます。
- 月間のアクセス数
- 問い合わせ件数
- 資料ダウンロード数
- 商談化率
オウンドメディアの効果測定に必要なKPIが数字で把握できる、オウンドメディアの成果を明確にすることができます。
3. 集客が安定すれば、ブランディングや採用にも好影響
集客型オウンドメディアを運用していると、副次的にブランディングや採用にも効果が出ることがあります。
- 専門的な記事を継続的に発信することで、自然とブランド力が向上する
- 会社の考え方や専門性が伝わり、共感した人材から応募が来る
- 安定した売上があれば、採用にも積極的に投資できる
つまり、「集客だけ」を目的にしても、結果的に他の目的も達成できる可能性があるから、まずはこの種類のオウンドメディアから取り組むべき、という理由もあるのです。
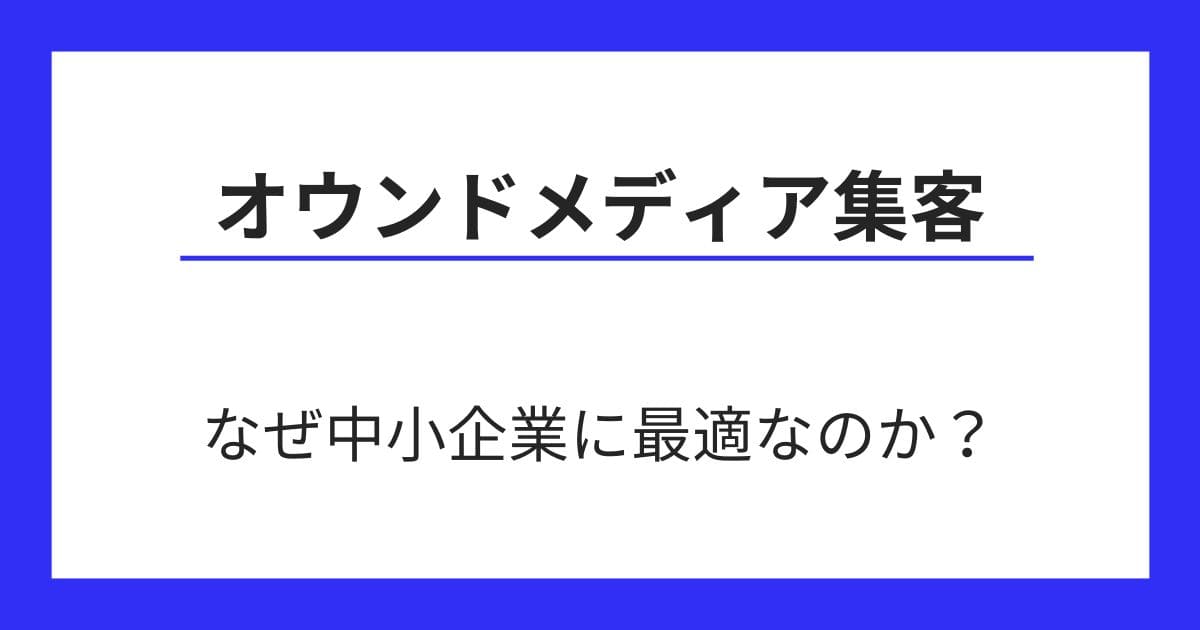
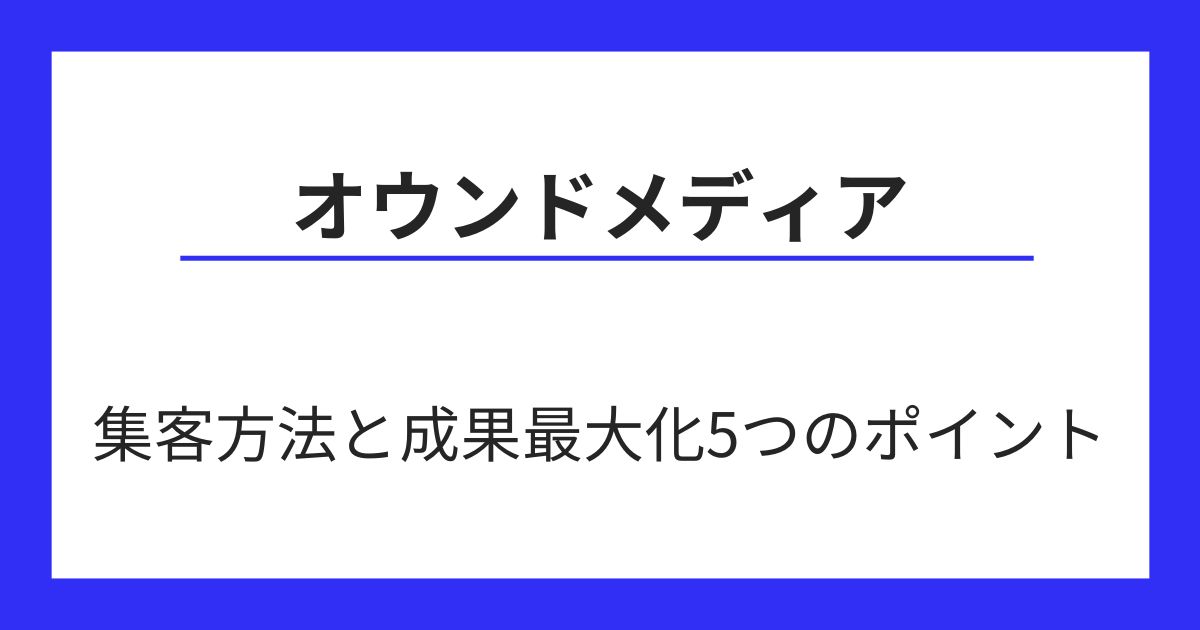
まとめ
オウンドメディアには、ホームページ、ブログ、SNS、メールマガジンなど複数の種類があり、それぞれ「信頼構築」「集客」「関係維持」など異なる目的で運用されます。
中小企業が最も悩む「集客」「売上」を解決し、ビジネスの土台を固めるにはまず、集客を目的としたオウンドメディア(ブログ型情報発信メディア)を始めることです。
まずは明確な目的のオウンドメディアで一点突破し、そこを起点にアーンドメディアや他のオウンドメディアやペイドメディアと連携させることで、より大きな成果を目指す事が出来るようになります。
オウンドメディアを始める前に、失敗しないための設計を描きませんか?
オウンドメディアを立ち上げたい企業様に、「目的・体制・導線」の3つの軸から、成果につながる戦略を一緒に整理する無料セッションをご提供しています。
制作に入る前だからこそ、成功確率を大きく高める設計が重要です。
まずは貴社に合わせた“勝てるメディア戦略”を一緒に考えましょう。
オウンドメディアを始める前に、失敗しないための設計を描きませんか?
オウンドメディアを立ち上げたい企業様に、「目的・体制・導線」の3つの軸から、成果につながる戦略を一緒に整理する無料セッションをご提供しています。
制作に入る前だからこそ、成功確率を大きく高める設計が重要です。
まずは貴社に合わせた“勝てるメディア戦略”を一緒に考えましょう。